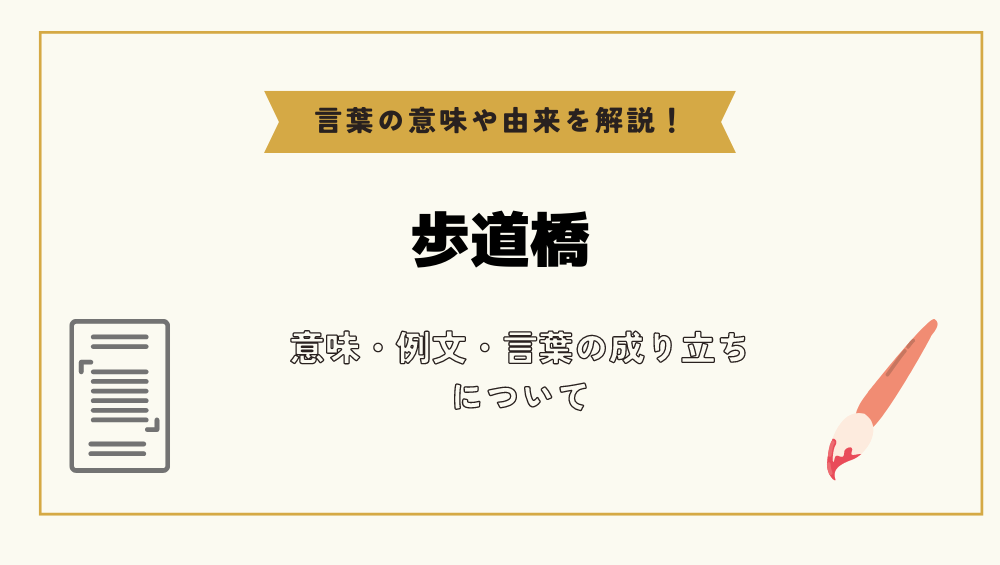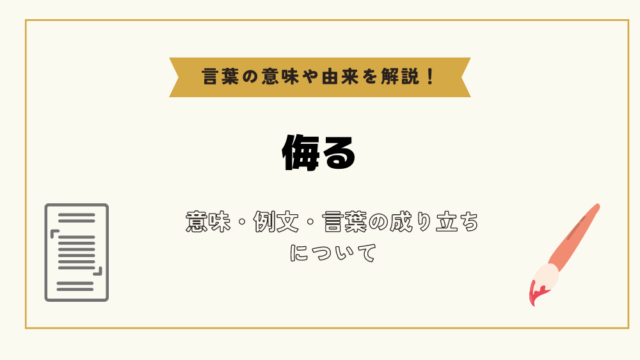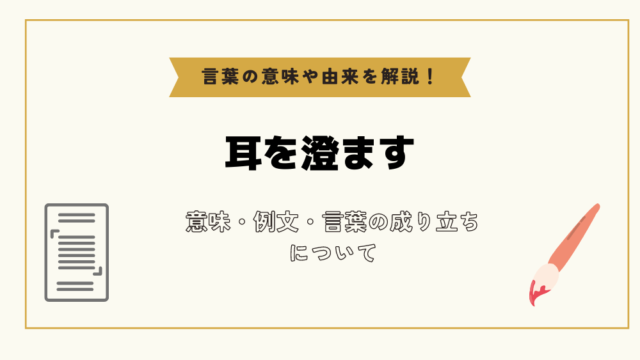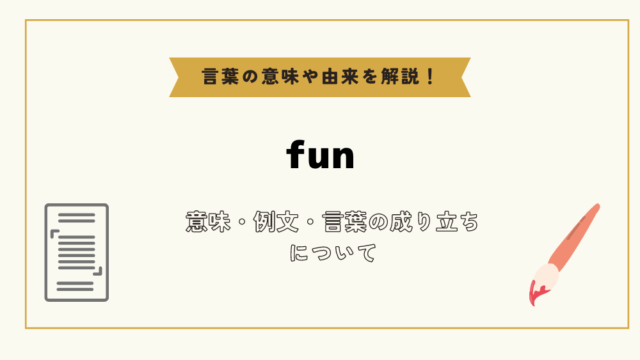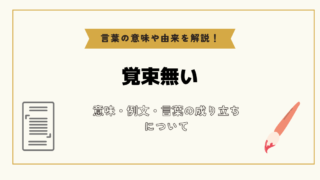Contents
「歩道橋」という言葉の意味を解説!
「歩道橋」とは、道路や鉄道などの交通施設に設置されている、歩行者専用の橋のことを指します。
歩道橋は、道路や鉄道を横断する際に歩行者が安全に通行できるようにするために作られています。
一般的に歩道橋は、道路の両脇に取り付けられた階段やエスカレーター、エレベーターを通じて歩行者が上下することができます。
歩道橋の上部には屋根や手すりが設置されており、天候や高さの違いによる危険を回避することができます。
歩道橋は交通安全の観点から非常に重要であり、特に学校や駅周辺、繁華街など人の往来が多い場所に設置されています。
歩道橋の設置により、歩行者は車や列車といった交通手段との接触を避けることができ、安心して移動することができます。
「歩道橋」の読み方はなんと読む?
「歩道橋」は、ほどうきょうと読みます。
ひらがな表記で「ほ・どう・きょう」となります。
この読み方は一般的なものであり、全国的に通用します。
また、「歩道橋」の「橋」は、「はし」と読むこともありますが、この場合は複数の橋で構成されるものを指すことが多いです。
一般的な意味での歩行者専用の橋を指す場合は、「ほどうきょう」という読み方が一般的です。
「歩道橋」という言葉の使い方や例文を解説!
「歩道橋」という言葉は、以下のような使い方があります。
例文1: 駅前には便利な歩道橋が設置されています。
例文2: 歩道橋を渡るときは、周囲の安全に十分注意しましょう。
例文3: 歩道橋の利用は、交通事故を予防するためにも重要です。
「歩道橋」は、歩行者が安全に交通を横断するために利用する橋を指す言葉です。
この言葉は交通安全の文脈や街のインフラに関する話題でよく使用されます。
「歩道橋」という言葉の成り立ちや由来について解説
「歩道橋」という言葉は、「歩道」と「橋」の組み合わせで成り立っています。
「歩道」は歩行者が通行するための道路のことを指し、「橋」は川や道路などをまたいで架けられた構造物を指します。
「歩道橋」の由来について具体的な起源は不明ですが、歩道橋の必要性が叫ばれたのは、都市化が進み車や列車といった交通手段が増えた20世紀初頭からです。
交通の安全確保や歩行者の利便性向上を目的に、多くの国や地域で歩道橋の建設が行われるようになりました。
「歩道橋」という言葉の歴史
「歩道橋」は、交通事故の発生を減らすために必要な施設として、20世紀初頭から徐々に普及してきました。
当初は主に都市部や交通量の多いエリアに設置されていましたが、その後、交通安全意識の高まりと共に地域全体に広がりました。
日本では、東京や大阪などの大都市で先駆的に歩道橋が建設されました。
その後、全国各地で交通安全のために歩道橋の整備が進んでいます。
現在では、歩道橋は道路交通の一部として不可欠な存在となっており、歩行者の安全確保に大きく貢献しています。
「歩道橋」という言葉についてまとめ
「歩道橋」とは、歩行者が道路や鉄道を安全に横断するために使用される橋のことを指します。
歩道橋は、歩行者の安全確保や交通事故の予防に重要な役割を果たしています。
日本全国で広く利用されており、交通安全意識の高まりと共に整備が進められています。
歩道橋の設置により、歩行者は安心して移動することができ、交通事故を減らすことができます。
「歩道橋」という言葉は、日常生活や交通安全の文脈で頻繁に使われることがあります。