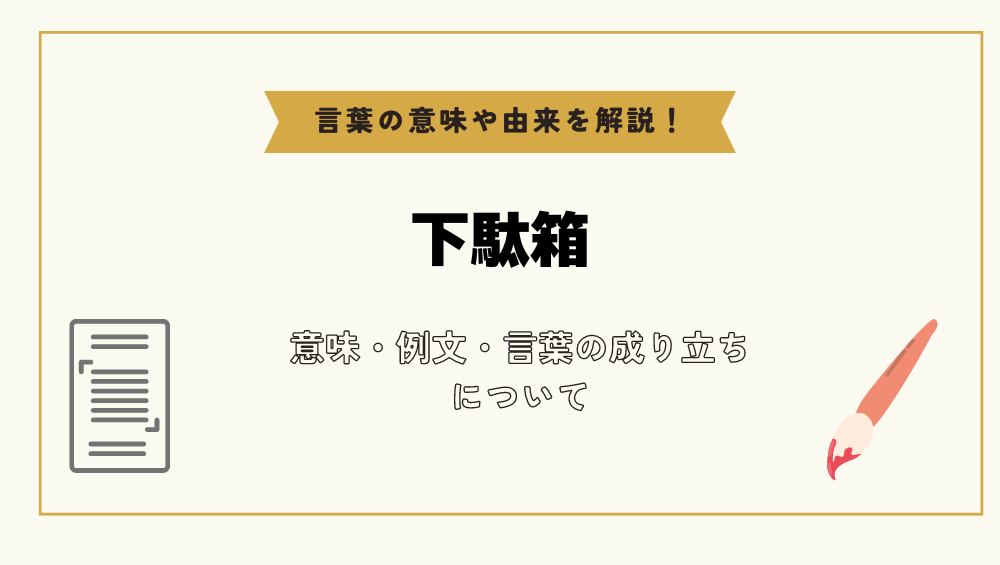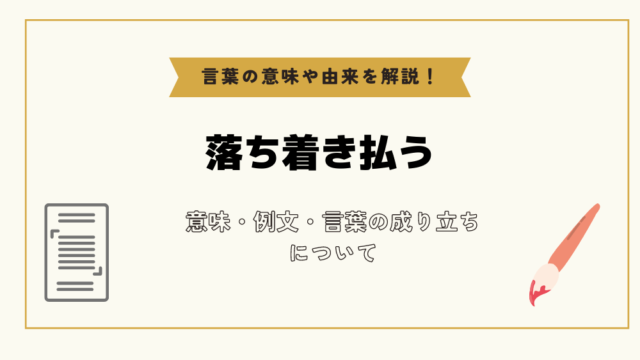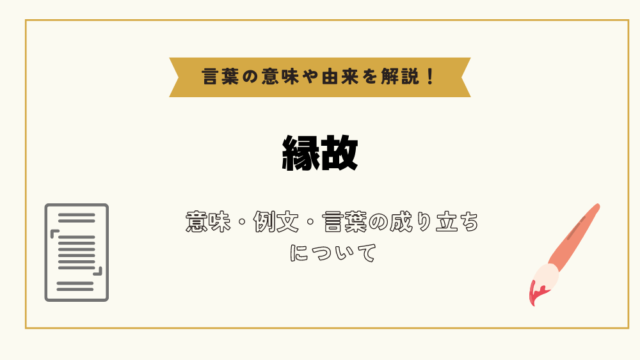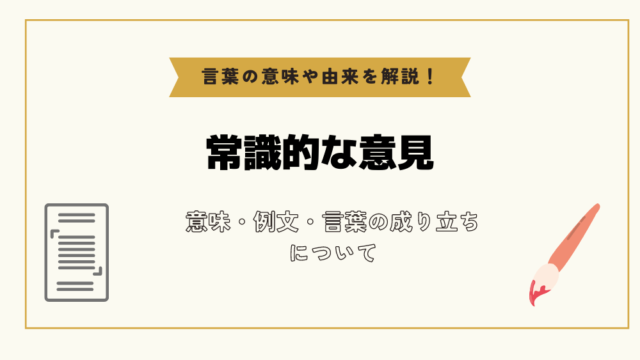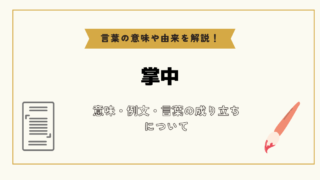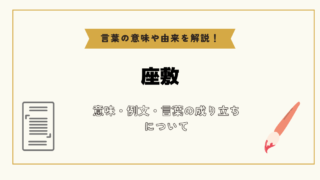Contents
「下駄箱」という言葉の意味を解説!
下駄箱(げたばこ)とは、履物である下駄を保管・整理するための箱を指します。日本の伝統的な建築物や学校、宿泊施設などでよく見かけるものです。「下駄箱」は、靴をしまうための箱のことを一般的に指す言葉として使われます。
「下駄箱」という言葉の読み方はなんと読む?
「下駄箱」という言葉は、「げたばこ」と読みます。漢字の「下駄」は「げた」と読みますが、「下駄箱」では「げたばこ」となります。日本語の特徴の一つである「送り仮名」と呼ばれる読み方のルールに基づいています。
「下駄箱」という言葉の使い方や例文を解説!
「下駄箱」という言葉は、日常会話や文章の中でよく使われます。例えば、学校で友達との会話で「下駄箱に本を入れてきた」と言う場合、その友達が学校で使う下駄箱に本を入れていたことを表現しています。また、宿泊施設での会話で「下駄箱に靴を入れてください」と言われた場合、宿泊客は提供された下駄箱に靴をしまう必要があることを意味します。
「下駄箱」という言葉の成り立ちや由来について解説
「下駄箱」という言葉の成り立ちについてははっきりとした由来はありませんが、日本の伝統的な生活様式や文化に基づいたものです。日本では、靴を脱いで履物(下駄など)を使用することが一般的であり、そのために下駄を保管・整理する必要が生じました。そして、それを収納する箱が「下駄箱」と呼ばれるようになったのでしょう。
「下駄箱」という言葉の歴史
「下駄箱」という言葉の具体的な歴史については明確な記録はありませんが、日本の伝統的な暮らし方と密接に関わっています。特に、学校や宿泊施設での普及が大きく、長い歴史の中で定着してきたものです。現代では、靴を脱ぐ文化が少なくなってきているため、下駄箱の使い方も変化してきています。
「下駄箱」という言葉についてまとめ
「下駄箱」という言葉は、日本の文化や生活様式と深く関わっています。その意味は「下駄を保管・整理するための箱」を指し、特に学校や宿泊施設でよく使われます。読み方は「げたばこ」となります。日本の伝統的な暮らし方に根付いたものであり、日本の歴史と結びついた言葉です。現代では、靴を脱ぐ習慣が少なくなってきたため、下駄箱の使用法も変化しています。下駄箱は、日本人の生活に密着した大切な存在なのです。