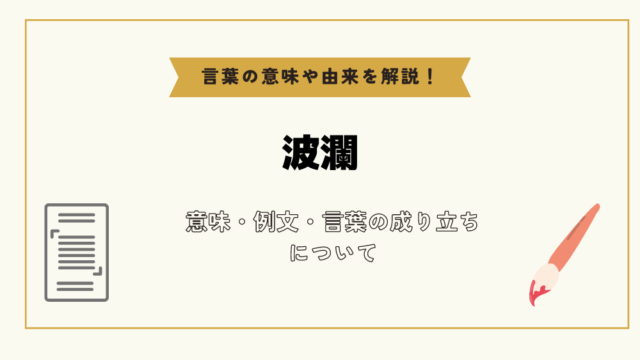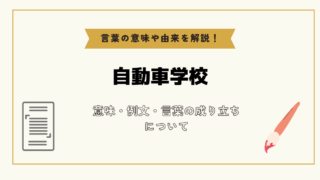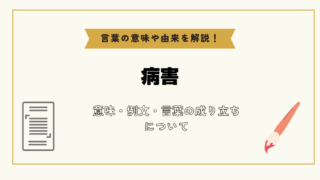Contents
「親不知」という言葉の意味を解説!
「親不知」という言葉は、歯科医や口腔外科によく関わる言葉です。
具体的には、親知らずとも呼ばれる「第三大臼歯」を指す言葉です。
親知らずは、通常の大きさの歯とは異なり、上下左右の奥に位置しており、日本人の場合、18歳以上になってから生えてくることが一般的です。
「親不知」という言葉の読み方はなんと読む?
「親不知」という言葉は、「おやしらず」と読みます。
現代の日本語では、「しんふち」という読み方も一部で用いられることもありますが、一般的には「おやしらず」と読まれることが多いです。
「親不知」という言葉の使い方や例文を解説!
「親不知」という言葉は、一般的には歯科医や口腔外科の専門的なコミュニケーションで使用されます。
例えば、歯科医から「親不知が生えてきている」と言われた場合、自分の奥の歯が生えてきていることを意味します。
また、「親不知を抜く必要がある」と言われた場合は、歯を抜く手術が必要な状態になっていることを指します。
「親不知」という言葉の成り立ちや由来について解説
「親不知」という言葉の成り立ちは、先ほども説明した通り、日本語の「親知らず」という言葉が源となっています。
なぜ「親知らず」という言葉から「親不知」という表現に変わったのかについては明確な由来はありませんが、口語化や短縮化の影響などが考えられます。
「親不知」という言葉の歴史
「親不知」という言葉の歴史は、正確な年代や起源はわかっていません。
ただし、「親知らず」という言葉自体は、江戸時代には既に使われていたと言われています。
現代では、親不知と表記されることが一般的ですが、これまでの流れや言葉の変化についての詳しい研究はまだ行われていません。
「親不知」という言葉についてまとめ
「親不知」という言葉は、歯科医や口腔外科といった分野で頻繁に使用される言葉です。
親不知とは、大人になってから生えてくる「第三大臼歯」のことを指します。
読み方は「おやしらず」が一般的ですが、「しんふち」という読み方も一部で使われています。
歯科医療の現場では、「親不知の生えてきている」「親不知を抜く必要がある」という言葉がよく使われます。
由来や歴史についてははっきりとわかっているわけではありませんが、日本語の変化や短縮化の影響により「親不知」という表現が生まれたと考えられます。