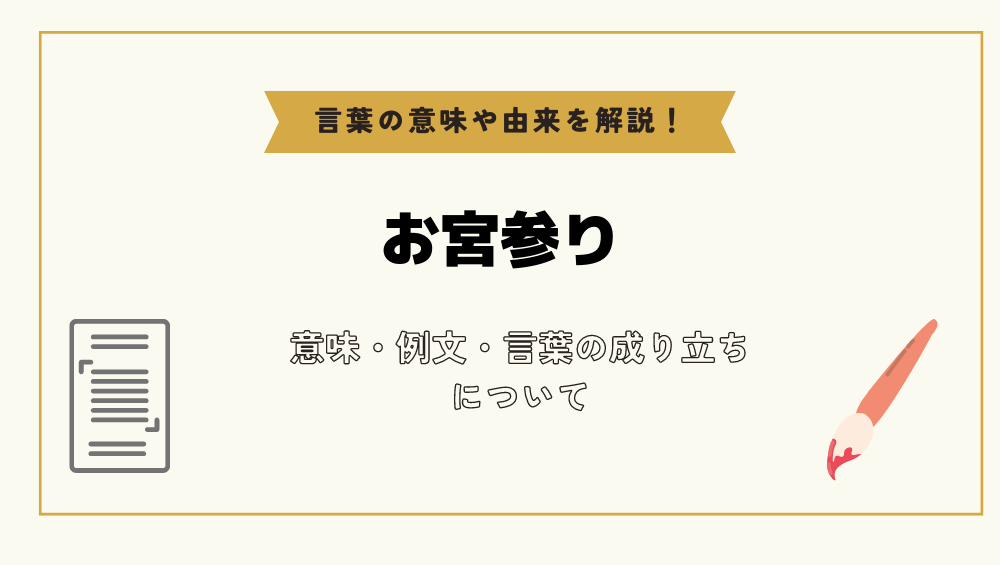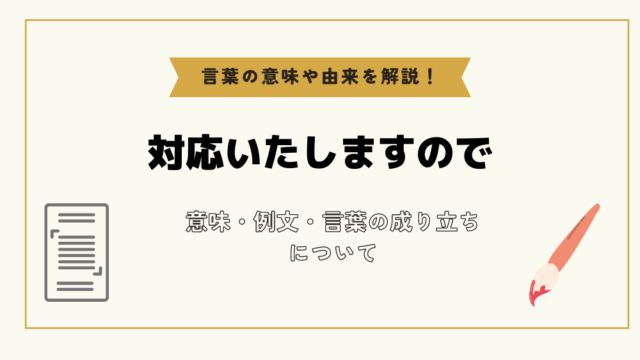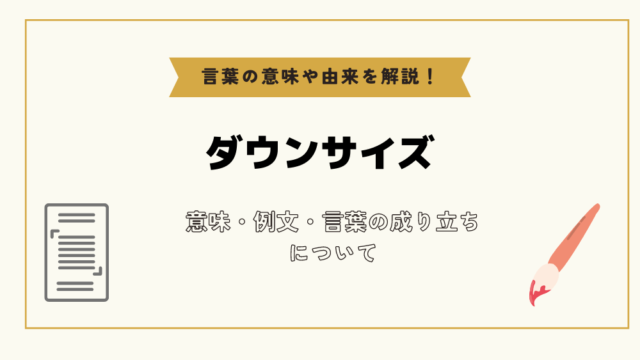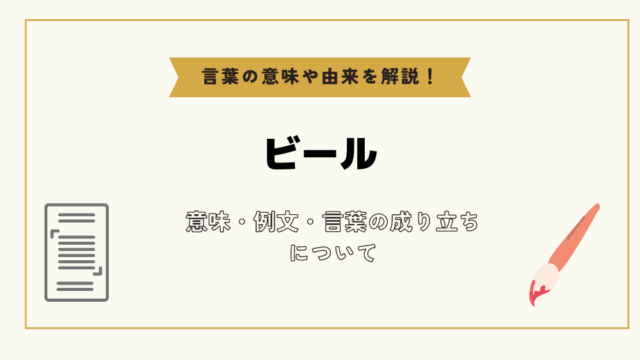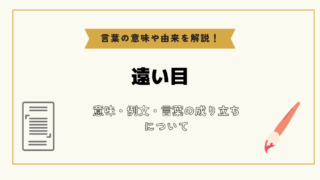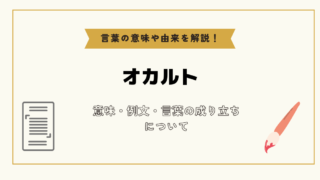Contents
「お宮参り」という言葉の意味を解説!
「お宮参り」とは、日本の伝統行事の一つで、生後30日程度の赤ちゃんを宮や寺院に参拝させることを指します。
この儀式は、赤ちゃんの安全祈願や感謝の気持ちを表すために行われます。
親子の絆を深め、新しい生活の始まりを祝福するものとして、多くの方々に愛されています。
「お宮参り」の読み方はなんと読む?
「お宮参り」は、「おみやまいり」と読みます。
この言葉は、日本の伝統的な行事であるため、古風な読み方をされることが多いです。
また、「お祓い」とも呼ばれることもありますが、意味や行われる儀式には微妙な違いがあります。
「お宮参り」という言葉の使い方や例文を解説!
「お宮参り」という言葉は、主に赤ちゃんが生後30日程度に行われる参拝の儀式を指すことが一般的です。
例文としては、「私たちは先日、息子のお宮参りを行いました」というように使用します。
このような言葉を使うことで、特別な意義を持つ行事であることを伝えることができます。
「お宮参り」という言葉の成り立ちや由来について解説
「お宮参り」の成り立ちについては諸説ありますが、一つは古代日本の巫女制度の影響があると言われています。
また、神社仏閣に参拝することで、神仏の加護を受けると考えられていました。
さらに、赤ちゃんの清らかな心を神聖視し、祈りを捧げることで成長と安全を願う風習が、お宮参りの由来とされています。
「お宮参り」という言葉の歴史
「お宮参り」という言葉は、古代から行われてきたとされています。
当時は国家神道や民間信仰などにより、神社や寺院に参拝を行うことが一般的でした。
江戸時代には、将軍家の子供の成長を祈願するために広まり、庶民の間にも浸透していきました。
現代では、お宮参りは日本の伝統行事の一つとして大切にされています。
「お宮参り」という言葉についてまとめ
「お宮参り」とは、生後30日程度の赤ちゃんを宮や寺院に参拝させる伝統的な行事です。
赤ちゃんの安全祈願や新しい生活の始まりを祝福するために行われます。
読み方は「おみやまいり」といいます。
使い方は、「お宮参りを行う」というように使用されます。
由来は古代の巫女制度や神社仏閣への参拝習慣に由来し、古くから行われてきた歴史があります。
伝統的でありながらも、現代でも多くの方々に愛されている貴重な行事です。