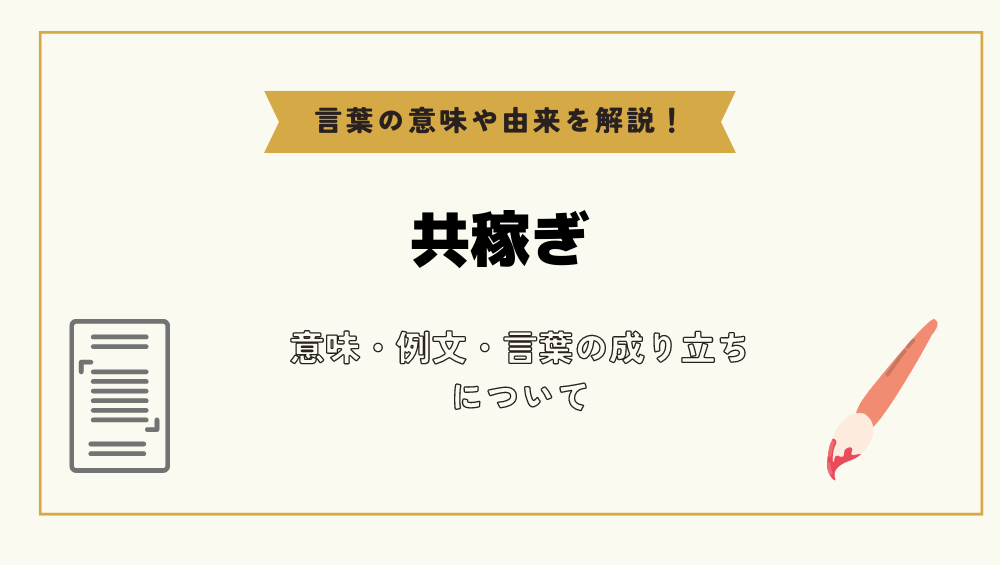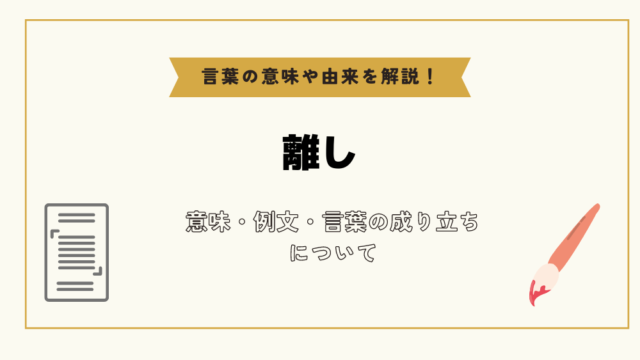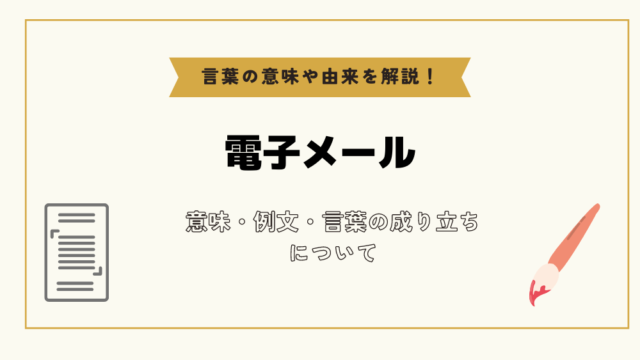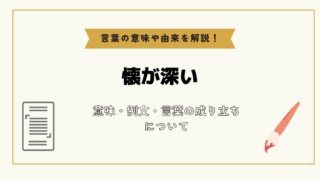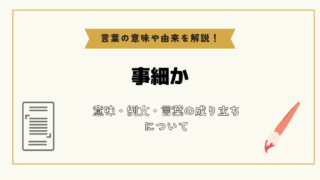Contents
「共稼ぎ」という言葉の意味を解説!
「共稼ぎ」とは、夫婦やパートナーなどが一緒に働いて収入を得ることを指す言葉です。
具体的には、夫婦やパートナーがそれぞれの仕事で収入を得ながら家計を支えることを指します。
共同で稼ぐことで経済的な負担を分担し、生活の安定や豊かさを目指すことができます。
共稼ぎは現代社会において一般的な働き方であり、男女平等やキャリア形成の観点からも重要です。
また、共稼ぎは家族の絆を深める機会でもあり、お互いの理解や協力を促進することができます。
共稼ぎは、家計の安定やパートナーシップの強化に役立つ大切な働き方です。
。
「共稼ぎ」という言葉の読み方はなんと読む?
「共稼ぎ」は「ともかせぎ」と読みます。
この読み方は一般的で、日本語の発音ルールに従ったものです。
一部漢字の読み方が複雑な場合もありますが、共稼ぎの場合は比較的読みやすい言葉です。
共稼ぎという言葉は口語的な表現であり、親しみやすさを感じさせるものです。
身近な言葉として認識されているため、日常会話でも頻繁に使われています。
「共稼ぎ」という言葉の使い方や例文を解説!
「共稼ぎ」という言葉は、次のような文脈で使われます。
例文1:彼とは共稼ぎで生活しています。
。
例文2:共稼ぎが当たり前の時代になりました。
。
例文3:共稼ぎが家庭の経済基盤を支えます。
。
例文4:共稼ぎを実現するための働き方改革が進んでいます。
共稼ぎは、夫婦やパートナー同士が一緒に働く状況を指すため、主に家庭や仕事に関する話題で使用されます。
言葉の意味や使い方を理解しておくことで、会話や文章で適切に表現することができます。
「共稼ぎ」という言葉の成り立ちや由来について解説
「共稼ぎ」という言葉は、戦後の日本における家族の働き方の変化に伴い生まれました。
従来は男性が一人で家計を支えるのが一般的でしたが、女性の社会進出や世帯の経済的な必要性の高まりから、夫婦やパートナー同士が一緒に働くことが増えました。
このような変化により、「共稼ぎ」という言葉が広まりました。
共同で稼ぐことで家庭の経済的な安定を図ることが求められるようになり、さまざまな働き方やサポート制度も整備されてきました。
「共稼ぎ」という言葉の歴史
共稼ぎが一般的な働き方となったのは、戦後の経済成長期からです。
当時は男性が主に会社で働き、女性は専業主婦として家庭に専念するケースが多かったですが、高度経済成長によって女性の社会進出や働く意欲が高まりました。
そして、1970年代以降には共稼ぎが一般的な働き方となり、家族の経済的な安定や生活の充実を目指すための選択肢として広まりました。
現代では、男女平等やキャリア形成の観点からも共稼ぎが重要視されており、夫婦やパートナー同士が一緒に働くことが当たり前となっています。
「共稼ぎ」という言葉についてまとめ
「共稼ぎ」とは、夫婦やパートナーが一緒に働き収入を得る働き方のことを指します。
家計の安定やパートナーシップの強化に役立つ大切な働き方であり、現代社会において一般的な形態です。
「共稼ぎ」は「ともかせぎ」と読み、口語的で親しみやすい表現です。
言葉の成り立ちや由来は、夫婦やパートナー同士が一緒に働く状況の変化によって生まれたものであり、日本の戦後から現代に至るまでの社会的な変化を反映しています。