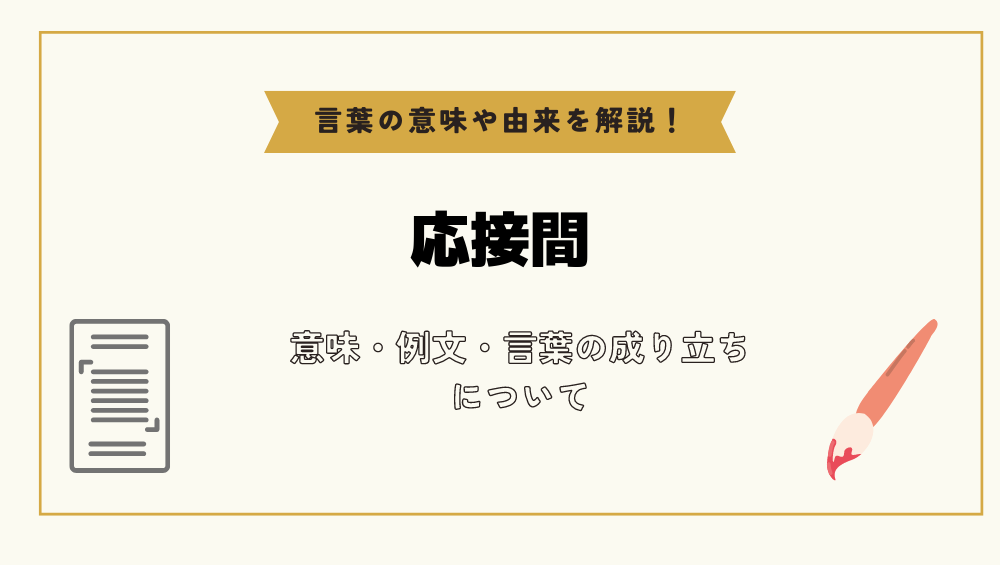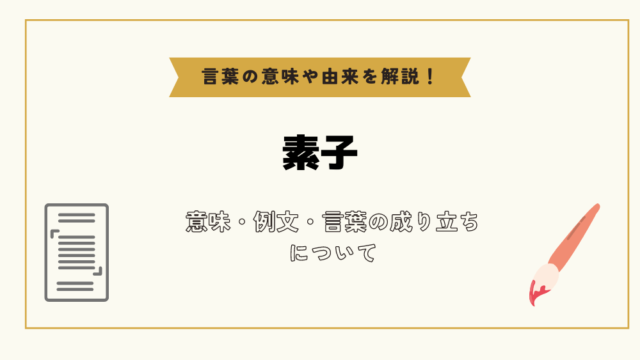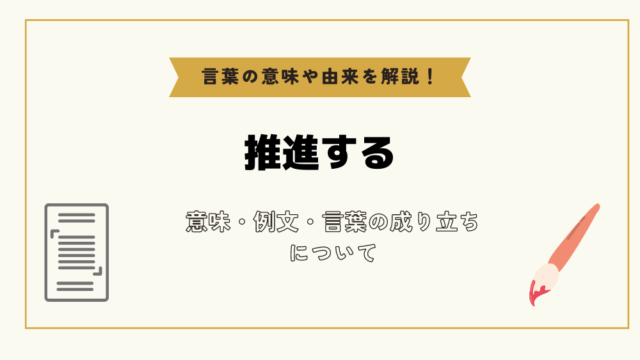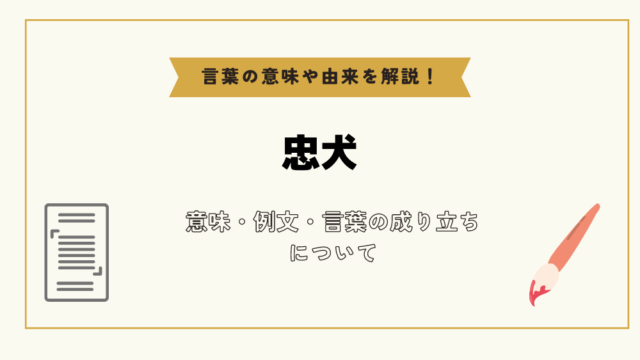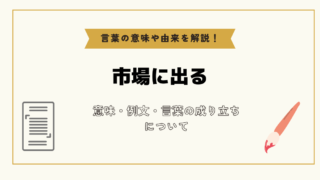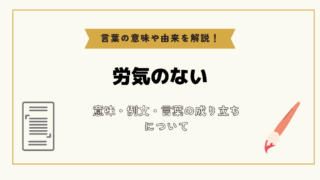Contents
「応接間」という言葉の意味を解説!
「応接間」とは、一般的には日本の伝統的な住宅において、来客を迎えるための部屋のことを指します。
一般民家でも、豪華な庭園を見せるために設けられていることが多いです。
応接間は、大切な来客を迎え入れるための特別なスペースです
。
応接間には、通常よりも広くて落ち着いた雰囲気を持ち、美しく飾られた家具や花、掛け軸などが置かれています。
来客との会話や商談を行う場所として、重要な役割を果たす場所です。
「応接間」という言葉の読み方はなんと読む?
「応接間」は、「おうせつま」と読むことが一般的です。
日本の伝統的な言葉であるため、正確な読み方を知っていることは、文化やマナーに関心を持つ上でも大切です。
「応接間」という言葉の使い方や例文を解説!
例えば、ビジネスの商談を行う際には、応接間が活用されることがあります。
相手を迎え入れる場所として、落ち着いた雰囲気を提供することで、信頼関係を築くことができます。
応接間は、重要な会議や商談の場で使用されることが多い
。
また、観光目的で訪れる外国人旅行客にも、応接間を利用して日本の伝統文化を紹介することがあります。
日本のおもてなしの心を感じさせる場所として、喜ばれています。
「応接間」という言葉の成り立ちや由来について解説
「応接間」は、元々は貴族や武士の間取りの一部として存在していました。
江戸時代には、一般の商家でも応接間が設けられるようになりました。
その由来は、来客を迎え入れる場所という役割にあります。
応接間の由来は、来客を迎え入れるための場所という役割にあります
。
応接間は、来客との円滑な会話や商談を行うためのスペースとして発展してきました。
日本独自の文化として、応接間は広く親しまれている存在です。
「応接間」という言葉の歴史
「応接間」の歴史は、古くて複雑です。
日本の伝統的な建築文化や家屋のスタイルと深く関わっているため、その変遷も見逃せません。
応接間の歴史は、日本の建築文化と密接に関わっています
。
江戸時代には、応接間は一般庶民にまで広まり、広いスペースや美しい庭園が付随するようになりました。
そして現代に至っても、応接間のスタイルや概念は受け継がれています。
「応接間」という言葉についてまとめ
「応接間」とは、来客を迎え入れるための特別な部屋であり、重要な会議や商談の場として使用されることが多いです。
一般的には、「おうせつま」と読みます。
日本の伝統的な建築文化と密接に関わっており、歴史的な背景を持っています。
応接間は、日本の文化やおもてなしの心を感じさせる大切なスペースです
。
観光客や外国人旅行者にも喜ばれており、日本の伝統文化の一つとして大切にされています。