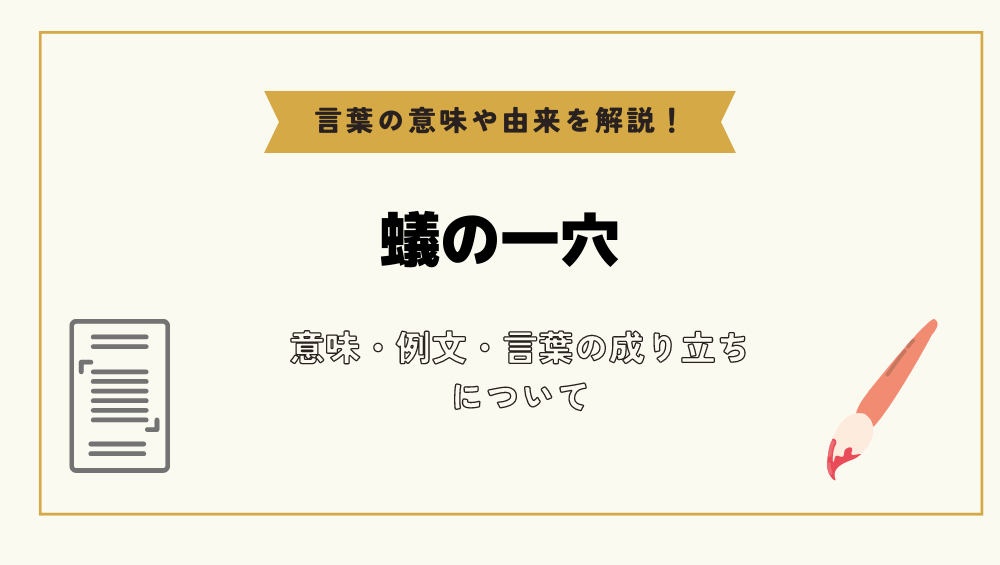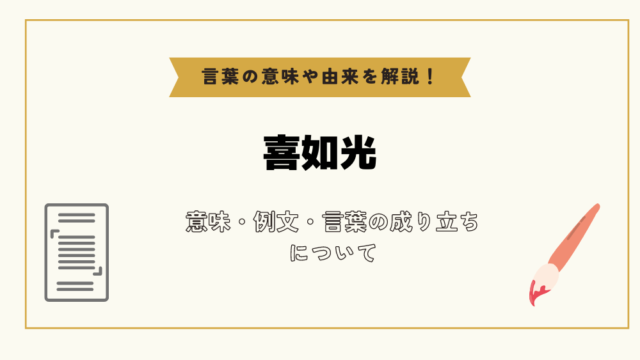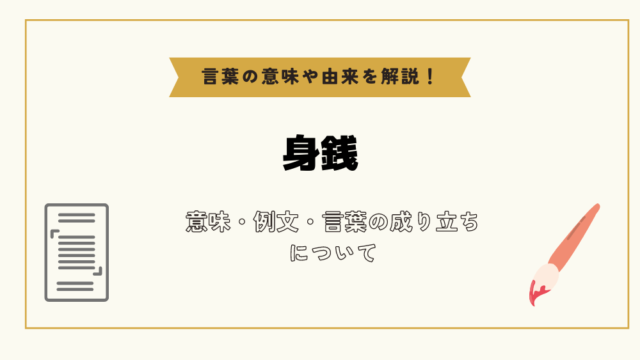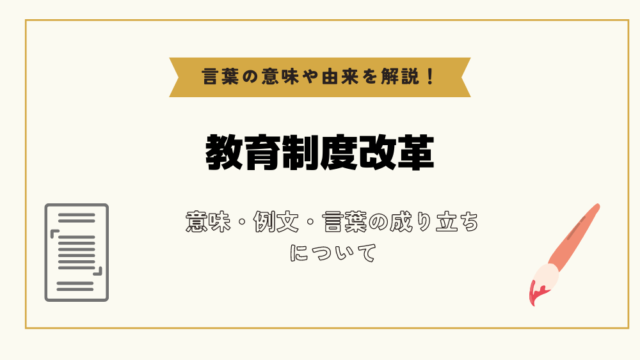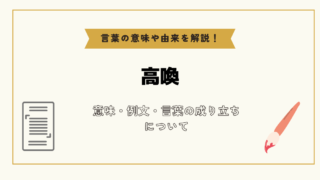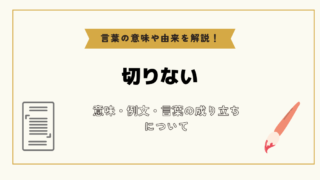Contents
「蟻の一穴」という言葉の意味を解説!
蟻の一穴とは、日本語のことわざであり、集団行動をするときに、一人一人の責任や役割の大切さを表現した言葉です。蟻は一匹一匹が小さく弱いですが、仲間と協力し合って巣を作り、食物を確保することができるのです。
人間の社会でも、一人ひとりが責任を果たすことで、成果を上げることができます。蟻の一穴とは、単純な言葉ですが、その意味は非常に重要であり、人々に協力や責任の重要性を思い起こさせるのです。
「蟻の一穴」という言葉の読み方はなんと読む?
「蟻の一穴」という言葉は、読み方は「ありのいっけつ」となります。日本語のことわざや慣用句は、特定の読み方がある場合があり、この言葉も同じです。
「ありのいっけつ」という読み方で唱えることで、この言葉の意味を伝えることができます。日本語の豊かさを感じることができる言葉ですね。
「蟻の一穴」という言葉の使い方や例文を解説!
「蟻の一穴」という言葉は、主に集団行動や協力の必要性を強調するときに用いられます。例えば、会社のプロジェクトでチーム内のメンバーが全員が協力しないと成功できない場合、上司が「蟻の一穴だから、みんなで力を合わせましょう」と言うことがあります。
また、家族や友人の関係でも、お互いに協力し合わなければ解決できない問題があるときに使うこともあります。一人ひとりが重要な役割を果たすことで、全体の目標達成につながることを表現しています。
「蟻の一穴」という言葉の成り立ちや由来について解説
「蟻の一穴」という言葉は、古くから伝わる日本のことわざですが、具体的な由来や成り立ちについては詳しくはわかっていません。
蟻が協力して巣を作り、食物を確保する姿を観察してきた人々が、その様子から学んだ教訓を込めて言われるようになったと思われます。人間の集団行動においても、協力と責任の重要性を伝えるために使われることがよくある言葉です。
「蟻の一穴」という言葉の歴史
「蟻の一穴」という言葉の歴史については正確な記録はありませんが、古くから使用されていることが伺えます。
日本のことわざは、古代から口伝や文献によって伝承されてきました。また、蟻の姿や行動は日本人にとって身近であるため、このことわざも日本独特の言葉として受け継がれてきたのでしょう。
「蟻の一穴」という言葉についてまとめ
「蟻の一穴」という言葉は、一人ひとりの責任や役割の大切さを強調する言葉です。集団行動において、一人ひとりが協力し合うことで目標を達成することができます。
この言葉は、日本語のことわざの中でもよく知られているものであり、その重要性や教訓を人々に伝えるために使われています。協力や責任の重要性を思い出させ、より良い社会を築くためにこの言葉を活用しましょう。