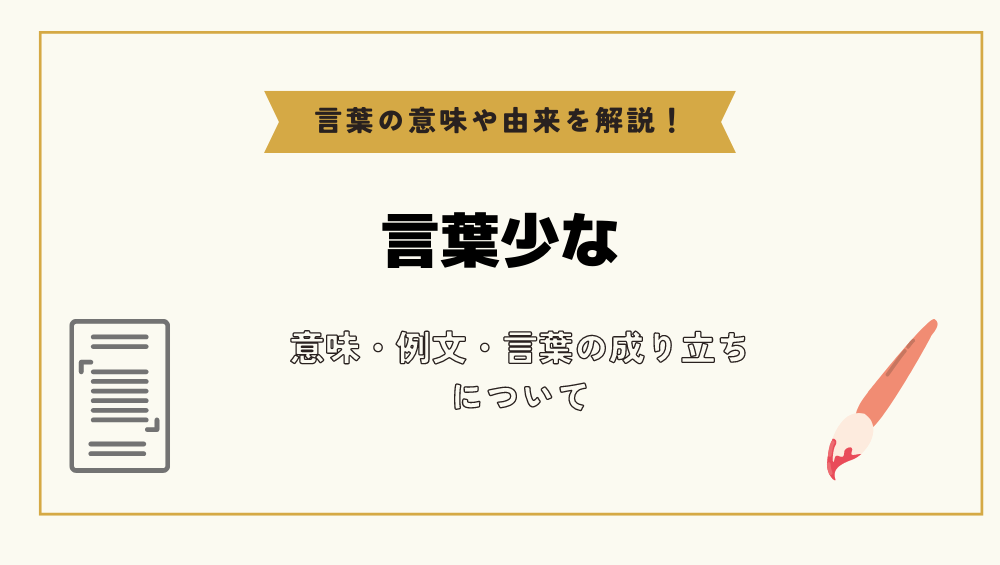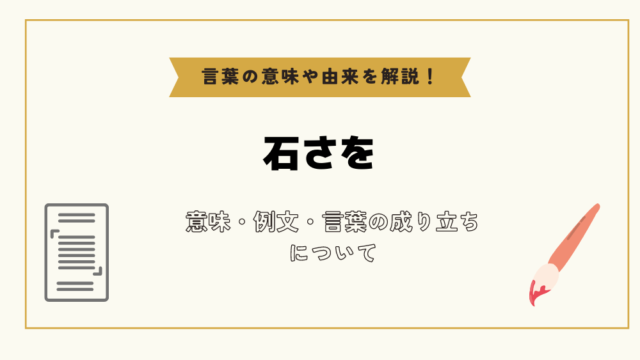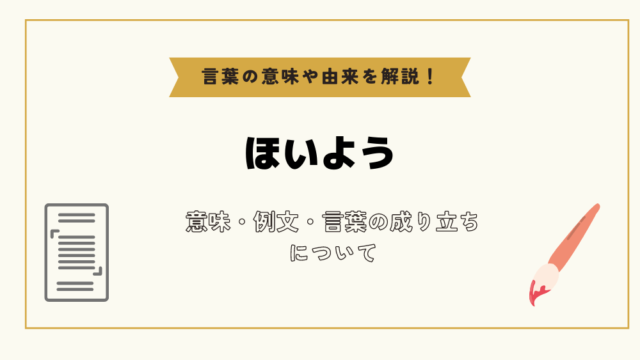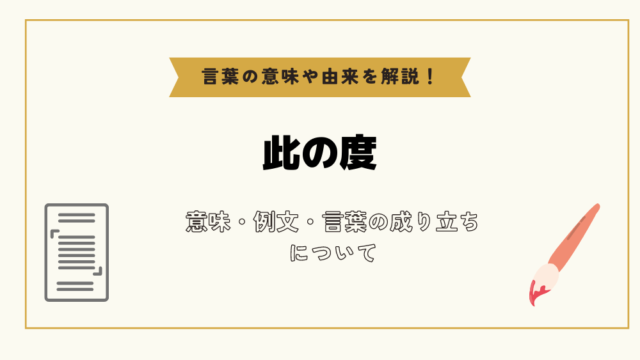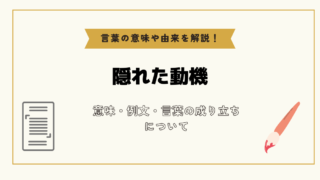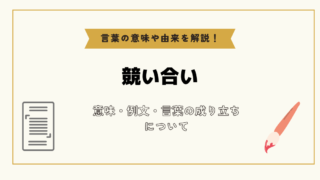Contents
「言葉少な」という言葉の意味を解説!
「言葉少な」という言葉は、物事を簡潔に表現することを指す言葉です。
つまり、少ない言葉で的確に伝えることを意味しています。
この言葉は、情報を短くまとめたい時や効果的に意見を伝えたい時に使われることが多いですね。
「言葉少な」の読み方はなんと読む?
「言葉少な」という言葉は、「ことばすくな」と読みます。
日本語の読み方としては、はっきりとした発音で、間違いなく「ことばすくな」となります。
「言葉少な」という言葉の使い方や例文を解説!
「言葉少な」という言葉は、文章や発言で使用されることが一般的です。
例えば、短いスピーチやプレゼンテーションでは、時間の制約や聴衆の集中力を保つために「言葉少な」の原則が重要です。
また、メールやSNSのメッセージでも、相手に分かりやすく伝えるために簡潔な表現を心がけることが大切です。
「言葉少な」という言葉の成り立ちや由来について解説
「言葉少な」という言葉は、古代日本語の表現方法の一つから派生しています。
古代の文学作品では、限られた文字数で物語を伝える必要があったため、短い言葉で要点をまとめる技術が生まれました。
これが後の「言葉少な」という表現に繋がっています。
「言葉少な」という言葉の歴史
「言葉少な」という言葉の歴史は古く、日本の古典文学にもその痕跡が見られます。
特に平安時代の歌物語や説話集では、一句や一節で深い意味を表現する技術が発展し、後の文学作品にも影響を与えました。
その後、現代の言葉の表現においても、「言葉少な」の原則は重要なテクニックとして受け継がれています。
「言葉少な」という言葉についてまとめ
今回は、「言葉少な」という言葉について解説しました。
簡潔な表現や、物事を効果的に伝えるための方法として、この言葉は非常に重要です。
日本の古典文学から派生し、現代のコミュニケーションにも影響を与えている「言葉少な」の原則を活用して、より効果的な伝達手段を身につけましょう。