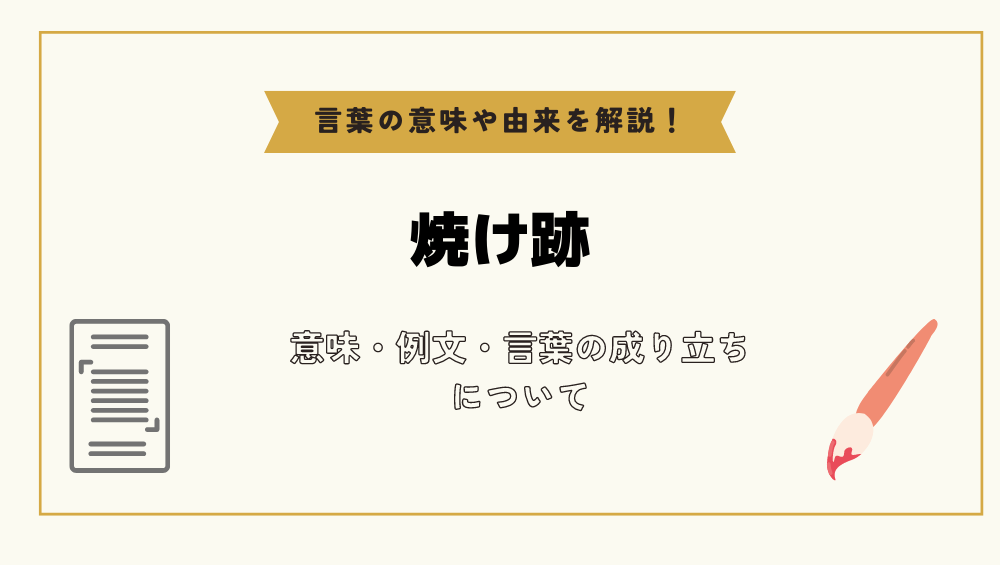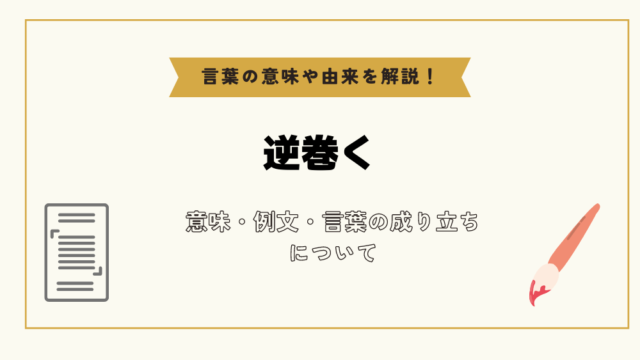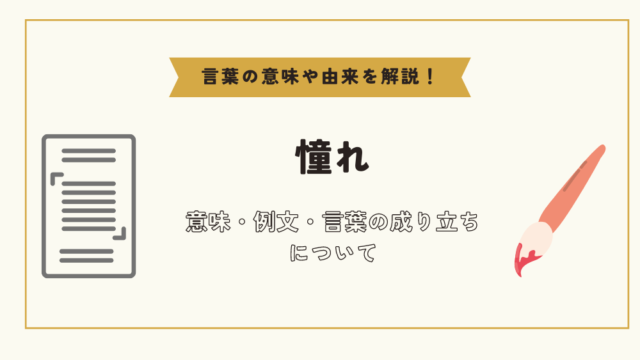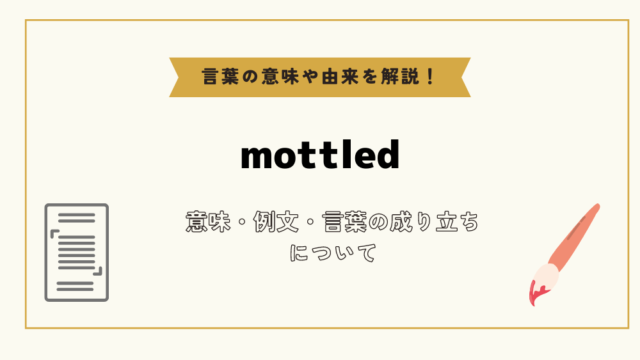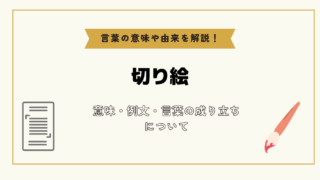Contents
「焼け跡」という言葉の意味を解説!
「焼け跡」という言葉は、火災の跡地や火事で焼けてしまった場所を指す言葉です。
建物や森林など何かが燃えてしまった後の光景を示す言葉として使われます。
火事や火災によって発生した炎の威力により、元々あったものが焼けてしまった後の状態を表現するために使用されます。
「焼け跡」の読み方はなんと読む?
「焼け跡」は、日本語の発音で「やけあと」と読みます。
四文字熟語として使われることもあり、その場合も同じように「やけあと」と読みます。
「焼け跡」という言葉は、一度見たら忘れられない、独特の響きがありますよね。
読み方もその特徴を表現していると言えます。
「焼け跡」という言葉の使い方や例文を解説!
「焼け跡」という言葉は、火事や火災によって発生した跡地を指すため、日常会話ではそれに関連した文脈で使用されます。
例えば、「昨日のニュースで、大火事が起きた地域の焼け跡を見た。
あの光景は本当に悲しかった。
」という風に使うことができます。
「焼け跡」という言葉の成り立ちや由来について解説
「焼け跡」という言葉の成り立ちは、「焼く(燃やす)」という意味の「焼け」に、「跡」という意味を持つ字を当てたものです。
火災によってできる跡地を指す言葉として使われてきました。
日本人が火事や火災によって急激に失われたものの悲しみを表現するために生まれた言葉と言えるでしょう。
「焼け跡」という言葉の歴史
「焼け跡」という言葉は、日本の歴史において古くから使われてきました。
江戸時代から明治時代にかけては、火事が頻繁に発生し、町や村が焼け跡と化す光景を何度も目にしてきました。
時代が変わっても、火事という自然災害は消えることなく続いてきました。
私たちが今も「焼け跡」という言葉を使うのは、その歴史的な背景があるからです。
「焼け跡」という言葉についてまとめ
「焼け跡」という言葉は、火災によって燃え尽くされた後の跡地を指す言葉です。
その響きや使われ方から、悲しみや喪失感を表現する場面でよく用いられます。
日本の歴史の中で数多くの火災が起き、建物や町が焼け跡となったことから、私たちの心の中に深く刻まれた言葉でもあります。