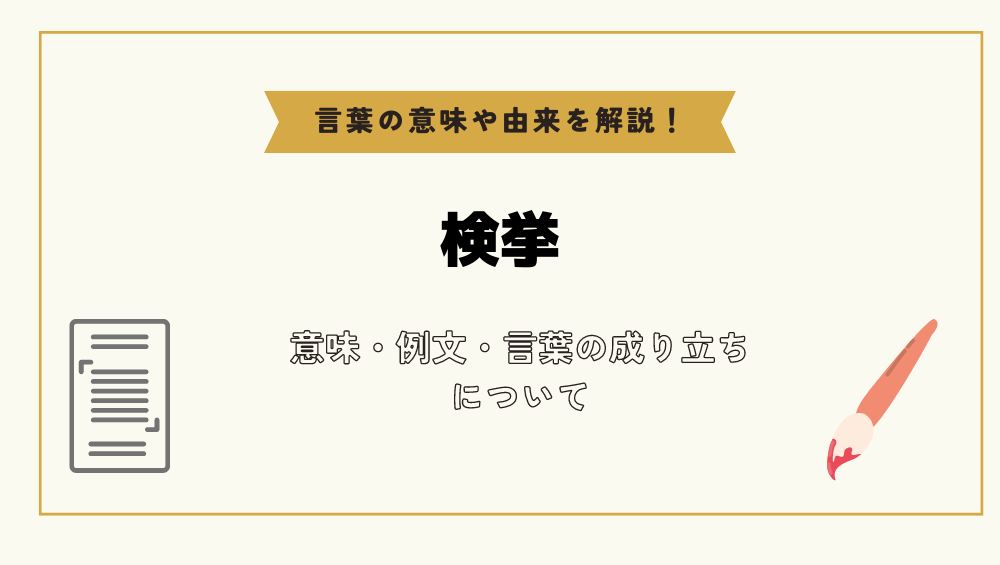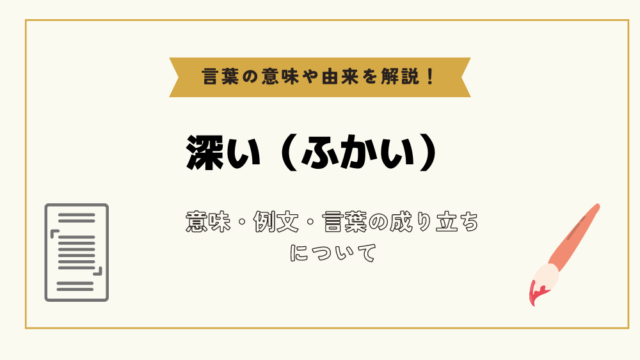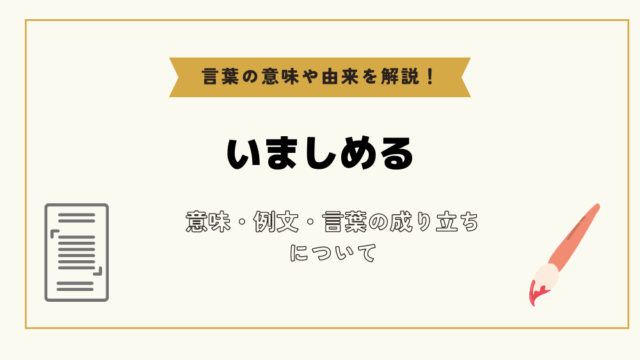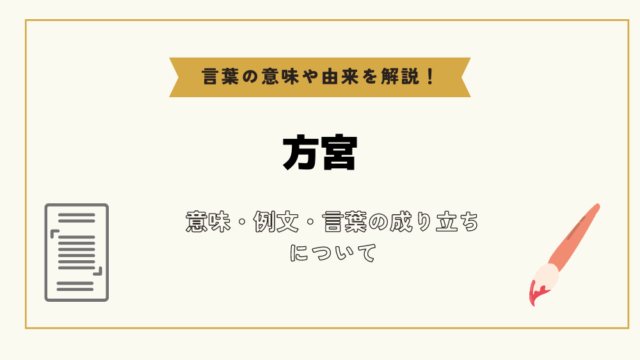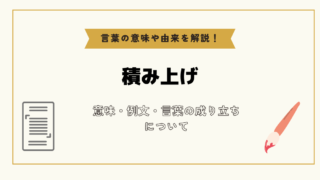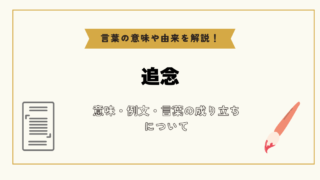Contents
「検挙」という言葉の意味を解説!
検挙とは、犯罪や違法行為を行った者を警察や捜査機関が逮捕・発見することを指す言葉です。
犯罪者や違法行為者を摘発する手段の一つであり、社会の安全と秩序を守るために重要な役割を果たしています。
検挙は、警察や捜査機関が情報の収集や証拠の確保を行い、犯罪者や違法行為者を特定する過程が含まれます。そして、犯罪の証拠が押さえられ、容疑者が逮捕されたり、違法行為が摘発されることで、検挙が成立します。
例えば、麻薬取引や窃盗などの犯罪行為が行われている場合、警察は捜査を行い、犯罪者を特定することを目指します。そして、犯罪行為が明らかになった時点で容疑者が検挙されるのです。
検挙は、犯罪者や違法行為者を罰するだけでなく、社会の安全と秩序を守るためにも重要な役割を果たしています。警察や捜査機関の努力によって、犯罪が減少し、安全な社会が築かれることを期待しましょう。
「検挙」という言葉の読み方はなんと読む?
「検挙」という言葉は、「けんきょ」と読まれます。
この読み方は、一般的な日本語のルールに従っています。
漢字の「検」は「けん」と読み、「挙」は「きょ」と読みます。
「けんきょ」という言葉は、警察や捜査機関の活動を指す重要な言葉であり、犯罪や違法行為の摘発を行う際に頻繁に使われます。覚えておくと、ニュースなどでこの言葉を聞いた際にスムーズに理解できるでしょう。
「検挙」という言葉の使い方や例文を解説!
「検挙」という言葉は、犯罪の捜査や違法行為の摘発を示す際に使われます。
警察や捜査機関が犯罪者や違法行為者を特定し、逮捕・発見する行為を指すのです。
例えば、以下のような使い方があります。
– 警察は麻薬取引の現場に乗り込み、犯罪者を検挙した。
– 捜査の結果、窃盗グループのメンバーが検挙された。
このように「検挙」は、犯罪や違法行為に関連する多くの文脈で使われる言葉です。警察の活動や犯罪の摘発に興味がある方にとっては、覚えておくべき重要な言葉と言えるでしょう。
「検挙」という言葉の成り立ちや由来について解説
「検挙」という言葉の成り立ちは、漢字の組み合わせによってできています。
漢字の「検」と「挙」を合わせることで、「検挙」という言葉が成立しています。
「検」という漢字は、「調べる」という意味を持ち、「挙」という漢字は、「あげる」という意味を持ちます。そのため、「検挙」とは、警察や捜査機関が犯罪者や違法行為者を「調べ上げる」という意味を持つ言葉となります。
この言葉の由来は、日本の法律や社会制度の発展とともに広まってきたものと考えられます。犯罪や違法行為を摘発することは、法治社会の構築や秩序維持に欠かせない重要な要素であり、そのために「検挙」という言葉が生まれたと言えるでしょう。
「検挙」という言葉の歴史
「検挙」という言葉の歴史は古く、日本の法律制度が整備される以前から存在していました。
古代から中世にかけては、地域の支配者や武士団体が犯罪者を持ち帰り、裁判を行っていました。
近代に入り、明治時代からは西洋の法制度が導入されるとともに、警察機関の発展が進みました。犯罪の検挙は、警察の重要な業務の一つとなりました。現代でも警察や捜査機関が犯罪者を検挙する役割を果たしています。
時代が変わっても検挙の重要性は変わらず、社会の安全を守るために様々な取り組みが行われています。科学技術の発展などの影響もあり、検挙の手段や技術も進化しているのです。
「検挙」という言葉についてまとめ
「検挙」という言葉は、犯罪や違法行為を行った者を警察や捜査機関が逮捕・発見することを指す重要な言葉です。
警察の活動や社会の安全を守るために不可欠な役割を果たしています。
「検挙」という言葉の読み方は「けんきょ」と読まれ、日本語のルールに従っています。犯罪者や違法行為者を摘発する際に使われる一般的な言葉です。
正しい使い方や文脈による例文、そして成り立ちや歴史についても解説しました。検挙の意味や背景を理解することで、警察の活動や犯罪摘発の重要性について深く考えることができます。