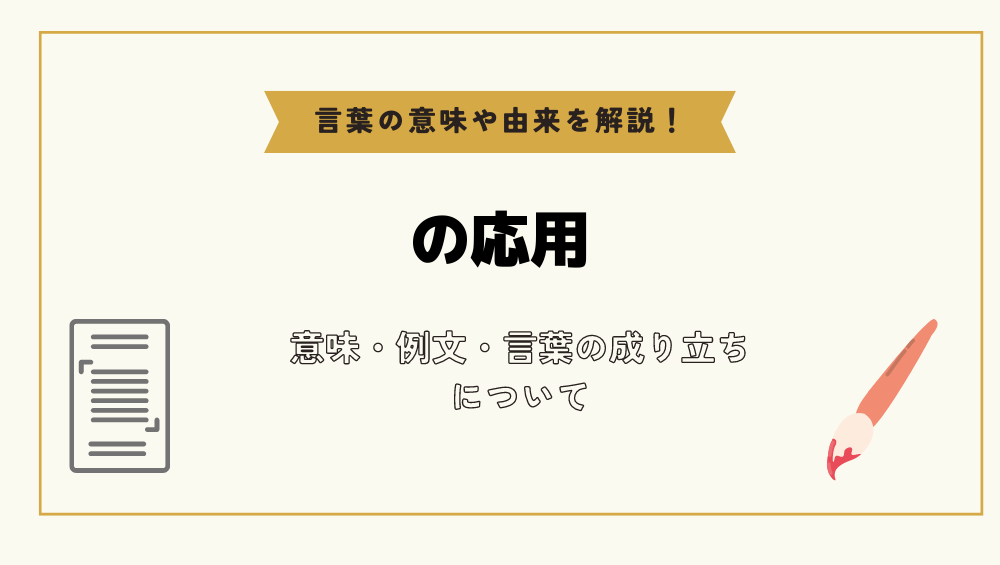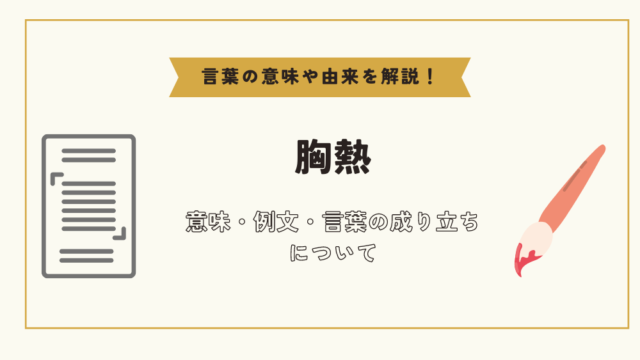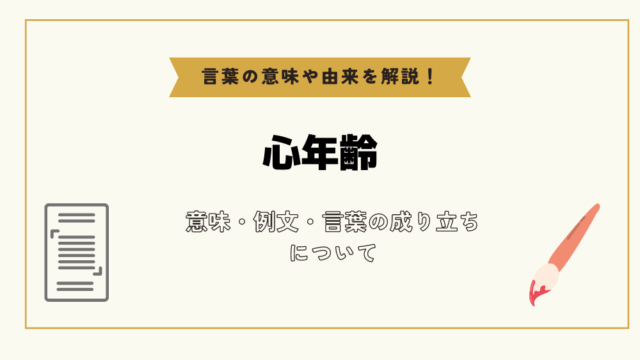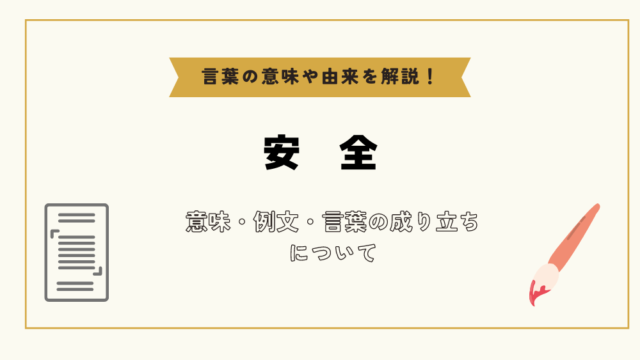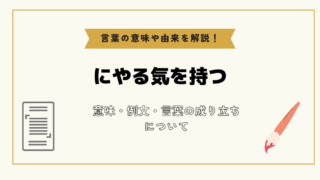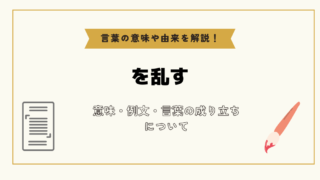Contents
「の応用」という言葉の意味を解説!
「の応用」という言葉は、ある基本的な概念や技術を応用して新たな分野や問題に取り組むことを指します。
つまり、既存の知識やスキルを応用して、新しいアイディアや解決策を生み出すことなのです。
「の応用」は、幅広い分野で使用される言葉であり、科学、技術、ビジネス、教育など、様々な場面で活躍しています。
「の応用」の読み方はなんと読む?
「の応用」は、読み方としては「のおうよう」となります。
日本語には様々な言葉の読み方がありますが、この場合は「おうよう」という読み方が一般的です。
もちろん、地域や方言によって微妙な違いがあるかもしれませんが、基本的には「のおうよう」と発音します。
「の応用」という言葉の使い方や例文を解説!
「の応用」という言葉は、さまざまな文脈で使われます。
例えば、学校の授業で学んだ基礎知識を「の応用」として応用問題に取り組む、あるいは仕事で得た経験やスキルを他の分野に「の応用」するなどです。
つまり、「の応用」は既存の知識やスキルを新しい状況や問題に適用することを意味します。
「の応用」という言葉の成り立ちや由来について解説
「の応用」という言葉の成り立ちは、日本語の一般的な文法に由来しています。
日本語では、AのBという形で、ある事柄(A)が別の事柄(B)に関連していることを表現します。
例えば、「数学の応用」という場合、数学という基礎的な事柄が応用という別の事柄に関連していることを示しています。
「の応用」という言葉の歴史
「の応用」という言葉の歴史は、日本語の発展とともに長い歴史を持っています。
古くは、和歌や漢詩などの古典文学で「の応用」の表現が用いられていました。
しかし、近代以降の日本では、理科や工学、技術分野などで「の応用」という言葉がさらに広く使われるようになりました。
現在では、ビジネスや教育など様々な分野で見られるようになっています。
「の応用」という言葉についてまとめ
「の応用」という言葉は、ある基本的な概念や技術を応用して新たな分野や問題に取り組むことを指します。
その読み方は「のおうよう」となります。
例文を通じて使い方を理解し、成り立ちや歴史を知ることで「の応用」という言葉の意味を深く理解することができるでしょう。
さまざまな場面で「の応用」を活かし、新しいアイディアや解決策を生み出すことを目指しましょう。