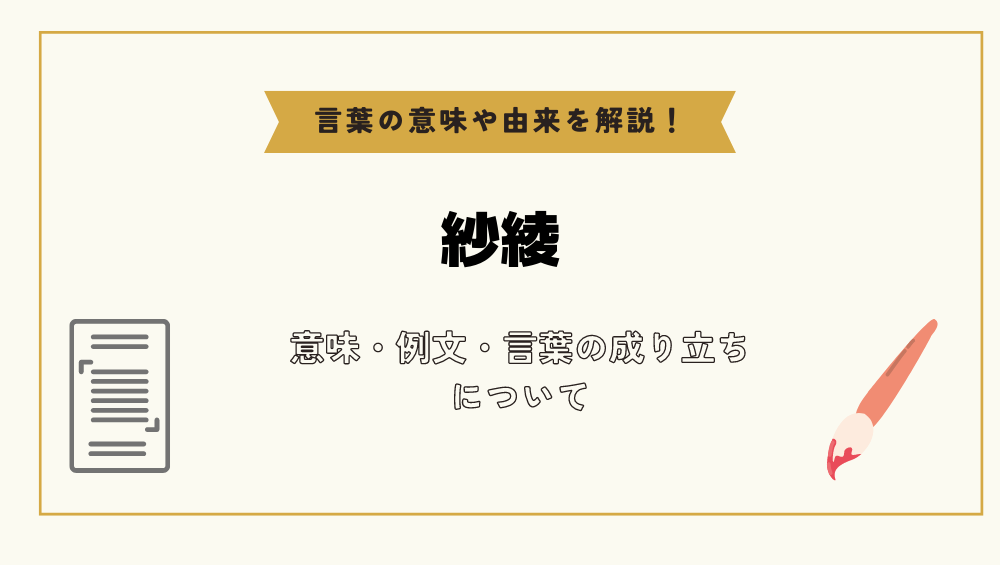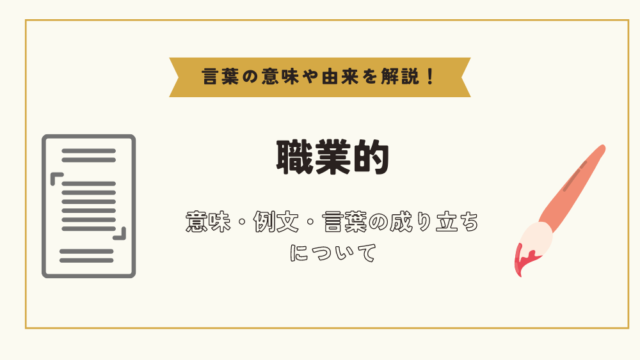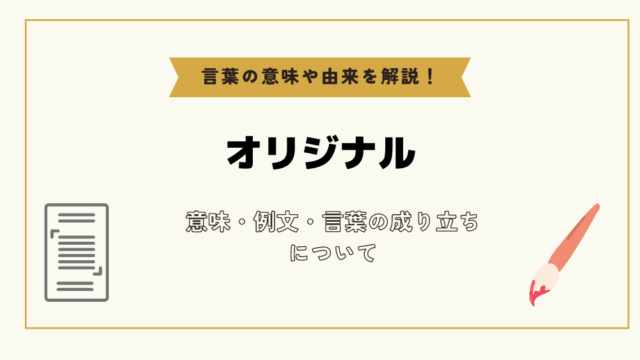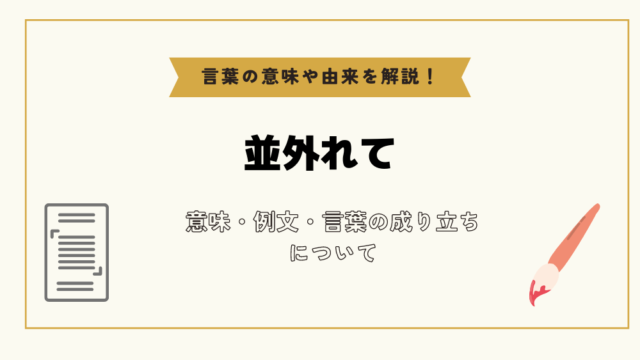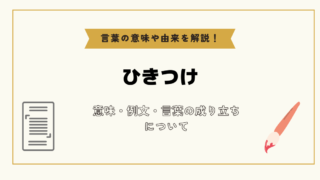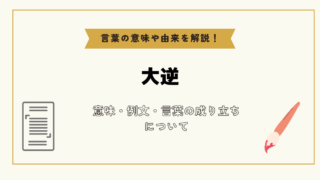Contents
「紗綾」という言葉の意味を解説!
紗綾(しゃあ)とは、織物の一種で、糸を交互に縦と横に交差させて織り上げた美しい模様のことを指します。
この模様は、細かくて緻密なのが特徴であり、独特の光沢感があります。
紗綾は帯や着物などの和服に使われることが多いですが、最近では洋服や小物にも取り入れられています。
この織り方は、日本の伝統工芸技術の一つであり、丁寧な手仕事が求められるため、高い技術力が必要です。
「紗綾」という言葉の読み方はなんと読む?
「紗綾」という言葉は、「しゃあ」と読みます。
カタカナ表記であるため、外国の方でも読みやすいです。
日本語の中でも、独特の響きを持つ言葉です。
「紗綾」という言葉の使い方や例文を解説!
「紗綾」という言葉は、主に和の世界で使用されます。
例えば、和傘を表現する際に「紗綾の傘」と言うことがあります。
また、振袖や袴などの着物を説明する際にも、「紗綾の柄が美しい」と表現することがあります。
さらに、糸の紡ぎ方や織り方を指して「この生地は紗綾織りです」と言うこともあります。
紗綾の美しさや独特な光沢感が評価されて、特別な場にふさわしいとされています。
「紗綾」という言葉の成り立ちや由来について解説
「紗綾」という言葉は、紗(しゃ)と綾(あや)という2つの単語が組み合わさってできました。
紗は、糸を細かく撚った織物を指し、綾は織物の一種です。
紗綾という言葉が生まれた背景には、古代中国の文化があります。
中国ではすでに古くから織物の技術が発達していて、その技術が日本に伝わったことにより、現在の紗綾が存在するのです。
「紗綾」という言葉の歴史
紗綾は、日本には奈良時代の頃から存在していたとされています。
当初は高貴な身分の人々が身に着けることができる贅沢品でしたが、次第に一般の人々にも広まっていきました。
江戸時代には、紗綾の需要が高まり、町人文化の中でも愛される存在となりました。
現在でも、お祭りや結婚式などの特別な行事で紗綾を身に着けることが多く、その歴史と伝統は今もなお続いています。
「紗綾」という言葉についてまとめ
紗綾は、繊細で美しい織物の一種です。
日本の伝統文化や技術の象徴として、長い歴史を持っています。
紗綾は、和服や小物に使われることが多く、その美しさは非常に高く評価されています。
日本の特別な行事やお祭りなどで紗綾を身に着けることが多いため、その存在感は大きいです。
ぜひ一度、紗綾の繊細な模様や光沢感を体感してみてください。