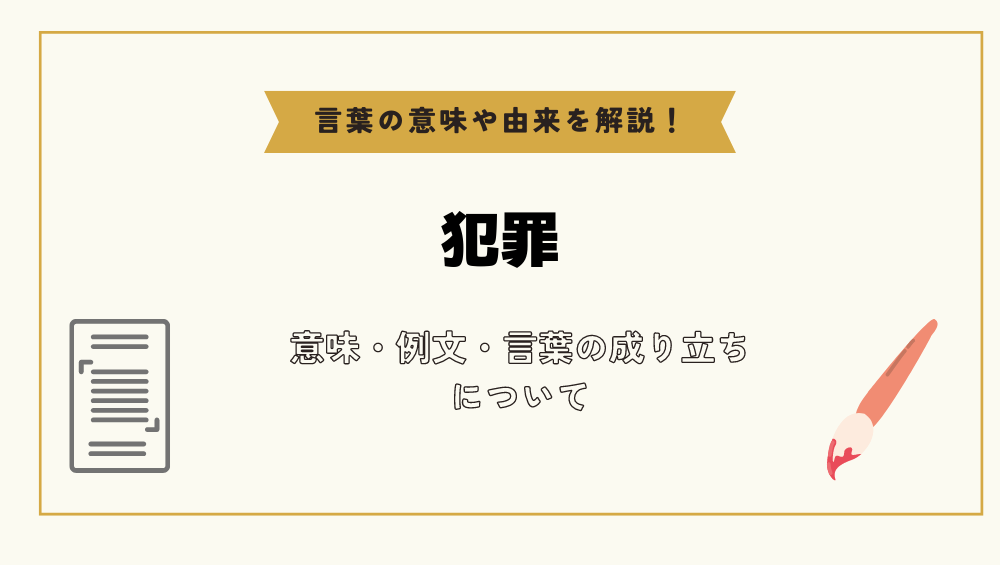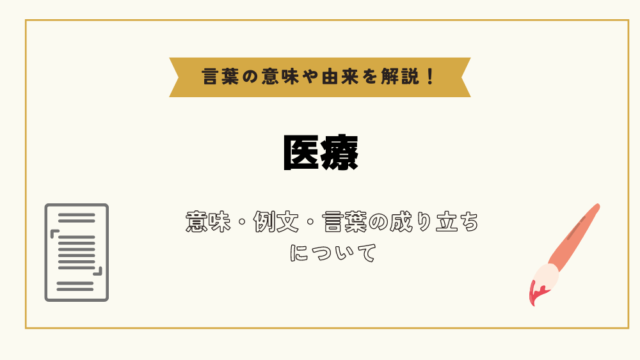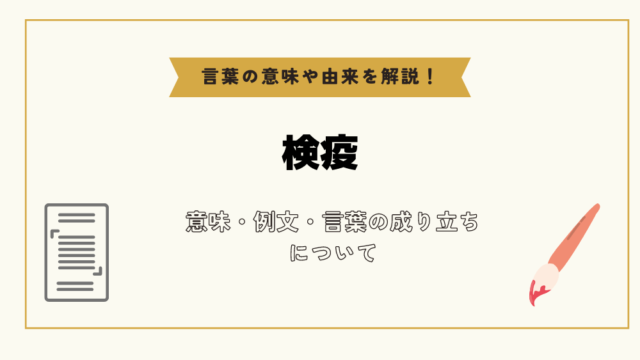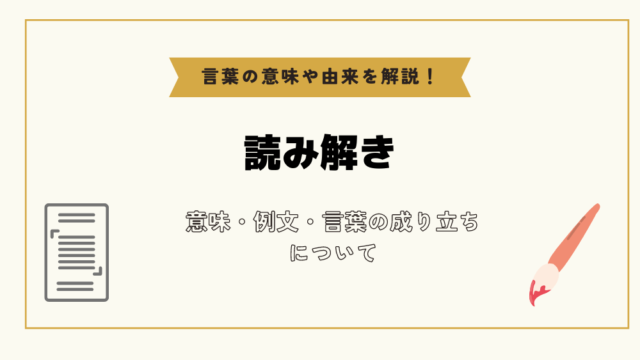「犯罪」という言葉の意味を解説!
「犯罪」とは、国家が定めた刑罰法規に違反する行為を指し、違反行為に対して刑事上の制裁が科されるものを総称します。
法律学では、犯罪を「構成要件該当性・違法性・有責性」を備えた行為と整理します。構成要件とは条文に記載された行為類型に該当するかどうかを指し、違法性は社会的相当性を逸脱しているか、有責性は責任能力や故意・過失の有無です。
日常会話では「法に触れる悪い行為」程度の意味で使われることも多いですが、専門的には刑事罰が予定されている点が欠かせません。行政上の罰則(過料など)があるだけでは「犯罪」とは呼ばない点に注意しましょう。
「刑罰」は自由刑(懲役・禁錮など)や罰金刑、死刑など多岐にわたり、犯罪と一体で論じられます。刑法だけでなく特別法(覚醒剤取締法など)にも犯罪類型が細かく規定されています。
犯罪は社会秩序を維持する最後の歯止めとして位置づけられており、その定義は厳格で限定的です。
国や時代により「犯罪」とされる行為は移り変わります。かつては同性愛や賭博が重罪に分類された社会もあり、文化・価値観の影響を強く受ける言葉と言えるでしょう。
「犯罪」の読み方はなんと読む?
「犯罪」は一般に「はんざい」と読みます。
漢字の構成は「犯(おかす)」と「罪(つみ)」で、どちらも音読みを用いた熟語です。「はんさい」と読まれることはありませんので注意しましょう。国語辞典でも見出し語は「はんざい」一本で、送り仮名は不要です。
「犯」を訓読みして「つみをおかす」と表現される場合でも、熟語としての読みは変わりません。ニュース原稿や公文書では平仮名交じりで「はん罪」と表記することも稀にありますが、一般的ではありません。
音読み熟語のためアクセントは「ン」にかかり、やや後方高めの発音になります。朗読やスピーチで強調したい場合は、後の「ざい」をやや引き伸ばすと聞き取りやすくなります。
読み方が一義的である点は、公的文書や法律条文の正確性を支える重要な要素です。
「犯罪」という言葉の使い方や例文を解説!
法律実務では「犯罪が成立する」「犯罪の成否を検討する」といった形で用いられます。日常会話では「それって犯罪じゃないの?」と軽い確認で使われる場合もありますが、法的責任の有無は専門知識が不可欠です。
【例文1】未成年でも重大な犯罪を犯せば刑事責任を問われる場合があります。
【例文2】SNSでの誹謗中傷は場合によっては犯罪に発展します。
例文のように、単純な違法行為から重大事件まで幅広く修飾語として使える点が「犯罪」の特徴です。
ビジネス文脈では「企業犯罪」「経済犯罪」などの複合語が頻出します。これらは横領や粉飾決算など経済活動に関連する違法行為を示し、行政処分だけでなく刑事罰が想定されていることを示唆します。
メディアでは「凶悪犯罪」「少年犯罪」など、犯行の性質や主体を示す語を前置して用い、社会問題としての重みを強調します。報道基準では容疑者段階で「犯罪」と断定しないよう配慮が求められる点も覚えておきましょう。
「犯罪」という言葉の成り立ちや由来について解説
「犯」は「侵す・破る」を意味し、古代中国の律令制度でも違反行為を示す文字として用いられました。「罪」は「罰せられるべき過ち」を指し、礼・法のいずれに反しても罪として扱った歴史があります。
日本では奈良時代に唐の律令を輸入した際、「犯罪」という熟語が法令用語として登場しました。当時の写経や令集解にも見られ、読みは漢音で固定されました。
語源的に「法を犯し、罰を受けるべき事柄」を一語で示す効率性が評価され、千年以上にわたり用いられてきたのです。
仏教経典では「罪」を輪廻の原因と語るなど宗教的ニュアンスも加わりましたが、国家統治の観点からは「犯罪」が世俗法違反を表す語として独立しました。江戸期の武家法度にも類似表現が使われ、明治期に西洋法を取り入れる際も「crime」の訳語としてそのまま継承されています。
今日の刑法典でも「犯罪ノ成立」など明治語法を踏襲した条文が残っており、古語の名残を感じさせる語と言えるでしょう。
「犯罪」という言葉の歴史
古代律令国家では「五刑」(笞・杖・徒・流・死)を科す行為を「犯罪」と総称しました。身分制と結び付いており、貴族には軽い刑が適用されるなど不平等も顕著でした。
江戸時代には武家社会の法度や町触れで「犯罪」という語が散見されますが、実務的には「科罪」「重科」といった言い回しも併存しました。奉行所の記録にも「犯罪人」という表記が見られ、現代に通じる用法が定着していきます。
明治維新後、フランス刑法を手本にした旧刑法が制定され、「犯罪」という言葉は近代国家の法体系の基礎用語として公式に採用されました。
戦後は日本国憲法の刑事手続保障のもと、犯罪概念も人権尊重の視点から再構築されました。現行刑法は1907(明治40)年制定ですが、その後の改正で時代状況に合わせた犯罪類型の新設(組織的犯罪処罰法など)が進んでいます。
情報化社会の到来に合わせ、ハッキングやサイバー攻撃など新たな犯罪類型も誕生しました。歴史を通じて、犯罪概念は社会構造の変化を映し出す鏡でもあるのです。
「犯罪」の類語・同義語・言い換え表現
日常語としては「違法行為」「不法行為」「悪事」が近い意味を持ちますが、刑事罰を前提としているかどうかで厳密性が異なります。民事上の「不法行為」は損害賠償を生じさせる点で共通しますが、刑事罰は伴いません。
法律用語では「故意犯」「過失犯」「未遂犯」など、犯罪類型を細分化した表現が活用されます。経済分野では「ホワイトカラー犯罪」、IT分野では「サイバー犯罪」という言い換えが増えています。
いずれの類語も、刑法上の犯罪との関係を意識して使い分けることで、文章の精度が向上します。
学術的にはラテン語起源の「デリクト」(delict)を引用する文献もありますが、日本語としては専門家の間でも限定的な使用にとどまります。翻訳の際は注釈を加えると親切です。
同義語を選ぶときは、刑事罰の有無・故意の要否・社会的評価などニュアンスの違いに注意しましょう。これにより読者に正確な情報を届けることができます。
「犯罪」の対義語・反対語
法律分野で厳密に対置される語は「適法行為」です。刑罰法規に違反しない行為を指し、社会的相当性を満たす点が特徴です。裁判所は行為が「犯罪」か「適法」かを峻別し、結論を導きます。
一般用語としては「遵法」「善行」「合法」なども反対のイメージを持つ語として挙げられます。しかし「合法」は単に法に適合しているだけで、積極的な社会的価値を含むわけではありません。
「犯罪」を論じる際は、対義語とセットで考えることで、法秩序の輪郭がより鮮明になります。
倫理学では「徳行」「道徳的行為」が反対概念として参照されることがあります。ただし道徳と法律は一致しない場合もあるため、文脈ごとに注意が必要です。
「犯罪」についてよくある誤解と正しい理解
「誰も見ていなければ犯罪にならない」という誤解が根強くあります。しかし刑法は行為が成立した時点で犯罪として扱い、発覚の有無は量刑や処分に影響を与えるに過ぎません。
【例文1】盗撮は発覚しなくても犯罪である。
【例文2】未遂でも犯罪が成立する場合がある。
発覚の有無や結果の大小ではなく、法規範に違反した時点で犯罪が成立するという事実を押さえましょう。
もう一つの誤解は「被害者が許せば犯罪ではない」というものです。親告罪では告訴が要件となりますが、非親告罪では被害者の意思に関係なく公訴が提起されます。例えば強盗罪は非親告罪で、示談が成立しても犯行自体が消えるわけではありません。
また「少年が犯した行為は犯罪ではなく非行だ」と考えられがちですが、家庭裁判所の審判を経て「刑事処分相当」と判断されれば、成人と同様に刑事裁判に付される可能性があります。用語としての「少年犯罪」も法令上明確に存在します。
メディア報道では「容疑者」と呼称する段階で「犯罪者」と断定しない配慮を行いますが、これは推定無罪の原則を尊重するためです。したがって「犯罪者」と「被疑者」を混同しないよう注意しましょう。
「犯罪」という言葉についてまとめ
- 「犯罪」とは刑罰法規に違反する行為全般を指す法律用語。
- 読み方は「はんざい」で音読みが一般的。
- 古代中国の律令用語を起源とし、日本では奈良時代から用例がある。
- 現代では法的概念として厳格に使われ、報道では推定無罪への配慮が必要。
「犯罪」は日常語としても頻繁に登場しますが、本質は刑罰を前提とする厳密な法律概念です。読みやすさと正確さを両立させるためには、類語・対義語・歴史的背景を理解し、文脈ごとに適切に使い分けることが欠かせません。
また、犯罪概念は社会の価値観とともに変化します。過去には重罪だった行為が合法化された例もあれば、その逆もあります。歴史に目を向けると、現在の法体系がどのように形づくられてきたかを俯瞰でき、言葉の重みも一層実感できるでしょう。