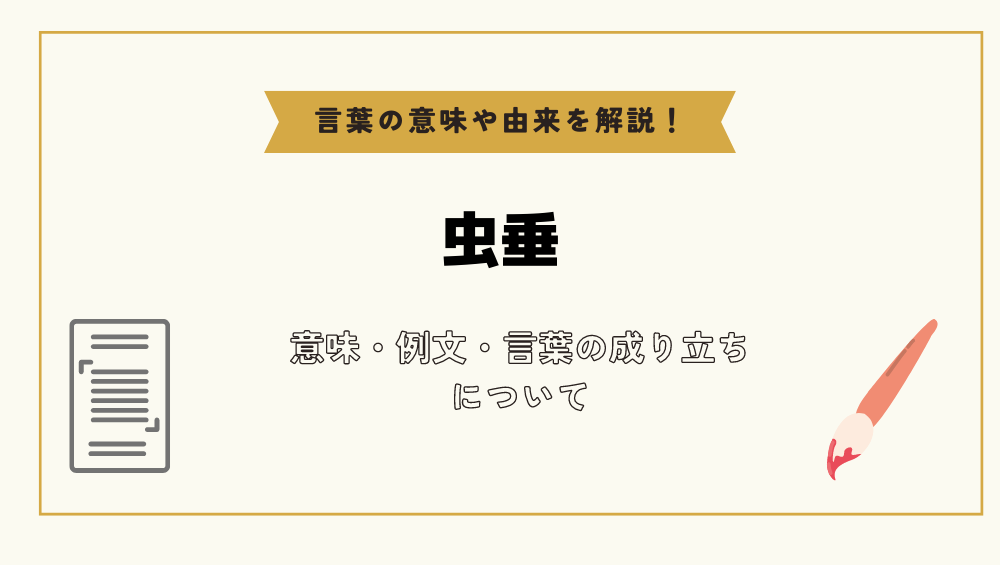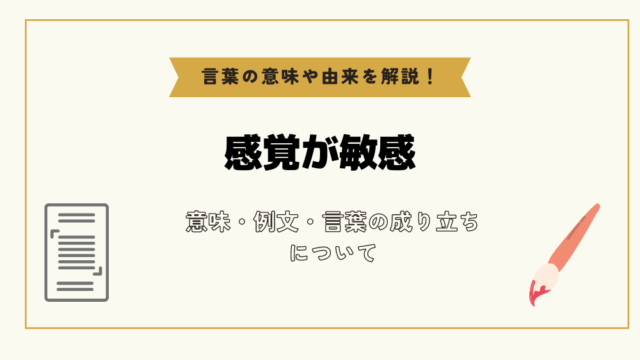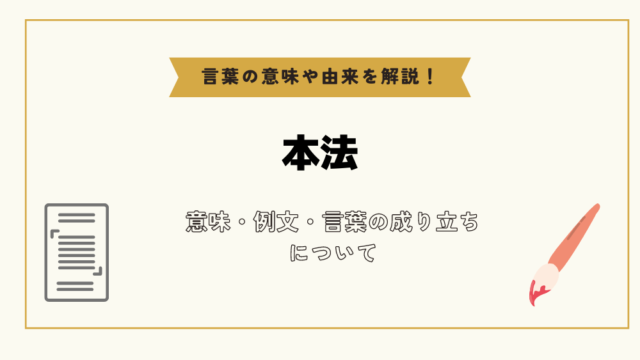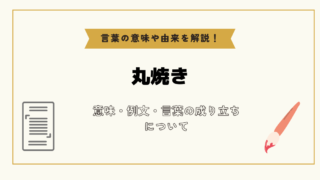Contents
「虫垂」という言葉の意味を解説!
「虫垂」とは、人間の消化器官の一部である盲腸の先にある細長い突起のことを指します。
全長は通常6〜8センチメートルほどで、直径は1センチメートル程度です。
【重要なポイント】虫垂には機能がなく、特に問題がなければ身体に影響を及ぼすことはありません。
しかし、虫垂に炎症が起こると虫垂炎という病気になり、緊急の手術が必要となります。
「虫垂」の読み方はなんと読む?
「虫垂」は、ちゅうすいと読みます。
ちゅうすいは漢字の「蟲垂」と書きますが、一般的には「虫垂」と表記されることが多いです。
【重要なポイント】書くときは正式には「蟲垂」と書くことが望ましいですが、一般的な文章では「虫垂」と書くのが一般的です。
「虫垂」という言葉の使い方や例文を解説!
「虫垂」は、盲腸と一緒に用いられることが多いです。
例えば、「虫垂炎」という病気のほかに、虫垂を摘出する手術を「虫垂切除術」といいます。
【重要なポイント】「虫垂」は医学的な言葉であり、一般的な会話や文章ではあまり使われることはありません。
「虫垂」という言葉の成り立ちや由来について解説
「虫垂」という言葉の成り立ちは、虫のような形状をしていることからきています。
そのままではなく、縮小形の「虫」を表す「虫」と「垂れる」「垂らす」といった動作を表す「垂」が組み合わさった言葉です。
【重要なポイント】虫垂がなぜ「虫」という名前なのかははっきりわかっていませんが、形状に由来していると考えられています。
「虫垂」という言葉の歴史
「虫垂」という言葉の歴史は、古くないと言われています。
盲腸自体の存在は古くから知られており、虫垂の名前も比較的最近につけられたものと考えられています。
【重要なポイント】虫垂炎の手術が一般的になる以前は、虫垂の存在や役割についての知識は乏しかったと言われています。
「虫垂」という言葉についてまとめ
「虫垂」とは盲腸の先にある突起のことを指し、なんらかの問題が起きない限りほとんど意識することなく存在しています。
虫垂炎という炎症を起こすこともあり、その場合は緊急の手術が必要となります。
一般的な文章ではあまり使われない言葉ですが、医学的な文脈ではよく使われます。
【重要なポイント】虫垂は、形状から「虫」と呼ばれるようになったと考えられています。
歴史は古くないものの、虫垂炎の治療方法の発展により、その存在や役割についての知識も広まっています。