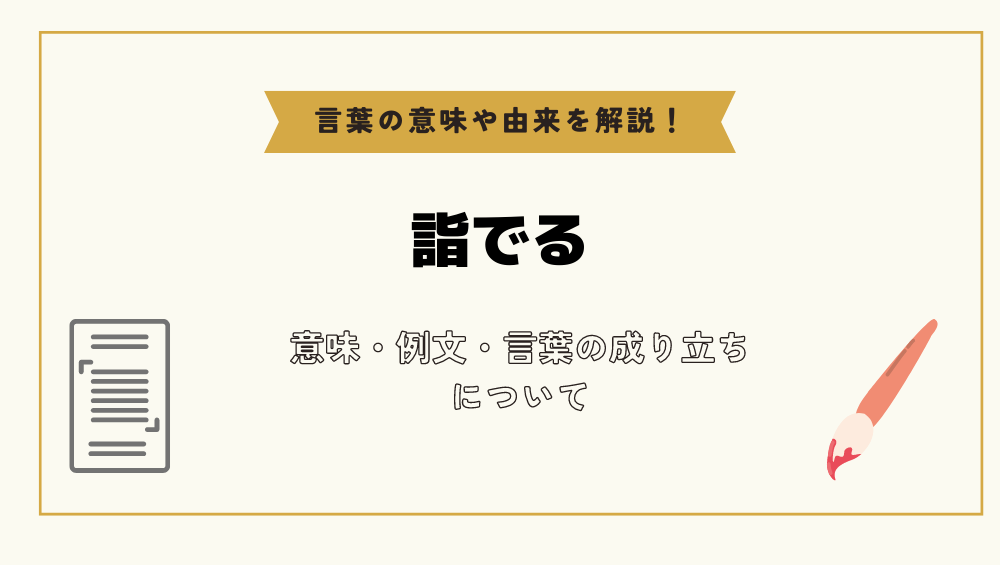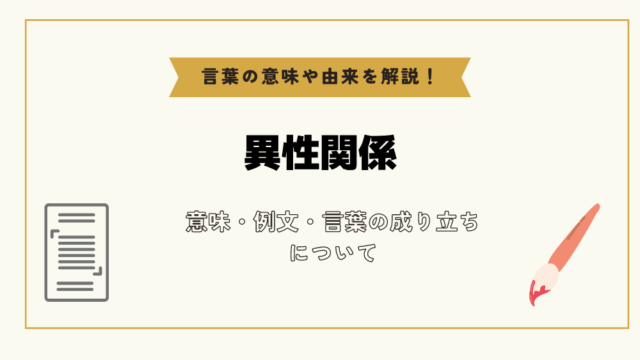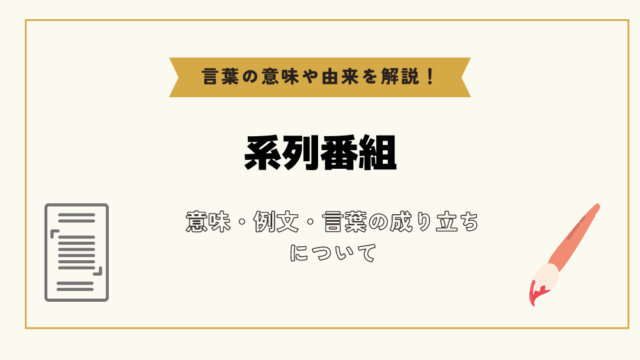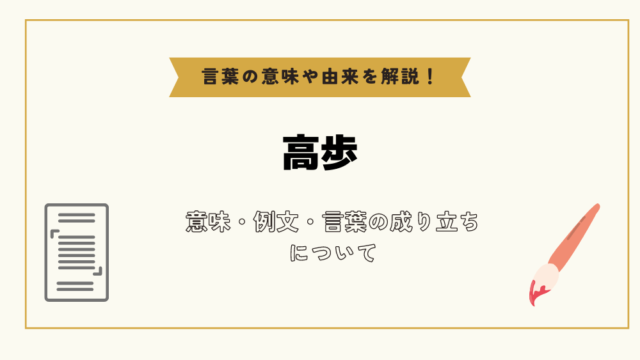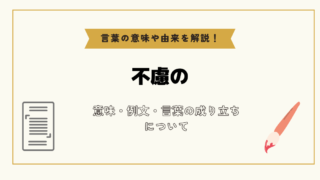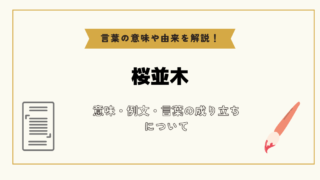Contents
「詣でる」という言葉の意味を解説!
「詣でる」という言葉は、神社や寺院など宗教的な場所へ参拝することを指します。
自分の信仰心を示すために、特定の場所へ出向き、祈りを捧げる行為です。
「詣でる」という言葉は、心を込めてお参りすることを表現しており、尊敬の念や感謝の気持ちを示すとされています。
「詣でる」の読み方はなんと読む?
「詣でる」は、読み方としては「もうでる」となります。
漢字の「詣」という字は、もともとは「もう」の訓読みです。
しかし、一般的には「もうでる」という読み方が広く使われており、意味を正確に伝えるためには「もうでる」と読むのが適切です。
「詣でる」という言葉の使い方や例文を解説!
「詣でる」という言葉は、主に神社や寺院への参拝を表現する際に使用されます。
例えば、「日本には多くの歴史的な神社や寺院がありますので、休日には詣でることをおすすめします。
」と言った表現が一般的です。
また、「詣でる」という言葉は、宗教的な意味合いだけでなく、人々がある場所へ集まり感謝や尊敬の気持ちを示す場合にも使用されることがあります。
「詣でる」という言葉の成り立ちや由来について解説
「詣でる」の成り立ちは、古代中国に由来しています。
中国では、朝廷に謁見することを「詣参」といったそうです。
平安時代に日本に伝えられ、やがて仏教的な参拝の行為にも使われるようになりました。
そして、現代では広く宗教的な行為や尊敬の気持ちを表現するために使用されるようになりました。
「詣でる」という言葉の歴史
「詣でる」という言葉は、日本の歴史と深く結びついています。
古くから神道や仏教など宗教行事の一環として行われてきました。
また、平安時代になると京都や奈良などの歴史的な寺院や神社が栄え、詣でることが一般的な習慣となりました。
現代でも多くの人々が信仰心や感謝の気持ちを込めて詣でる行為を行っています。
「詣でる」という言葉についてまとめ
「詣でる」という言葉は、神社や寺院など宗教的な場所へ参拝し、心を込めたお参りをすることを指します。
その意味合いから、信仰心や尊敬の念、感謝の気持ちを示す表現としても使用されます。
古代中国から伝わった「詣参」という言葉が日本で発展し、現代でも広く用いられています。