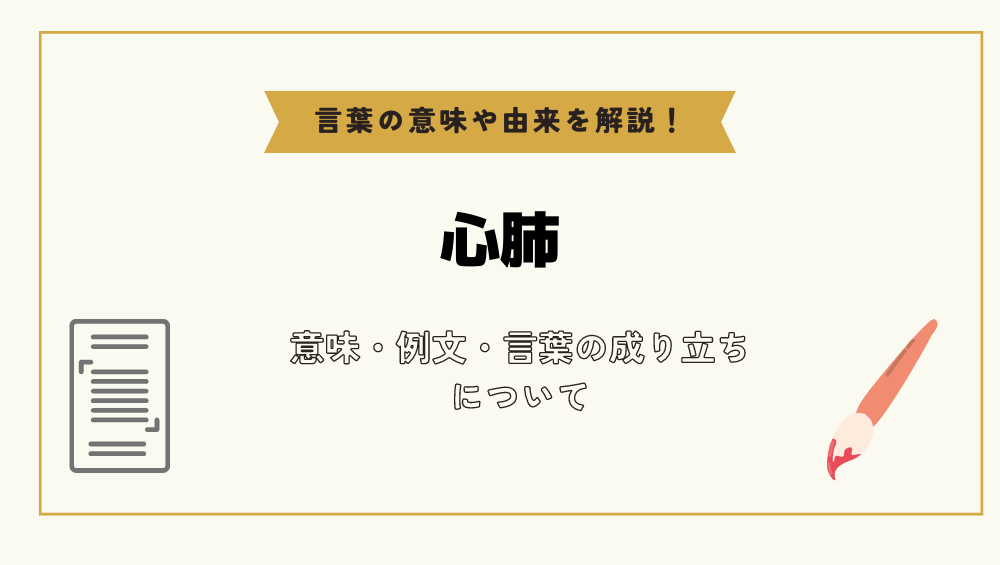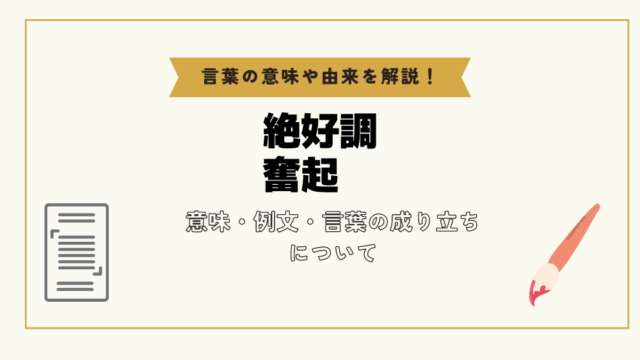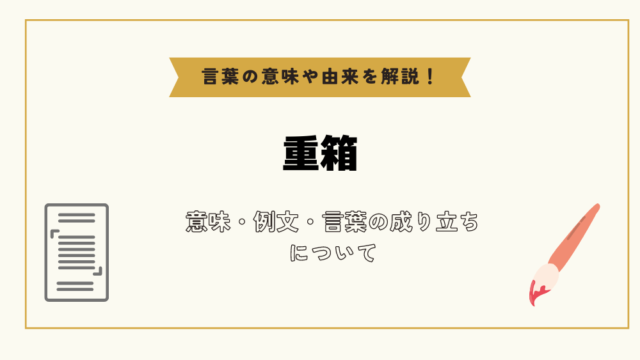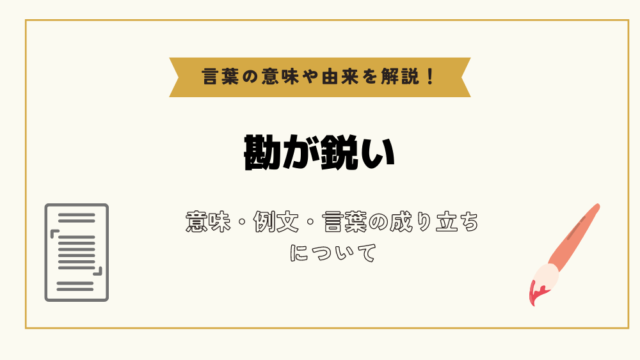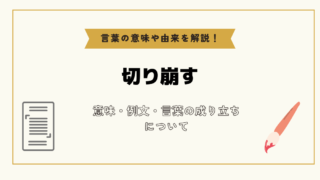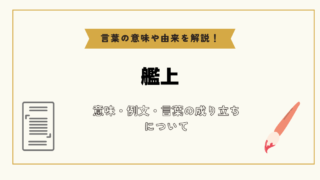Contents
「心肺」という言葉の意味を解説!
心肺(しんぱい)とは、心臓と肺のことを指します。
心臓は体に酸素と栄養を運び、老廃物を除去する重要な役割を果たしています。
一方、肺は酸素を取り込んで二酸化炭素を排出する呼吸の場となり、体内の酸素濃度を調節します。
心肺は人間の生命維持にとって欠かせないと言えるでしょう。心肺が正常に機能しない場合、酸素供給が十分に行われず、臓器や組織は損傷を受けます。そのため、心肺の健康は健康全体に大きな影響を及ぼします。
心肺の健康を保つためには、適度な運動やバランスの取れた食事、十分な睡眠が重要です。また、ストレスを適切に管理し、禁煙や適度な飲酒も心肺の健康に良い影響を与えます。
「心肺」という言葉の読み方はなんと読む?
「心肺」は、「しんぱい」と読みます。
日本語の「心」と「肺」の漢字を組み合わせ、それぞれの読み方を合わせたものです。
「心肺」という言葉の使い方や例文を解説!
「心肺」という言葉は、主に医学や健康に関する文脈で使用されます。
例えば、「心肺蘇生法」は、心停止や呼吸停止の状態での循環や呼吸を回復する手法を指す言葉です。
また、「心肺機能」という言葉は、心臓と肺の働きや能力を指し、個々の健康状態や身体能力の評価に使用されます。心肺機能が低下すると、日常生活の動作に制限が生じる可能性があります。
「心肺」という言葉の成り立ちや由来について解説
「心肺」という言葉は、日本語の「心」と「肺」という漢字を組み合わせたものです。
この言葉は、日本医学において生まれました。
心臓の役割は体内の血液を循環させることであり、肺は酸素を取り込み、二酸化炭素を排出する呼吸器官です。この2つの重要な器官を合わせて「心肺」と呼ぶようになったのです。
「心肺」という言葉の歴史
「心肺」という言葉は、古代中国の医学書にも見られます。
中国では、心臓や呼吸器官を指す言葉として、「心」と「肺」を組み合わせた呼称が使用されていました。
日本では、医学の発展とともに「心肺」の概念が広まり、現代の医療や健康の分野でも頻繁に使用されるようになりました。心臓と肺の重要性が理解されるにつれ、この言葉も一般に浸透していきました。
「心肺」という言葉についてまとめ
「心肺」という言葉は、心臓と肺を指す言葉であり、人間の生命維持に欠かせないものです。
心肺の健康を保つためには、適度な運動やバランスの取れた食事、十分な睡眠が大切です。
また、医療や健康の分野で広く使われる言葉であるため、その意味や使い方を理解しておくことが重要です。