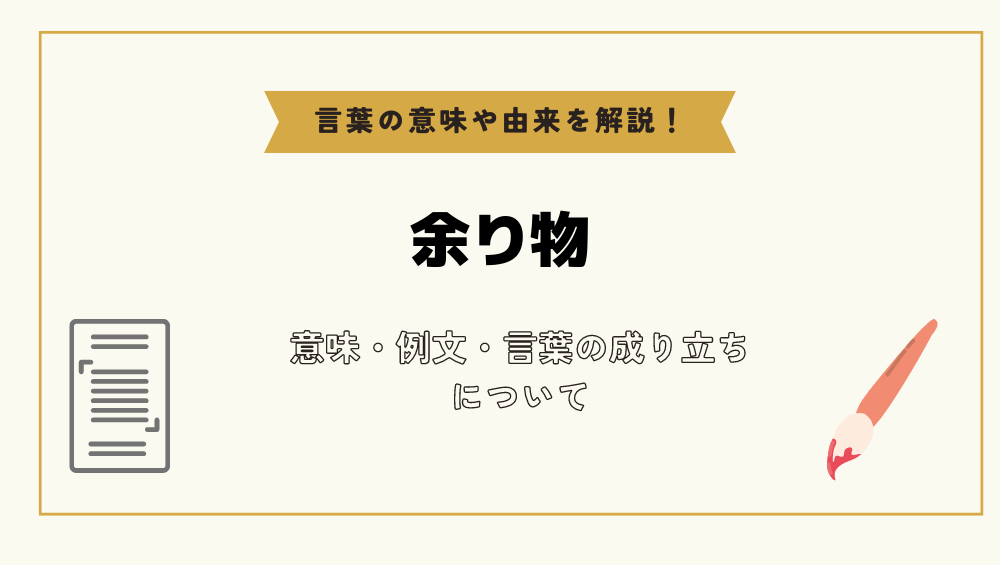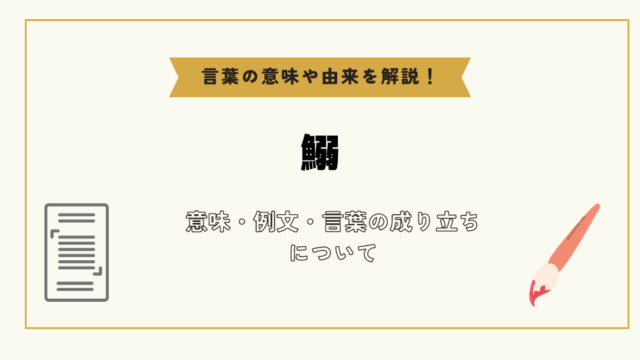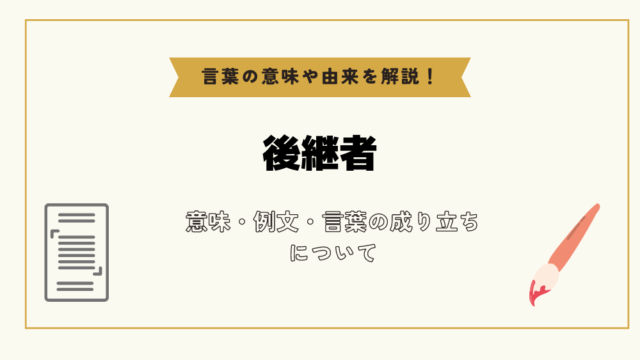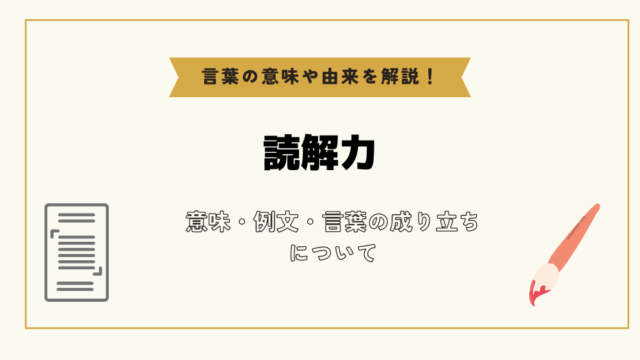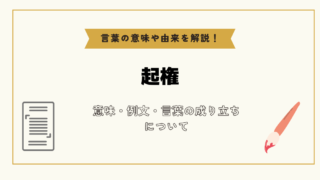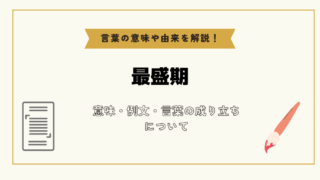Contents
「余り物」という言葉の意味を解説!
「余り物」という言葉は、主に食べ物や物の残りを指す言葉です。
何かを食べたり使ったりした後に、残った部分や余ったものを指すのが一般的です。
例えば、食事で残った食べ物や、使い終わった後の物の残りなどが「余り物」と呼ばれます。
「余り物」は、一般的にはあまり良い印象を持たれない言葉ですが、実は無駄を省くために活用されることも多いです。
また、食べ物の場合は、冷蔵庫に保存したり、別の料理にアレンジしたりすることで、無駄なく使われることもあります。
「余り物」という言葉の読み方はなんと読む?
「余り物」という言葉は、「あまりもの」と読みます。
「あまりもの」とは、物の残りや余りの意味を持ちます。
この読み方は、一般的な日本語のルールに基づいています。
「余り物」という言葉の使い方や例文を解説!
「余り物」という言葉は、日常会話や文章でよく使われる表現です。
例えば、食事の場面で、「残ったおかずは冷蔵庫に入れておこう。
明日の朝ごはんの「余り物」として有効活用できるかもしれないから」と言うことがあります。
また、物を使い終わった後に、その「余り物」を捨てずに再利用することもあります。
「このプラスチックの容器は、「余り物」として使えるから、大切に取っておこう」と考える人もいます。
「余り物」という言葉の成り立ちや由来について解説
「余り物」という言葉は、古代の日本語では「余物」と書かれていました。
「余(あま)り物」という表現自体は、平安時代には既に存在していたと言われています。
当時の文献によれば、その時代でも食事の「余り物」を再利用する考え方は存在していたようです。
「余り物」の使い方や意味は、時代とともに変わっていき、現代の日本語においても広く使用されている表現となりました。
「余り物」という言葉の歴史
「余り物」という言葉の歴史は古く、平安時代から存在していました。
当時の文献によれば、人々は無駄を省くために食事の「余り物」を再利用していたことがわかります。
時代が進むにつれ、食材や物の扱い方が変わり、余り物の再利用が一般的になりました。
現代でも、食べ物や物の無駄を省くために、「余り物」を上手に活用することは重要な課題です。
「余り物」という言葉についてまとめ
「余り物」という言葉は、主に食べ物や物の残りを指します。
日常生活や文章でよく使われ、無駄を省くために再利用されることもあります。
また、「余り物」という言葉は古くから存在し、平安時代から使われていました。
現代の日本語でも広く使用されており、無駄を省くために活用されています。
食べ物や物の扱い方において、「余り物」の再利用は重要な課題です。