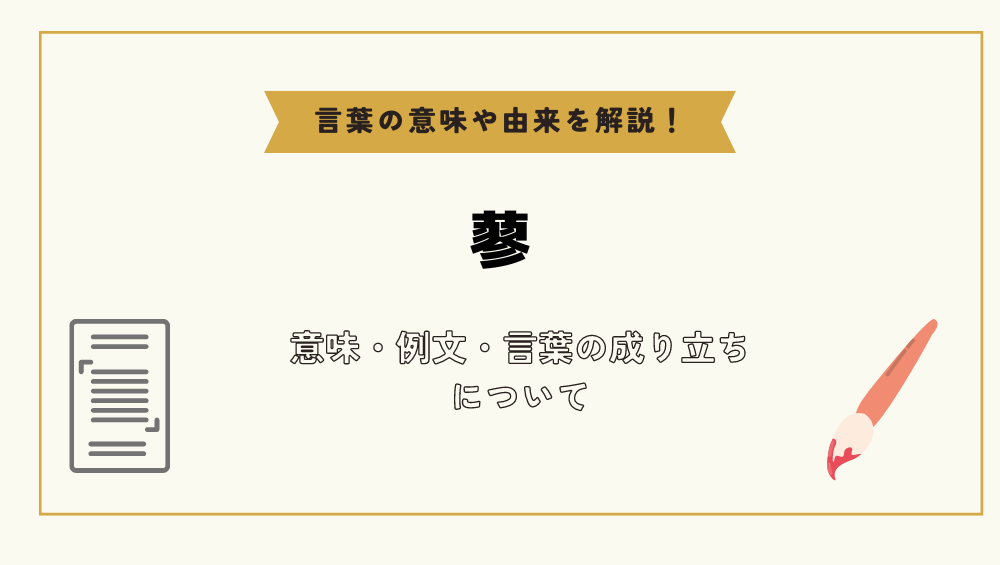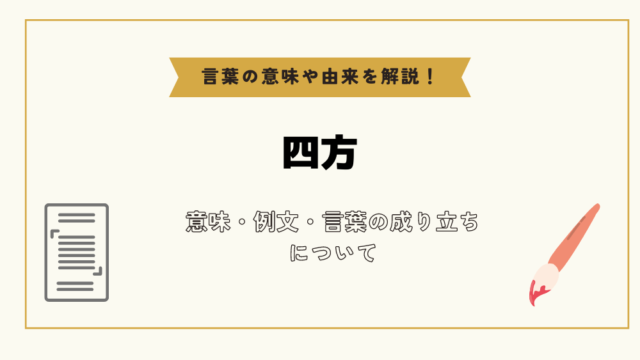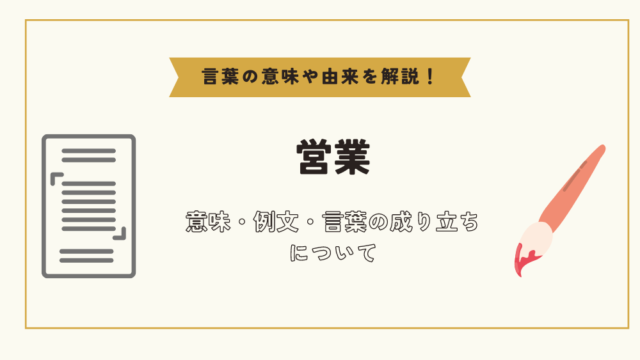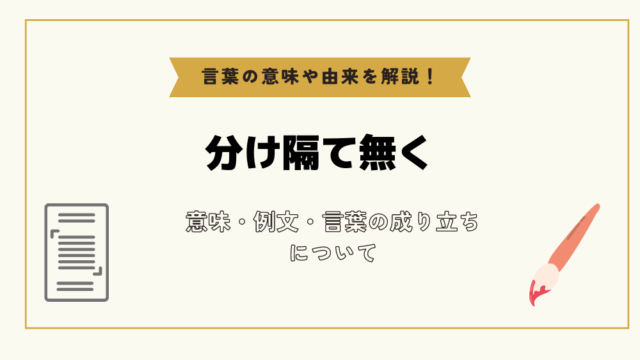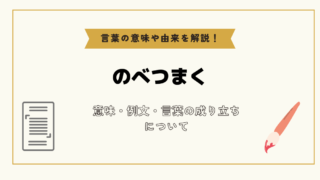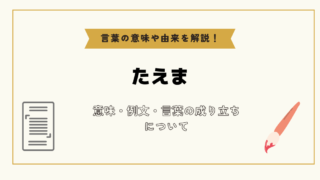Contents
「蓼」という言葉の意味を解説!
「蓼」という言葉は、特定の植物の名前を指す言葉です。
「蓼」は、タデ科の植物で、日本ではよく見かける雑草の一つです。
茎や葉にはセンニンソウやチシマザサといった種類がありますが、どの種類でも独特な香りがあります。
蓼は、自然の中で生育するため、日本の風景に深く関わっている存在です。
田畑や川岸などに生えており、近くにいくとよく見ることができるでしょう。
「蓼」という言葉の読み方はなんと読む?
「蓼」という言葉は、「タデ」と読みます。
「タデ」は、タデ科の植物を指す言葉で、一般的に使われる読み方です。
日本の自然環境でよく見かける植物なので、名前を知っておくと身近な存在として親しみを感じることでしょう。
「蓼」という言葉の使い方や例文を解説!
「蓼」という言葉は、主に植物の名前として使われます。
具体的には、センニンソウやチシマザサのことを指すことが一般的です。
例えば、「近くの川岸には蓼が生えていて、風情があります」と使うことができます。
また、「この場所で蓼を摘んで料理に使ってみましょう」と料理の材料としても用いることができます。
「蓼」という言葉の成り立ちや由来について解説
「蓼」という言葉の成り立ちは、そのままタデ科の植物を指すため、特に由来はありません。
しかし、日本人にとっては馴染み深い言葉です。
自然との関わりが深く、季節の移り変わりを感じさせてくれる存在であるため、日本文化においても重要な位置を占めています。
「蓼」という言葉の歴史
「蓼」という言葉の歴史は古く、古典文学にもよく登場します。
万葉集や古今和歌集などで詠まれることがありますし、俳句や川柳にも頻繁に出てきます。
そのため、日本人にとってはなじみ深い言葉として親しまれてきました。
「蓼」という言葉についてまとめ
「蓼」という言葉は、タデ科の植物を指す言葉です。
自然の風景や季節感を感じる上で重要な存在であり、日本文化にも深く関わっています。
日本語にはさまざまな植物の名前がありますが、「蓼」もその中で特に目にする機会が多い一つです。
近くに「蓼」が生えている場所を見かけたら、その香りを楽しみながら自然を感じてみてください。