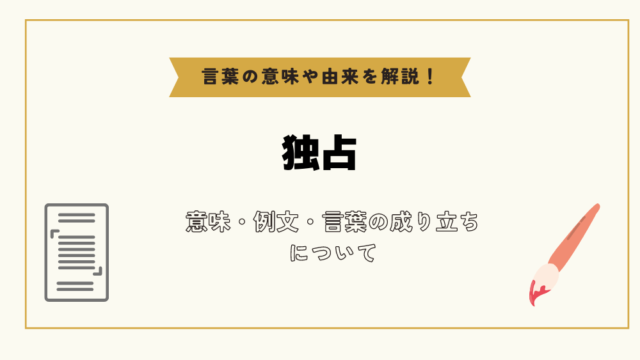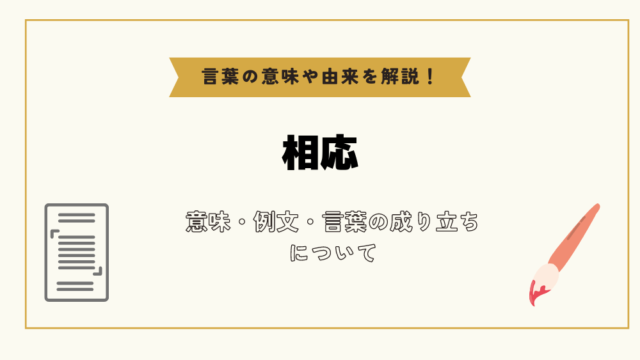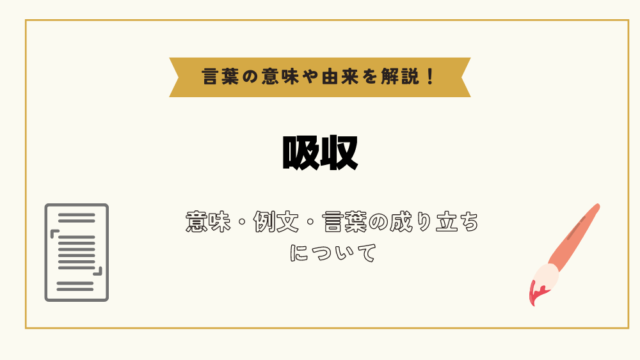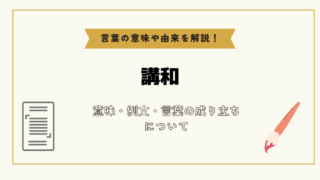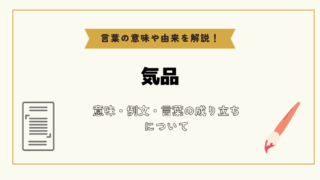「偽情報」という言葉の意味を解説!
「偽情報」とは事実と異なる、もしくは事実の一部だけを切り取って誤解を招く形で発信された情報を指します。この言葉には「意図的に相手をだます目的がある」というニュアンスが含まれており、単なる誤報(ミスリポート)とは区別されるのが特徴です。近年はインターネットやSNSの発達によって、個人が簡単に情報を発信できるようになり、偽情報が爆発的に増えました。
偽情報は大きく「デマ」と「プロパガンダ」の2種類に分けられます。前者は悪意というよりは面白半分や恐怖心から拡散されるケースが多く、後者は政治的・経済的利益を狙って組織的に流されるのが特徴です。いずれの場合も受け手が正しい情報リテラシーを身につけることが重要です。
具体的な危険性として、偽情報による混乱や差別、社会的分断が挙げられます。デマが原因で買い占めが発生したり、誤った医療情報が広まり健康被害が起こったりする例は少なくありません。こうした背景から「偽情報対策」が各国で重要視されているのです。
「偽情報」の読み方はなんと読む?
「偽情報」の読み方は「ぎじょうほう」です。音読みのみで構成された比較的シンプルな語なので、読み間違いは少ないものの「にせじょうほう」と口頭で言われることもあります。どちらも意味は同じですが、書き言葉としては「ぎじょうほう」が正式です。
日本語では「偽(ぎ)」が「フェイク」「虚偽」といった意味を帯びるため、この読み方を知っておくと関連語の理解も深まります。たとえば「偽装(ぎそう)」「偽計(ぎけい)」など、同じ読み方の語は法律文書でも登場するので、合わせて覚えると便利です。
読みやすさを重視する文章では、初出の際にルビ(ふりがな)を付けるか、カッコ書きで「ぎじょうほう」と補足することが推奨されます。誤認を防ぐためにも、専門用語に慣れていない読者向けの資料では特に注意が必要です。
「偽情報」という言葉の使い方や例文を解説!
「偽情報」はニュース報道や学術論文、SNS投稿など幅広い文脈で用いられます。文脈に応じて「誤情報」「フェイクニュース」と言い換えられることもありますが、いずれも「真実ではない情報」という共通点があります。ただし、誤情報が「意図せず誤って伝えられた情報」を指すのに対し、偽情報は「意図的」という点が大きな違いです。
【例文1】政府は選挙期間中に流布された偽情報の実態調査を行った。
【例文2】SNSで拡散されている噂の大半は偽情報である可能性が高い。
【例文3】偽情報を見抜く力を養うためにファクトチェックの方法を学ぶべきだ。
上記のように「偽情報」は名詞として単独で使うほか、「偽情報が~する」「偽情報を~する」という形で目的語や主語になるのが一般的です。ビジネスメールや報告書では「誤った情報」「不正確な情報」と併用すると、受け手に誤解を与えにくくなります。
「偽情報」という言葉の成り立ちや由来について解説
「偽情報」は「偽」と「情報」からなる合成語です。「偽」は古くから「にせ・いつわる」という意味で用いられ、『日本書紀』や『万葉集』にも類似表現が散見されます。「情報」は明治時代に西洋語の「information」を訳す形で一般化しました。
20世紀以降、国際社会で“disinformation”が問題視されるようになり、それを翻訳する語として「偽情報」が定着した経緯があります。とくに第二次世界大戦後、冷戦期の諜報活動で“disinformation”が頻繁に登場したため、日本でも報道や学術分野で使用され始めました。
このように「偽情報」は比較的新しい語ですが、構成要素である「偽」や「情報」は古くから日本語に存在していたため、違和感なく受け入れられたと言えます。
「偽情報」という言葉の歴史
偽情報の概念自体は古代から存在しました。例えば古代ローマの戦略家は敵を混乱させるために意図的な誤情報を流したと記録されています。日本でも戦国時代の「兵糧攻め」や「調略」において敵を欺くための虚報が行われました。
近代になると新聞やラジオが普及し、国家間の情報戦として偽情報が組織的に使われるようになります。第二次世界大戦では連合国と枢軸国が互いに偽情報を用いて敵の判断を誤らせました。冷戦期にはソ連と米国がプロパガンダとして偽情報を大規模に配信し、国際政治に深刻な影響を与えます。
21世紀のデジタル時代では、偽情報はSNSを通じて瞬時に世界へ広がり、選挙介入や株価操作など新たな脅威を生み出しています。その結果、各国でファクトチェック機関が設立され、プラットフォームもAIを使った検知システムを導入するなど対策が強化されています。
「偽情報」の類語・同義語・言い換え表現
偽情報の代表的な類語は「フェイクニュース」「デマ」「誤情報」「プロパガンダ」などです。これらは似て非なる概念なので、状況に応じて使い分ける必要があります。
・フェイクニュース…主にニュース形式で発信される偽情報。政治的・経済的意図を伴うことが多い。
・デマ…真実でない噂や流言。必ずしも組織的とは限らず、個人発のケースも多い。
・誤情報…意図せず発信された間違った情報。悪意が必ずしも存在しない点がポイント。
・プロパガンダ…特定の思想や政策を広めるために作為的に編まれた情報全般。
「偽情報」はこれらの上位概念として、意図的に虚偽を含む情報全般を指しうる便利な語です。文章の精度を高めるためにも、それぞれの違いを押さえておきましょう。
「偽情報」についてよくある誤解と正しい理解
「偽情報=完全な嘘」という誤解がしばしばありますが、実際には真実と嘘を巧みに混ぜることで信ぴょう性を高めたハイブリッド型が主流です。ほんの一部だけは事実であるため、受け手は簡単にだまされてしまいます。
もう一つの誤解として「偽情報は見抜ける人だけが対処すれば良い」という考えがありますが、拡散者の多くは一般市民であり、誰もが無関係ではいられません。そのため「情報源を複数確認する」「一次資料に当たる」「ファクトチェック団体の結果を参照する」など、日常的な対策が求められます。
【例文1】偽情報は完全なデタラメとは限らないため注意が必要だ。
【例文2】自分は騙されないと思い込むことが偽情報に落ちる最大の落とし穴だ。
「偽情報」を日常生活で活用する方法
偽情報という言葉を正しく理解すると、情報リテラシー向上に役立ちます。日常の会話やビジネスの場で「それは偽情報かもしれないので確認しましょう」と指摘することで、無用なトラブルを防げます。
家庭では子どもに対して「ネットには偽情報もある」と教え、検索結果を鵜呑みにしない力を育むことが大切です。また企業ではリスクマネジメントの一環として、社員向けに偽情報対策の研修を行うケースが増えています。
【例文1】社員全員が偽情報の検知ツールを使えるよう研修を実施した。
【例文2】子どもと一緒にニュースを読み、偽情報と真情報を見分けるゲームをした。
「偽情報」という言葉についてまとめ
- 偽情報とは意図的に虚偽を含めて発信される情報の総称。
- 読み方は「ぎじょうほう」で、書き言葉が基本。
- 冷戦期の“disinformation”翻訳として定着し、現代ではSNSで拡散が顕著。
- ファクトチェックと複数情報源の確認が対策の鍵。
偽情報は単なる間違いではなく、作為的に真実を歪める危険な情報形態です。読み方は「ぎじょうほう」と覚え、他者に説明するときは「フェイクニュース」などとの違いも示すと理解が深まります。
歴史的には古代の軍事作戦から冷戦の諜報活動を経て、デジタル時代に大きく進化しました。現代の私たちに求められるのは、情報を鵜呑みにせず複数ソースを当たり、ファクトチェックを習慣化する姿勢です。
偽情報に対する正しい知識を持ち、家庭や職場で共有することで、社会全体の情報リテラシーが向上します。今日から意識してみるだけで、あなたの生活はより安全でストレスの少ないものになるでしょう。