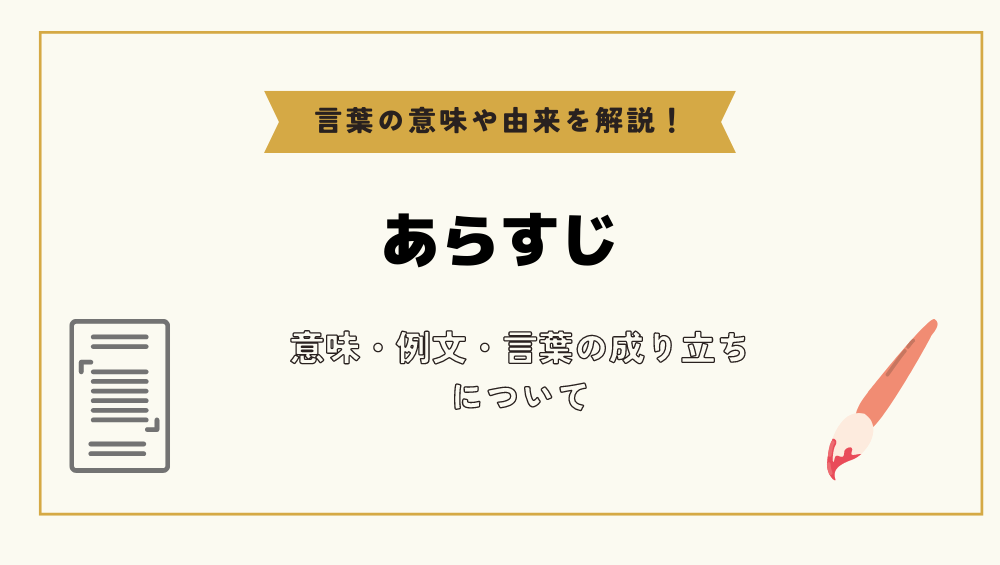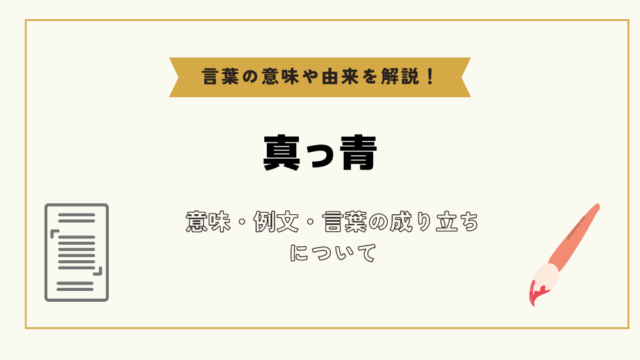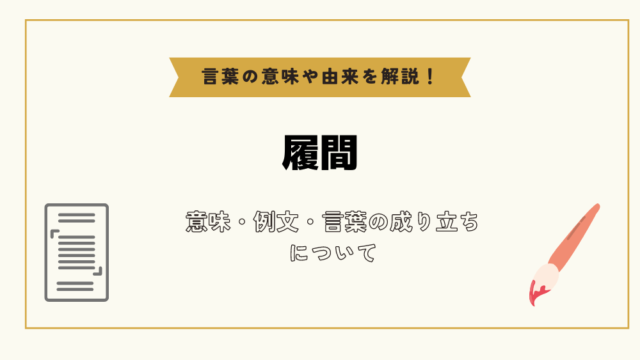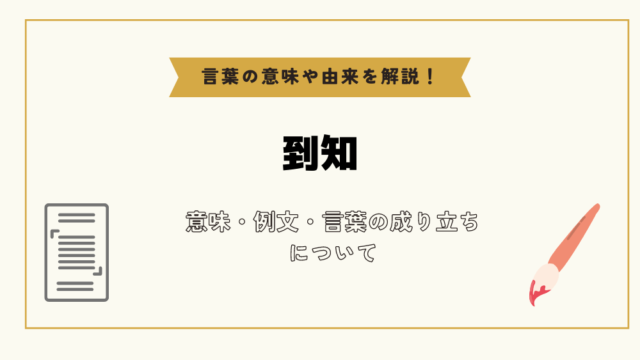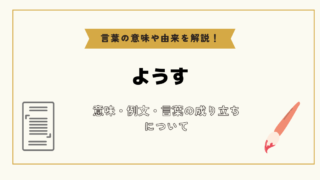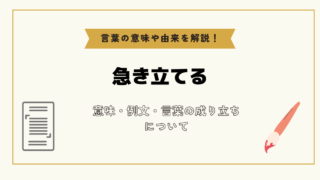Contents
「あらすじ」という言葉の意味を解説!
「あらすじ」という言葉は、物語や映画、ドラマなどの内容を簡単にまとめたものを指します。
作品の要点や流れを把握するために、事前にあらすじを読むこともあります。
「あらすじ」は、日本語の名詞であり、英語では「summary」と表現されます。
物語の骨子や大まかな筋書きを端的に伝えるため、短い文章でまとめられることが特徴です。
例えば、小説を紹介する際には「この小説は、ある事件をきっかけに主人公が大きな変化を遂げる物語です」といったように、要点を抑えた文を使ってあらすじを紹介することがあります。
「あらすじ」の読み方はなんと読む?
「あらすじ」の読み方は、「あらすじ」となります。
これは、音読みではなく、訓読みと呼ばれる読み方です。
日本語の中には、意外な読み方をする言葉も多く存在しますが、幸いにも「あらすじ」はそのまま読めるため、覚えやすい読み方と言えます。
「あらすじ」という単語は、日本語に馴染みのある読み方であり、多くの人が理解することができます。
特に書籍や映画などの作品紹介の際によく使用されるため、そのままの読み方で活用していくと良いでしょう。
「あらすじ」という言葉の使い方や例文を解説!
「あらすじ」という言葉は、物語や作品の内容を伝えるためによく使われます。
例えば、映画の宣伝広告や書籍の帯などで「この作品は、感動的な人間ドラマが描かれており、見る者を魅了します」というような文に続いて「あらすじ」という言葉が使われることがあります。
また、ネット上には多くのサイトがあり、そこでは映画やドラマのあらすじを紹介していることもあります。
このような場合、例えば「あらすじは以下の通りです」といった形式で、物語の要点や魅力的な展開を分かりやすく述べています。
「あらすじ」という言葉の成り立ちや由来について解説
「あらすじ」という言葉は、古くから日本に存在する言葉ではありません。
もともとは、中国語の「概要(がいよう)」を意味する言葉が転じて、日本語で使用されるようになりました。
日本語における「あらすじ」の成り立ちは、現在使用されている「あらし」と「時事(じじ)」という言葉を組み合わせることで作られました。
「あらし」は、「あらためる」「まとめる」という意味合いを持ち、「時事」は「物事の事情や流れ」という意味を持ちます。
このように、「あらし」と「時事」が組み合わさることで、物事の要点や流れをまとめるという意味が込められた「あらすじ」という言葉が誕生したのです。
「あらすじ」という言葉の歴史
「あらすじ」という言葉は、古代の日本においてはあまり使用されていなかったとされています。
物語や作品について触れる際には別の表現方法が用いられていました。
しかし、近代になり、文学や演劇の普及とともに「あらすじ」という言葉が一般化しました。
特に映画の普及は、物語の要点を簡潔かつ効果的に伝える必要性を生み出し、そのための便利な言葉として「あらすじ」が使われるようになりました。
そして現在では、書籍や映画、テレビドラマなどさまざまな作品を紹介する際に「あらすじ」という言葉が頻繁に使われており、多くの人々に親しまれています。
「あらすじ」という言葉についてまとめ
「あらすじ」という言葉は、物語や作品の内容や要点を簡潔にまとめたものを指します。
日本語でよく使われる単語であり、英語では「summary」と表現されます。
「あらすじ」という言葉は、物語の流れを把握するためや作品の紹介に役立ちます。
その読み方は「あらすじ」となり、音読みではありません。
「あらすじ」という言葉は、作品紹介や映画の宣伝広告などでよく使われます。
ネット上でも、物語の要点や展開を分かりやすくまとめた「あらすじ」が紹介されています。
「あらすじ」という言葉の成り立ちは、中国語の「概要」を意味する言葉が転じて日本語で使われるようになりました。
その組み合わせ方が「あらし」と「時事」という言葉です。
おそらく、「あらすじ」という言葉は、近代になってから一般化したと考えられます。
文学や演劇の普及とともに使用されるようになり、特に映画の普及によって広まりました。