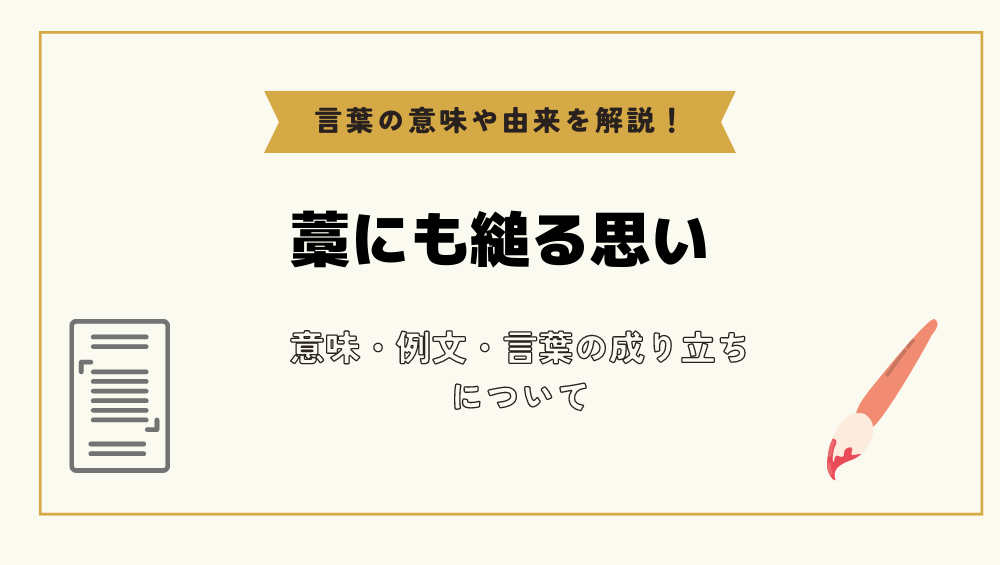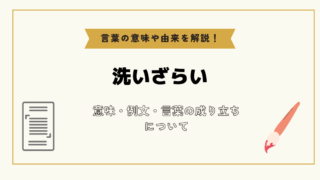Contents
「藁にも縋る思い」という言葉の意味を解説!
「藁にも縋る思い」という言葉は、何か困難な状況に直面した時に、自分の力だけではどうにもならず、あらゆる手段を使っても助けを求める心情のことを指します。
例えば、絶望的な状況において、最後の手段としてもがきつつも希望を捨てずに頼みの綱とする気持ちや、苦しい現実から逃れるために必死に助けを求める思いを含んでいます。
この言葉は、困難に直面した人々の深い心情を表現する枕詞として広く使われています。
「藁にも縋る思い」の読み方はなんと読む?
「藁にも縋る思い」は、「わらにもすがるおもい」と読みます。
この言葉は日本の伝統的な言い回しであり、古くから使われてきた表現です。
「藁にも縋る思い」という言葉の使い方や例文を解説!
「藁にも縋る思い」は、自分の困難な状況や苦しみから逃れるために、あらゆる手段を使ってもがき苦しむ様子を表現する言葉です。
例えば、試験に落ちた後の学生が「藁にも縋る思いで家庭教師を頼んだ。
」と言うように、自分の力だけではどうにもならないと感じ、最後の手段として頼みの人や物、考え方を求める様子を示しています。
「藁にも縋る思い」という言葉の成り立ちや由来について解説
「藁にも縋る思い」という言葉は、昔の日本で農業が主体であり、悪天候や災害によって作物が失われることが多かった時代に生まれた言葉です。
藁は農作物を育てるために必要なものであり、失われた収穫物を取り戻すために、農民たちは藁にすがる思いで必死に努力したことが由来とされています。
「藁にも縋る思い」という言葉の歴史
「藁にも縋る思い」という言葉の歴史は古く、平安時代の文学作品や和歌にも登場しています。
その後も日本の文学や民間伝承で頻繁に使用され、広く一般に知れ渡るようになりました。
現代では、この言葉はさまざまな場面で使われ、困難な状況に直面した人々の心情や苦しみを表現するために広く用いられています。
「藁にも縋る思い」という言葉についてまとめ
「藁にも縋る思い」という言葉は、決して強い力を持っているわけではありませんが、困難な状況や絶望的な時に、最後の手段として頼みの綱とする心情を表現する言葉です。
日本の伝統的な表現として、広く使われているとともに、人々の共感を呼び起こす力を持っています。
この言葉は、私たちが頼みの綱を求める心情を象徴し、人間の弱さと向き合うための言葉とも言えます。