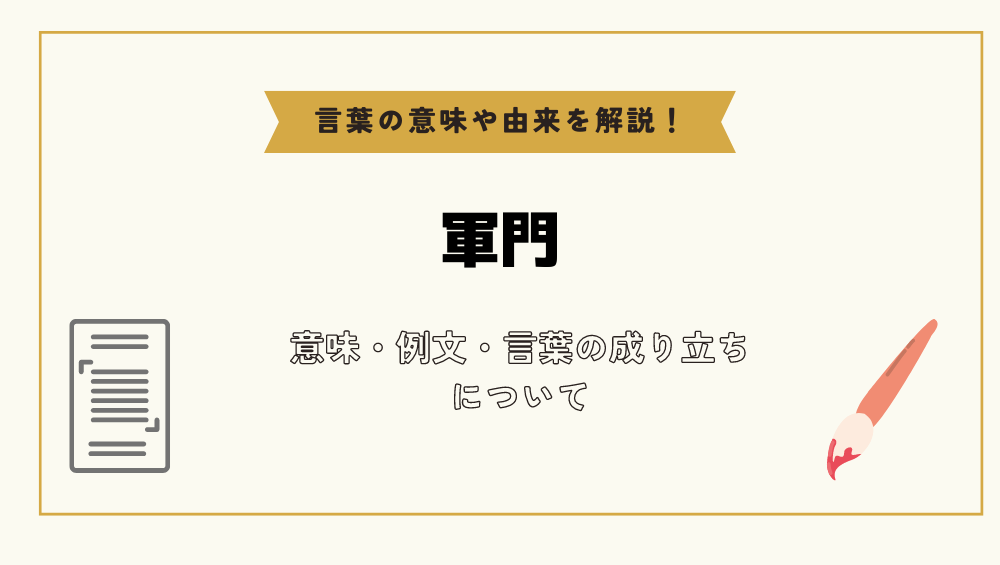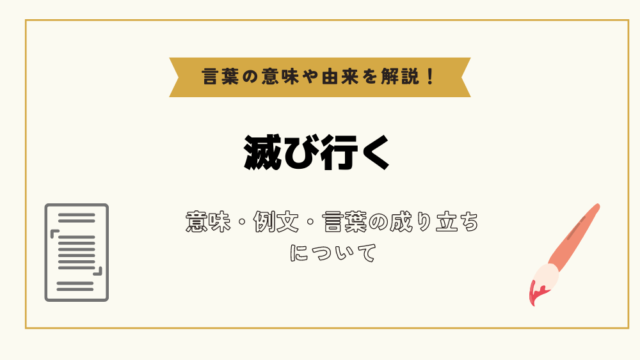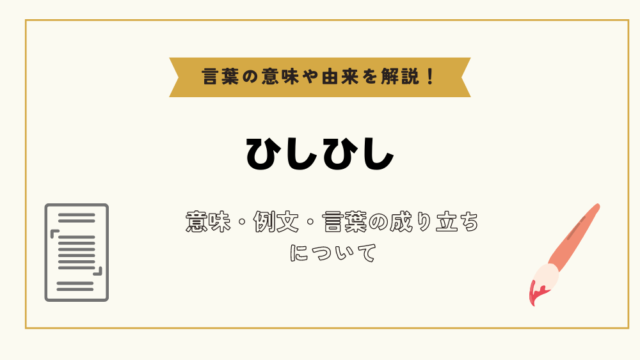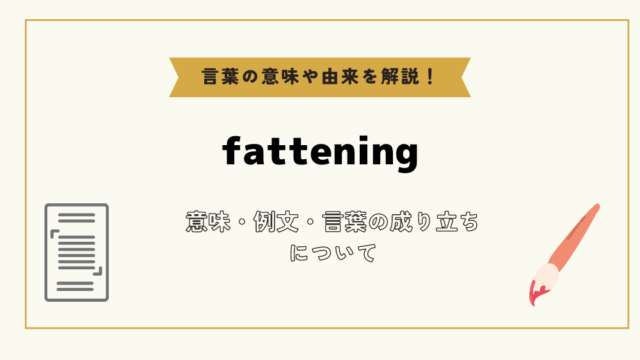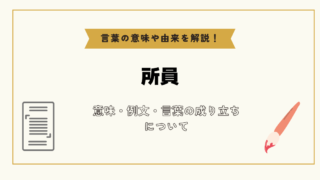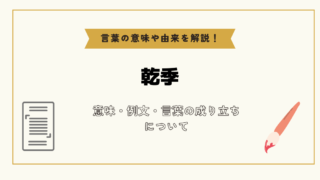Contents
「軍門」という言葉の意味を解説!
軍門(ぐんもん)とは、軍の指揮下に入ることを指す言葉です。
軍隊に所属する者が命令に従い、軍の組織の一員となることを意味しています。
この言葉は軍人や歴史関係の書物や作品でよく使われます。
軍門に下ることは、個人の意識や行動が軍の統制下に置かれることを示しています。
軍隊の厳しい規律や原則に従い、任務に忠実に取り組む姿勢を持つことが求められます。
「軍門」という言葉の読み方はなんと読む?
「軍門」という言葉は、読み方は「ぐんもん」となります。
日本語の読み方として一般的な音読みです。
幅広い世代や層に浸透しているため、多くの人々がこの読み方を知っています。
軍門という言葉を正しく伝える際は、「ぐんもん」という言葉を使用しましょう。
「軍門」という言葉の使い方や例文を解説!
「軍門」という言葉は、主に文学作品や歴史関連の書籍で使用されることがあります。
例えば、あるキャラクターが自身の意志で軍隊に参加する場面で、「私は軍門に下る」と言ったりします。
このような場合、そのキャラクターが軍の一員として戦い、組織の一翼を担っていくことを意味しています。
「軍門」という言葉の成り立ちや由来について解説
「軍門」という言葉の成り立ちは、中国の古典や兵法書に由来しています。
中国の古代において、将軍や武将のもとに兵士が集まり、彼らの統率の下で戦いに参加することがありました。
このような兵士の行動が「軍門に下る」と表現されました。
その後、日本においても同様の使い方が広まり、現代でも軍の指揮下に入ることを「軍門に下る」と形容することが一般的となりました。
「軍門」という言葉の歴史
「軍門」という言葉は、古代中国から伝わり、日本でも使われるようになりました。
日本の歴史においては、戦国時代や幕末の動乱時に多く用いられました。
戦国大名や武将たちは、自身の軍に兵士を集め、軍門に下らせました。
指導者としての権威を示すためにも、「軍門」は重要な言葉でした。
そして現代でも、軍事組織や歴史文化、文学作品などで「軍門」という言葉が使われ続けています。
「軍門」という言葉についてまとめ
「軍門」という言葉は、軍の指揮下に入ることを指し、軍人や歴史関連の文化や文学作品でよく使われます。
この言葉は軍の規律や組織に従い、使命を果たす姿勢を表現しています。
また、中国の古典や兵法書に起源を持ち、日本にも古くから伝わってきた言葉です。
戦国時代や幕末の歴史においても重要な役割を果たし、現代においてもその意味や用途は変わっていません。