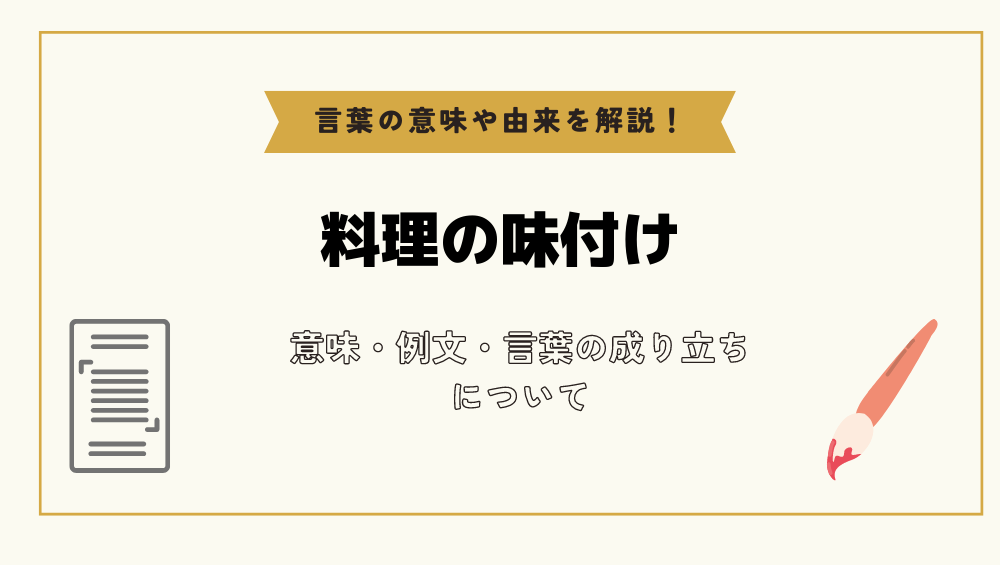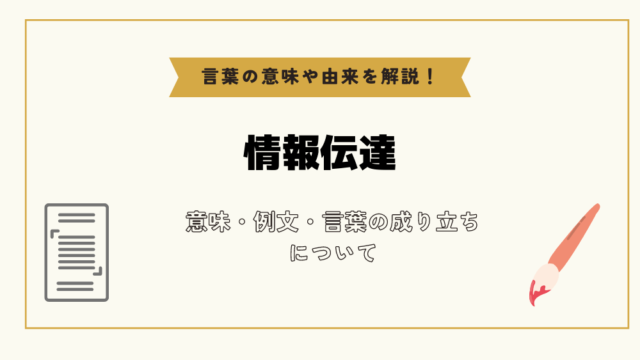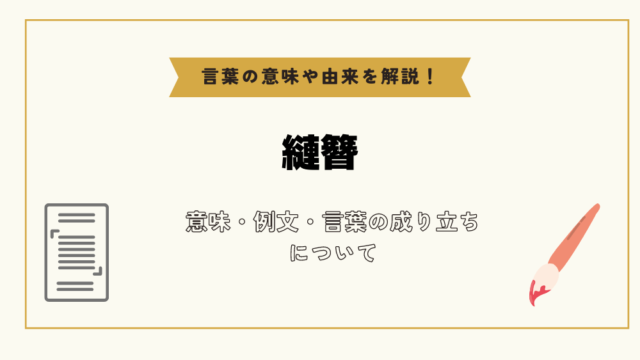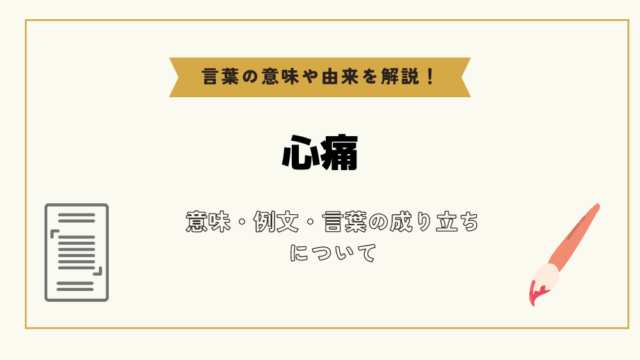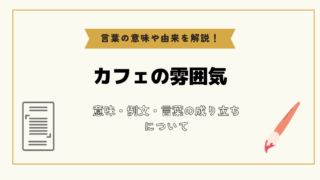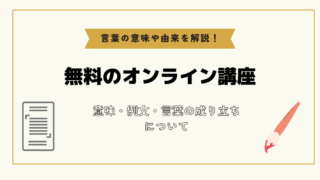Contents
「料理の味付け」という言葉の意味を解説!
料理の味付けとは、料理に風味や味を付けることを指します。
食材の味を引き立たせたり、調味料やスパイスを使って料理に深みやアクセントを与えることで、一品の料理がさらに美味しくなるのです。
料理の味付けは、シンプルなものから複雑なものまでさまざまな方法がありますが、どのような料理にも欠かせない要素と言えるでしょう。
「料理の味付け」という言葉の読み方はなんと読む?
「料理の味付け」という言葉は、「りょうりのあじつけ」と読みます。
日本語の読み方で分かりやすく、なおかつ一般的な表現です。
これなら、どなたでもすぐに理解できるでしょう。
「料理の味付け」という言葉の使い方や例文を解説!
「料理の味付け」という言葉は、料理のレシピを作る上で重要な項目です。
例えば、「この料理の味付けは、塩、醤油、胡椒で調整してください」といった具体的な指示が含まれています。
味付けは、調味料の種類や量、順番などによっても異なるので、レシピや料理の指示にはしっかりと目を通しましょう。
「料理の味付け」という言葉の成り立ちや由来について解説
「料理の味付け」という言葉の成り立ちは、主に日本の料理文化に由来しています。
日本では、風味や味わいを重視することが一般的であり、調味料やスパイスを使った味付けは欠かせないものとされています。
また、日本の伝統的な料理や地域料理においても、独自の味付け方法が発展してきた歴史があります。
「料理の味付け」という言葉の歴史
「料理の味付け」という言葉の歴史は、古代から続いています。
古代の日本では、岩塩や醤油、味噌などが主な調味料として使用され、さまざまな料理に味付けの要素が加えられていました。
また、江戸時代には料理の味付けに対するさらなる工夫が行われ、多くの料理書や調理法が生まれました。
現代では、洋風料理や世界各国の料理の影響も取り入れつつ、新たな味付けの方法やアイディアが生み出されています。
「料理の味付け」という言葉についてまとめ
「料理の味付け」という言葉は、料理における重要な要素であり、食材の味を引き立たせる役割を果たしています。
シンプルな料理から複雑な料理まで、どのような料理でも味付けが欠かせないものと言えるでしょう。
また、日本の料理文化や歴史においても、料理の味付けに対する工夫や研究が行われてきました。
私たちが普段口にする美味しい料理には、それぞれの料理の味付けがしっかりと施されているのです。