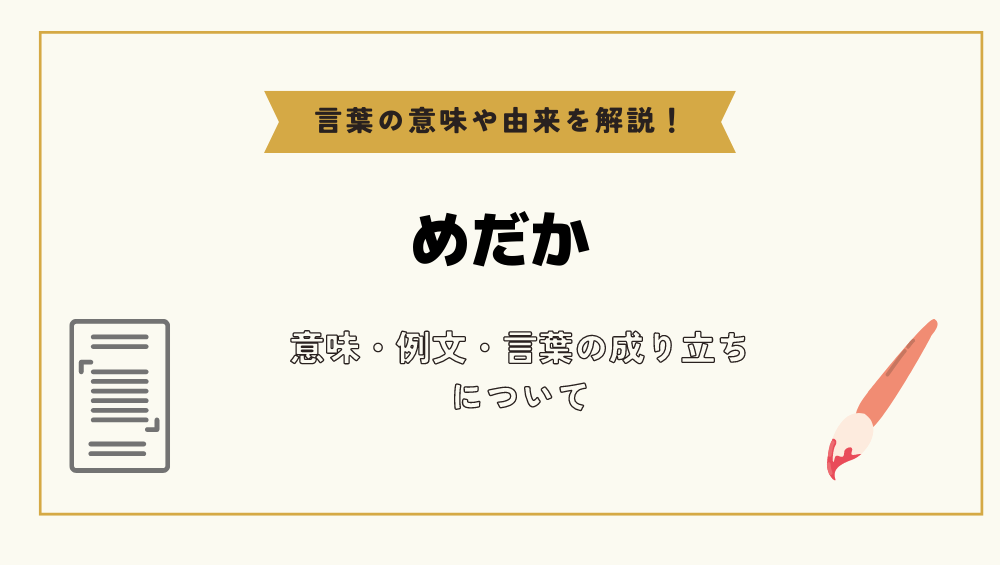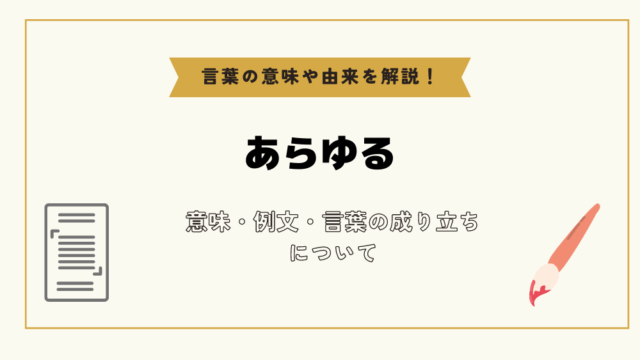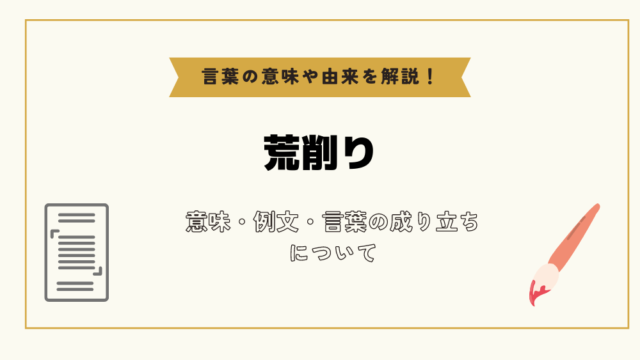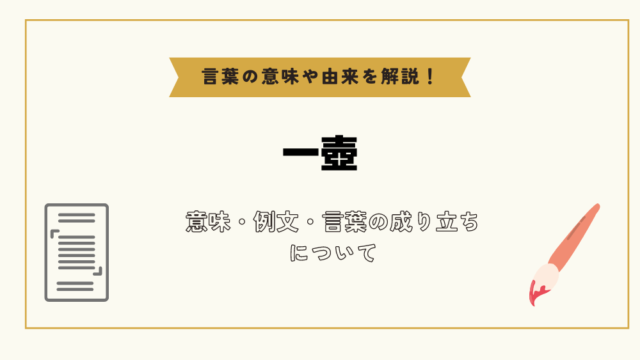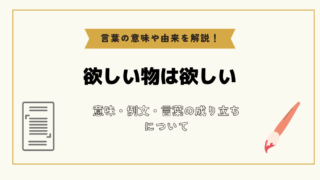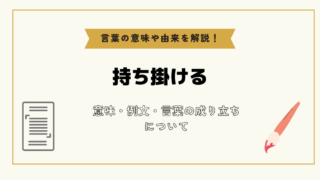Contents
「めだか」という言葉の意味を解説!
「めだか」とは、日本の淡水魚の一種を指す言葉です。
カエルや金魚に比べて小さいサイズで、鮮やかな色と可愛らしい姿が特徴です。
また、めだかは繁殖能力が高く、飼育が比較的容易なため、愛好家に人気のあるペットとして飼われています。
めだかは色とりどりで可愛い姿が特徴です。
。
「めだか」という言葉の読み方はなんと読む?
「めだか」という言葉の読み方は、「めだか」となります。
これは、そのままの読み方で広く使われる呼び方です。
日本語の読み方としては非常に一般的なものですので、誰もが聞いたことがある言葉かもしれません。
「めだか」という言葉は、「めだか」と読みます。
。
「めだか」という言葉の使い方や例文を解説!
「めだか」という言葉は、魚の名前として使われることが一般的です。
例えば、「庭でめだかを飼っています」と言うと、庭に飼われているめだかの存在を伝えることができます。
また、「めだかの水槽を飾っています」と言うと、めだかを飼っている人が水槽を飾ることによって、より美しい風景を楽しんでいることが伝わります。
「めだか」という言葉は、魚の名前として使われることがあります。
。
「めだか」という言葉の成り立ちや由来について解説
「めだか」という言葉の成り立ちや由来については、具体的な情報はわかっていません。
しかし、めだかは古くから日本で愛されてきた魚であり、日本独自の品種改良が行われてきたと言われています。
そのため、日本の魚として長い歴史を持ち、多くの人々に親しまれています。
「めだか」という言葉の成り立ちや由来については詳しい情報はわかっていません。
。
「めだか」という言葉の歴史
「めだか」という言葉の歴史は古く、江戸時代から飼育が行われてきました。
江戸時代の記録には、めだかの飼育法や品種改良に関する記述が見られます。
また、近代に入りめだかの人気が再燃し、さまざまな品種が誕生しました。
現在では、めだかの飼育や品評会なども行われ、多くの人々に親しまれています。
「めだか」という言葉は、江戸時代から飼育が行われてきた歴史を持っています。
。
「めだか」という言葉についてまとめ
「めだか」という言葉は、日本の淡水魚を指す言葉です。
その鮮やかな色と可愛らしい姿が人気であり、多くの人々が愛好しています。
また、「めだか」という言葉の由来や歴史については具体的な情報はわかっていませんが、古くから愛されてきた魚であることは間違いありません。
さまざまな品種が誕生し、現在でも広く飼育されています。