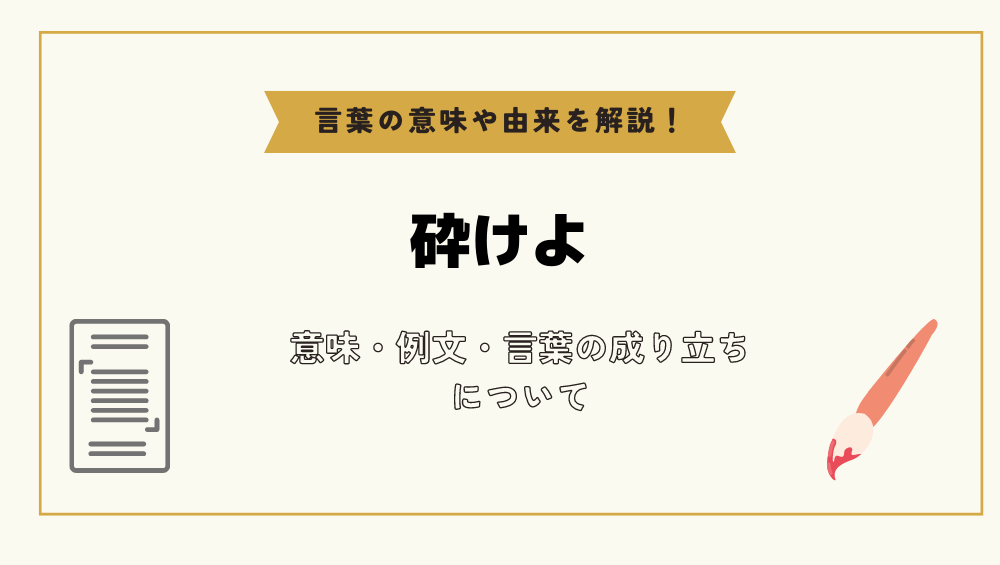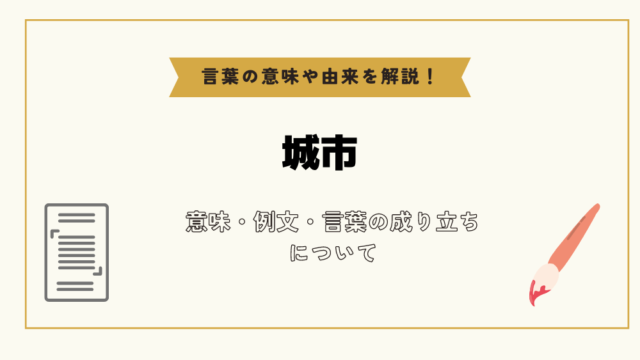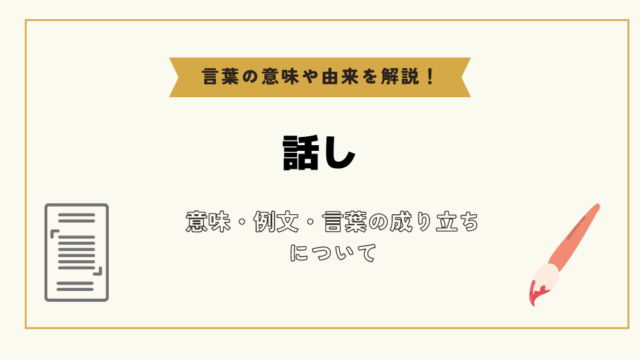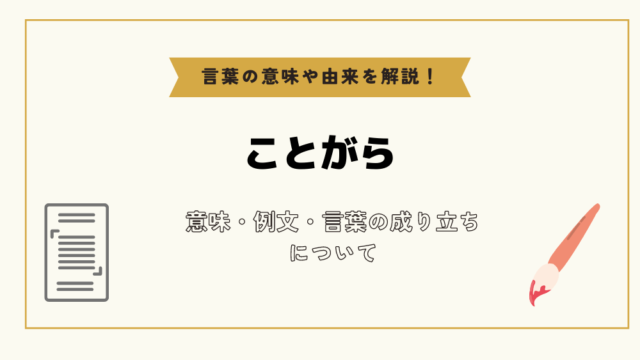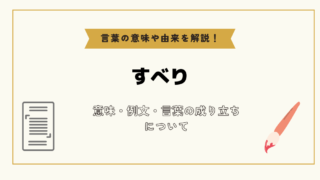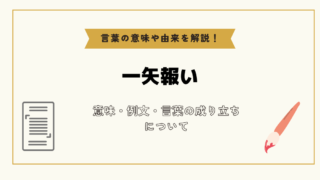Contents
「砕けよ」という言葉の意味を解説!
「砕けよ」という言葉は、固く閉ざされた心や考えを開放し、自由な発想や行動を促す言葉です。
この言葉には、束縛から解放され、自分らしく生きることの大切さや、自分を偽らずに素直に向き合う勇気を持つことが含まれています。
「砕けよ」という言葉は、物事に囚われずに自由に成長や創造を遂げることを意味しています。
たとえば、自分の思いや夢を他人に押し殺されることなく、思い切って挑戦することや、失敗を恐れずに前向きに取り組む姿勢を持つことが「砕けよ」の意味に沿った行動と言えます。
「砕けよ」の読み方はなんと読む?
「砕けよ」は、「くだけよ」と読みます。
この言葉は、日本の古典的な言葉であり、口語表現としても使われています。
日本人にとっては馴染み深い言葉であり、一度は耳にしたことがあるかもしれません。
「砕けよ」という言葉の使い方や例文を解説!
「砕けよ」という言葉は、日常生活の中でさまざまな場面で使うことができます。
例えば、友人や家族が関わるプロジェクトやイベントに参加する際に、「みんなでアイデアを出し合って砕けよう!」と声を掛けることができます。
また、「砕けよ!」という言葉は、自分や他の人が心の中で葛藤しているときに、気持ちを解放し、素直になるように促す効果もあります。
相手に対して「砕けた意見を聞かせてほしい」と言うことで、より率直な意見や本音を引き出すこともできるでしょう。
「砕けよ」という言葉の成り立ちや由来について解説
「砕けよ」という言葉は、江戸時代の剣術家や武士たちの言葉として生まれました。
剣術の修行や武道においては、心を開放し、自由な動きや判断をすることが重要視されており、この言葉が使われるようになりました。
また、「砕けよ」という言葉は、江戸時代の文学や浄瑠璃などでも頻繁に使用されていました。
この言葉は、当時の人々にとって、自由な精神や生き方を表現する言葉として親しまれていました。
「砕けよ」という言葉の歴史
「砕けよ」という言葉は、江戸時代から現代まで受け継がれてきた言葉です。
特に、日本の武道や古文学において、この言葉が多く使用されてきました。
しかし、現代の日本でも、この言葉はその意味や効果から広く使われています。
また、「砕けよ」という言葉は、映画やドラマ、小説などの作品でも頻繁に登場します。
そのため、多くの人々にとってなじみ深い言葉となっています。
「砕けよ」という言葉についてまとめ
「砕けよ」という言葉は、自由な発想や行動を示す言葉であり、自分らしく生きることの大切さを教えてくれます。
この言葉は、江戸時代から受け継がれ、現代でも活用されています。
自分の心や考えを砕いて、新たな可能性を見つけ出すことは、成長や創造の道に繋がるのです。