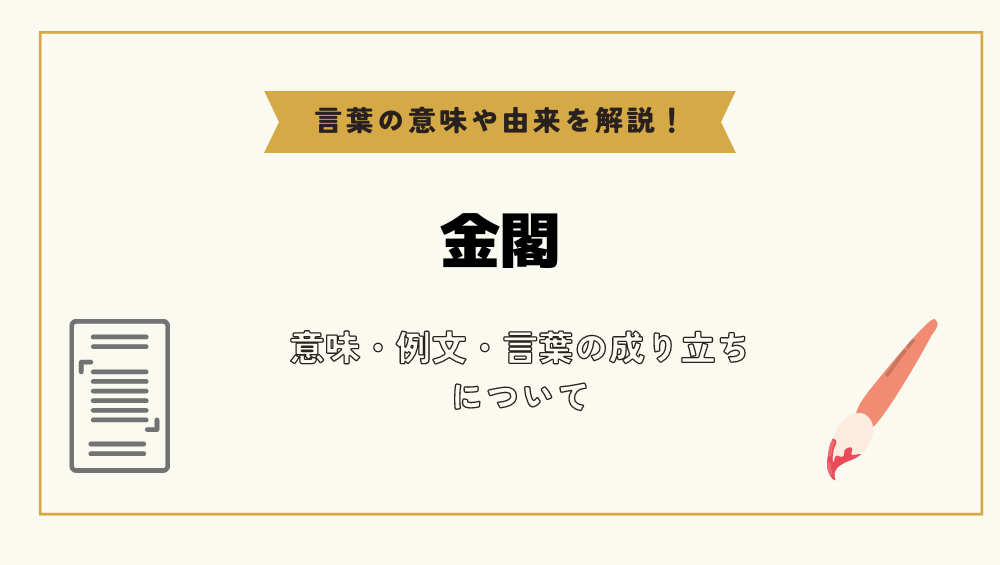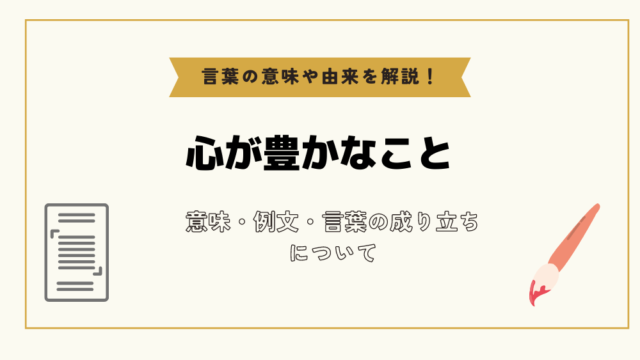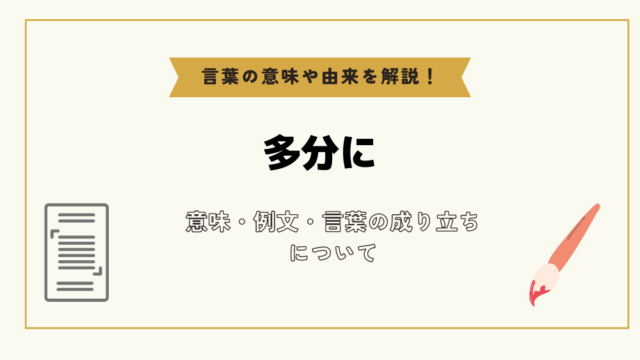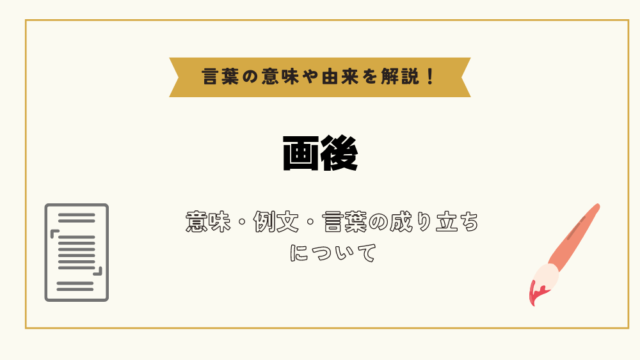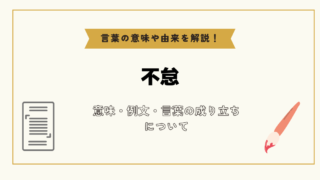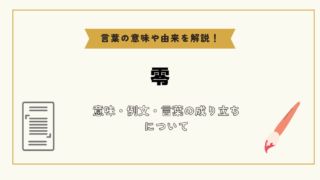Contents
「金閣」という言葉の意味を解説!
「金閣」という言葉は、日本の京都にある鹿苑寺の別名です。
正式な名前は「金閣寺」といい、室町時代に建てられました。
この寺は、美しい金箔で覆われた3層の塔が特徴で、国内外から多くの人々が訪れる観光名所となっています。
「金閣」の読み方はなんと読む?
「金閣」は、日本語の「きんかく」と読みます。
一部では「きんかくじ」とも呼ばれることもありますが、一般的には「きんかく」と言われています。
「金閣」という言葉の使い方や例文を解説!
「金閣」は、鹿苑寺の別名ですが、一般的にはこの寺院を指す場合に使われます。
例えば、「今年の夏休みには金閣を訪れたいです」という風に使うことができます。
「金閣」という言葉の成り立ちや由来について解説
「金閣」という言葉の成り立ちや由来は、鹿苑寺の創建の経緯に関係しています。
鹿苑寺は、室町時代に足利義満によって建立され、元々は義満の別邸として使用されていました。
その後、義満の死後に寺となり、再建された際に金箔で覆われた塔が建てられたのです。
「金閣」という言葉の歴史
「金閣」の歴史は、室町時代から始まります。
足利義満によって建立された鹿苑寺には、当初から金箔で覆われた塔が存在しました。
しかし、1950年代に失火によって焼失してしまいました。
その後、当時の建築様式を再現する形で復興され、現在に至っています。
「金閣」という言葉についてまとめ
「金閣」という言葉は、日本の京都にある鹿苑寺の別名です。
金箔で覆われた3層の塔が特徴で、美しい景観が人々を魅了しています。
室町時代から存在し、現在も多くの人々に愛されています。