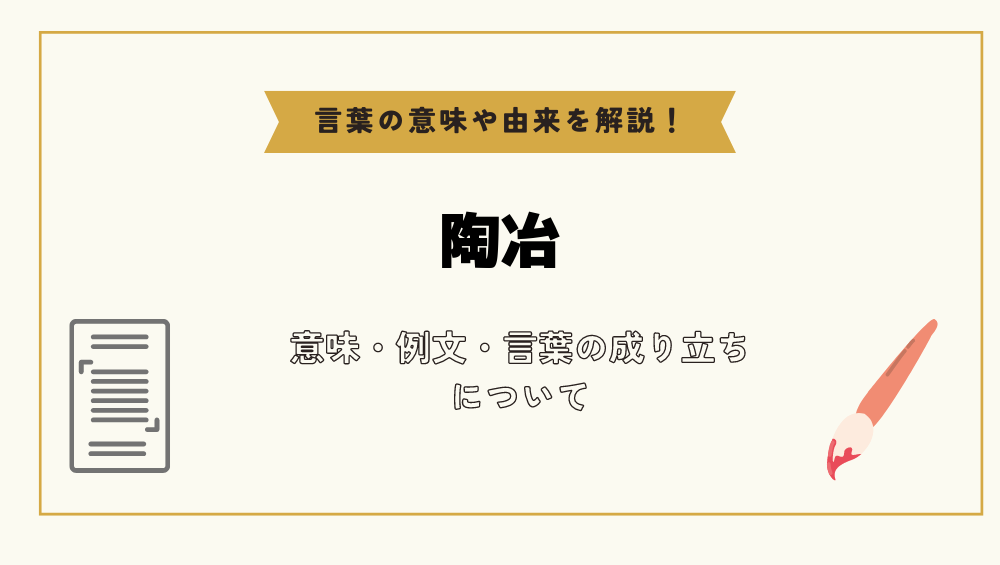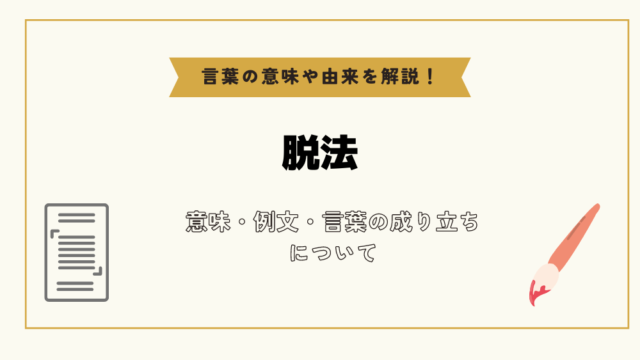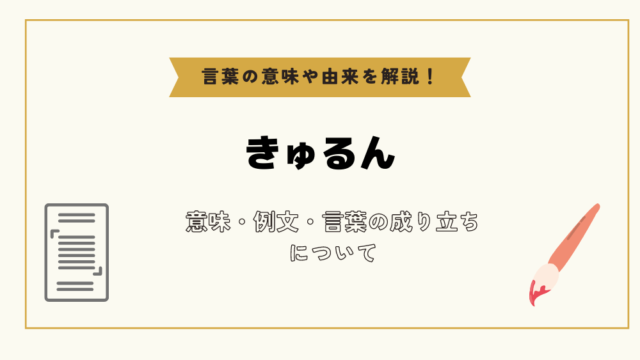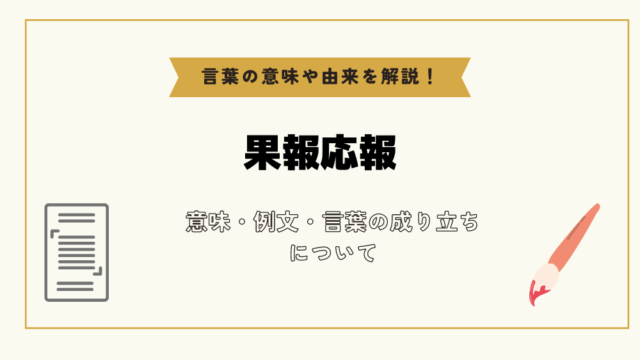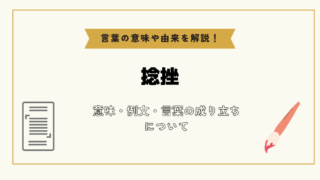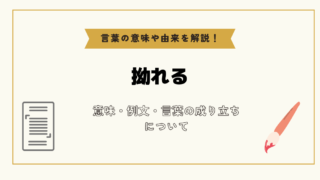Contents
「陶冶」という言葉の意味を解説!
陶冶(とうや)とは、人間の心や品性を鍛えるために、さまざまな手法や教育を通じて育てることを指します。
この言葉は、人間の成長や教育における重要なプロセスを表現しています。
「陶冶」という言葉の読み方はなんと読む?
「陶冶」という言葉は「とうや」と読みます。
この読み方は古くから伝わる日本語の読み方で、歴史や文化を感じさせる響きです。
「陶冶」という言葉の使い方や例文を解説!
「陶冶」という言葉は、人間の成長や教育に関連するさまざまな場面で使われます。
たとえば、子どもの教育においては、多様な経験を通じて情操や道徳性を陶冶することが重要です。
また、職業や芸術などのスキルや才能を磨くためにも、日々の努力や鍛錬が必要です。
例文:
– 「彼女は音楽の才能を陶冶するために、毎日練習に励んでいます。
」。
– 「陶冶された心を持った人は、他者の感情に寄り添った行動ができるようになります。
」。
「陶冶」という言葉の成り立ちや由来について解説
「陶冶」という言葉は古くから日本に存在し、元々は後漢時代の中国から伝わった漢字「陶」(こー)と「冶」(や)から派生しています。
漢字の「陶」は土器を作ることを意味し、「冶」は金属を加工することを意味します。
ここから転じて、人間の心や品性を作り上げるために、さまざまな教育や修行をすることを指すようになったのです。
「陶冶」という言葉の歴史
「陶冶」という言葉は、日本の歴史や文化に深く根付いています。
古くは「陶板」という、和歌や漢詩を刻んだ板を作る職人たちを指す言葉として使われていました。
また、平安時代には貴族の教育方法や風習においても重要視され、心の教育を行うための学問や修行が行われていました。
現代でも、「陶冶」という言葉は人間の成長や教育に関連する概念として広く使われています。
「陶冶」という言葉についてまとめ
「陶冶」は、人間の成長や教育における重要なプロセスを表現する言葉です。
さまざまな手法や教育を通じて人間の心や品性を鍛え、より素晴らしい人格を培うことを意味します。
日本の歴史や文化に深く根付いた言葉であり、現代でもその重要性が認識されています。