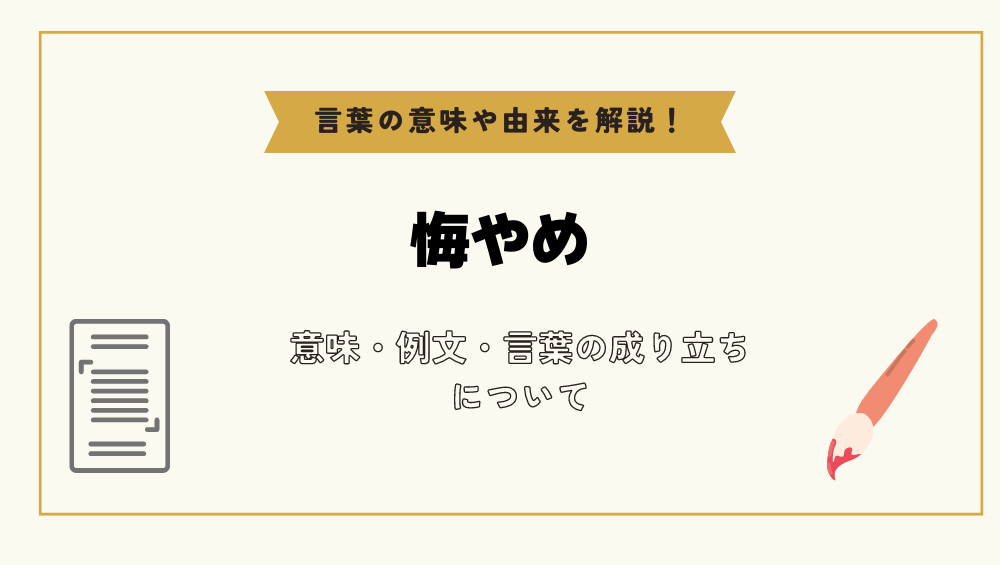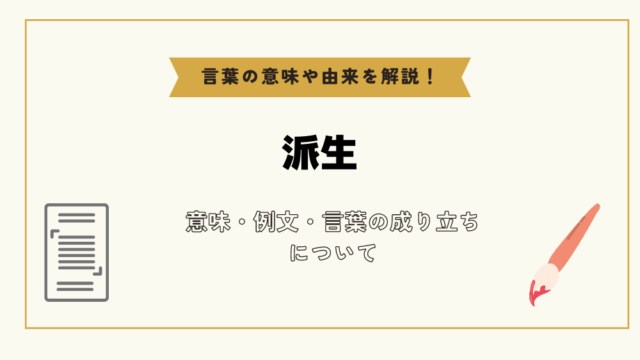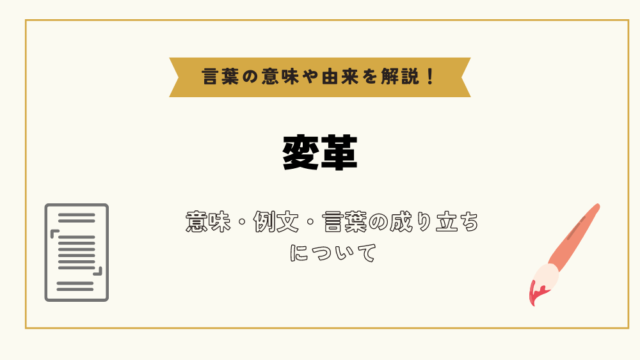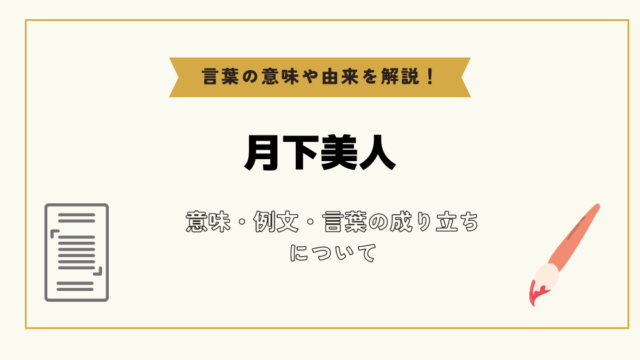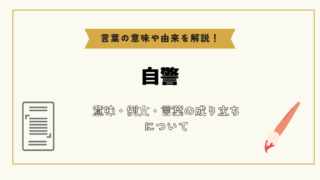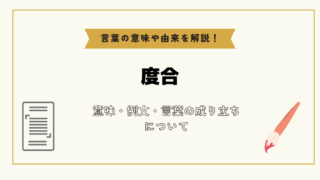Contents
「悔やめ」という言葉の意味を解説!
悔やめ(くやめ)とは、後悔や自責の念を持つことを表す言葉です。
「悔やむ」とも書きます。
自分の行いや選択に対して後悔の念を抱くときに使われ、「後悔する」「反省する」といった意味合いがあります。
人々の心の中で、悔やめの念は時にとても強くなります。
それは、自分自身への反省や過ちを認めることで、成長や改善につながる貴重な感情なのです。
「悔やめ」という言葉の読み方はなんと読む?
「悔やめ」という言葉は、日本語の発音規則に従った読み方をすると「くやめ」となります。
読み方は非常にシンプルで、一つずつの音を正確に発音することがポイントです。
悔やめという言葉を使うときは、自信を持って正しく読んでみましょう。
「悔やめ」という言葉の使い方や例文を解説!
「悔やめ」という言葉は、日常会話や文章で幅広く使用されます。
例えば、過去の自分の行動や選択に関して後悔の念を抱く場合に使うことがあります。
「あの時、もっと頑張っていれば良かった」と感じたり、「もう少し考えてから行動すべきだった」と反省の念を抱くときにも使えます。
例えば、「勉強を怠った結果、悔やめた」といった具体的な使い方です。
「悔やめ」という言葉の成り立ちや由来について解説
「悔やめ」という言葉は、江戸時代から使われていたとされています。
言葉の由来は古く、元々は「悔い」(くい)という言葉に「め」という助動詞が付いた形でした。
「悔い」は「後悔すること」という意味で、それに助動詞の「め」が加わることで動詞として使われるようになったのです。
「悔やめ」という言葉の歴史
「悔やめ」という言葉の歴史は古く、日本の古典文学や仏教の教えの中でも頻繁に使用されてきました。
古代から現代に至るまで、人々は自身の行動や選択に対して後悔や反省の念を抱くことがありました。
そのため、「悔やめ」という言葉も広く使われるようになり、現在の意味や使い方が定着したのです。
「悔やめ」という言葉についてまとめ
「悔やめ」という言葉は、後悔や自責の念を表す言葉です。
自分自身への反省や過ちを認めるという意味合いがあります。
日本語の発音規則に従えば「くやめ」と読みます。
日常会話や文章で広く使用され、過去の自分の行動や選択に対して後悔の念を抱くときに使われます。
由来は古く、江戸時代から存在していました。
現在も人々の心の中で重要な感情を表す言葉として使われ続けています。