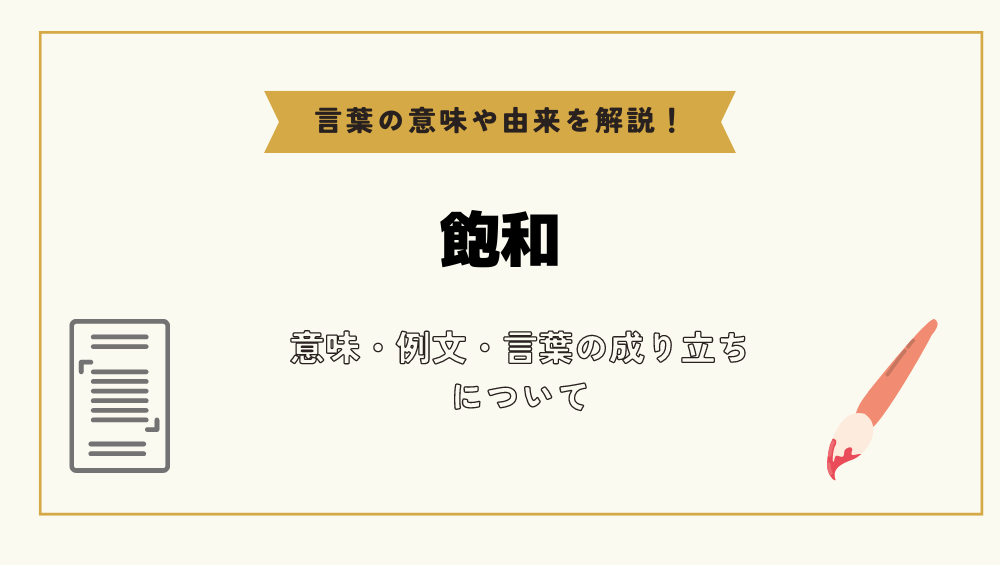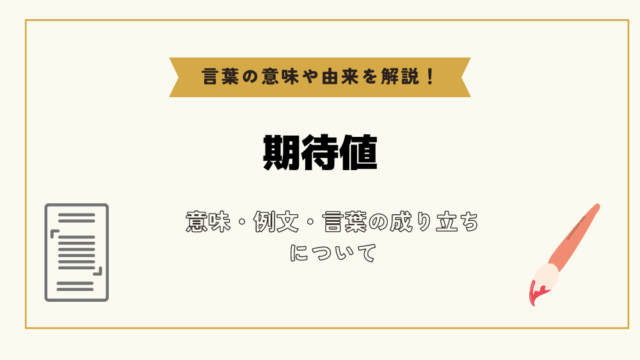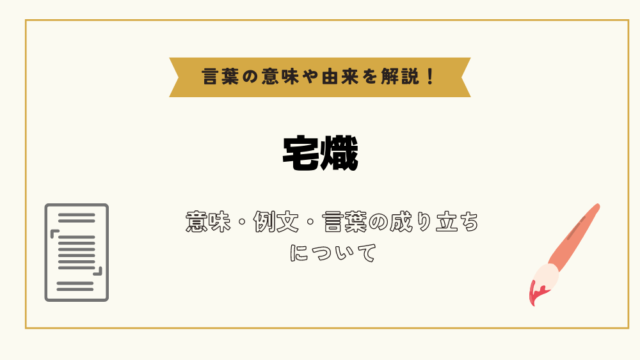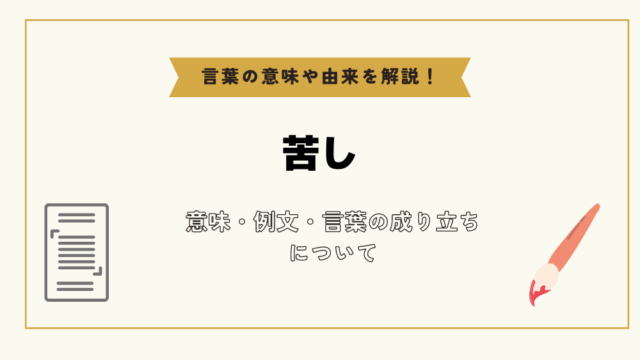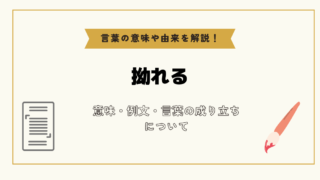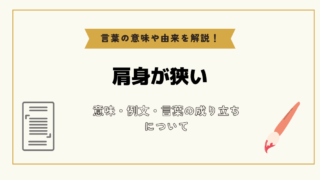Contents
「飽和」という言葉の意味を解説!
「飽和」という言葉は、ある物質が最大限に満たされている状態や、限界まで進んだ状態を表します。
何かが「飽和状態」となると、それ以上何かを加えたり進めたりすることができなくなります。
水が容器いっぱいになって流れ出すように、ある物質が一定の量や度まで達した時、それは「飽和」しています。
「飽和」の読み方はなんと読む?
「飽和」の読み方は、「ほうわ」と読みます。
「ほうわ」とは言いませんが、知らない人は驚くかもしれませんね。
日本の言葉には、いくつもの読み方がありますから、人名や地名などを覚えるのも大変ですよね。
「飽和」という言葉の使い方や例文を解説!
「飽和」という言葉は、科学や経済、心理学の分野など、さまざまな場面で使われます。
例えば、経済の話では「市場が飽和状態になる」と表現され、需要と供給のバランスが取れている状態を指します。
また、気分がすっきりしないときには、「この仕事にはもう飽和した」と言えば、その仕事に対する飽きや疲れを表現できます。
「飽和」という言葉の成り立ちや由来について解説
「飽和」という言葉は、古典中国語の「饕餮(とうてつ)」という言葉に由来しています。
元々は食欲や食事の満足感を表す言葉でしたが、後に物質や状態にも用いられるようになりました。
日本語に取り入れられた際に、正確な意味が変化したり、使われ方が広がったりしました。
「飽和」という言葉の歴史
「飽和」という言葉は、古くから日本語に存在していました。
しかし、その意味や使い方は時代とともに変化してきました。
特に近代以降の産業革命や科学技術の進展により、さまざまな分野で「飽和」という概念が重要な役割を果たすようになりました。
現代では、私たちの生活の中でも「飽和」に関わる概念が多く存在しています。
「飽和」という言葉についてまとめ
「飽和」という言葉は、物質や状態が最大限に満たされた状態を表す言葉です。
ある程度の量や度に達すると、それ以上は増えたり進んだりすることができません。
経済や科学、日常生活のさまざまな場面で使われる言葉であり、その成り立ちや由来も興味深いものです。