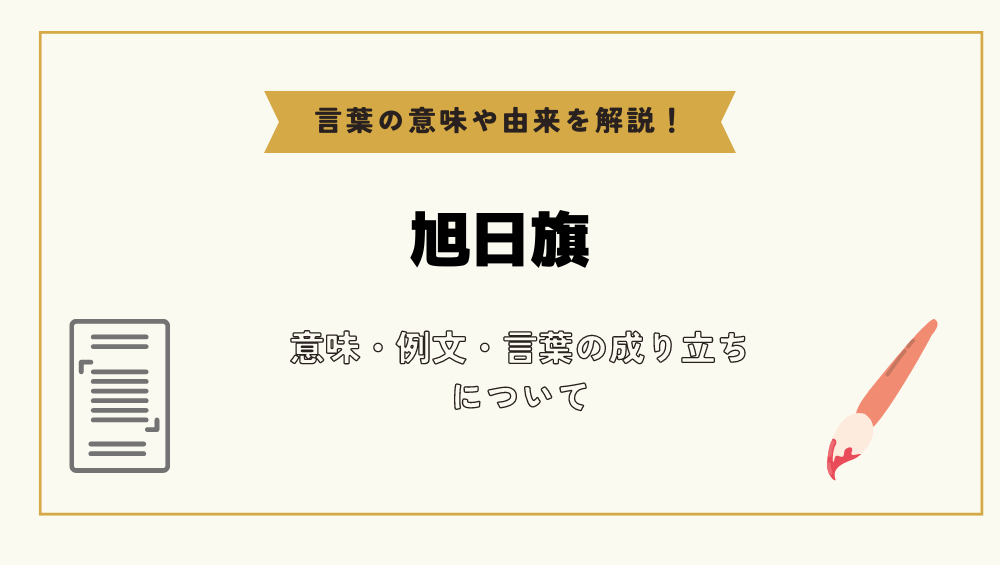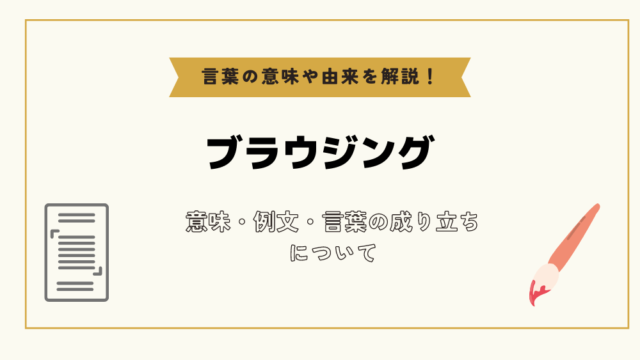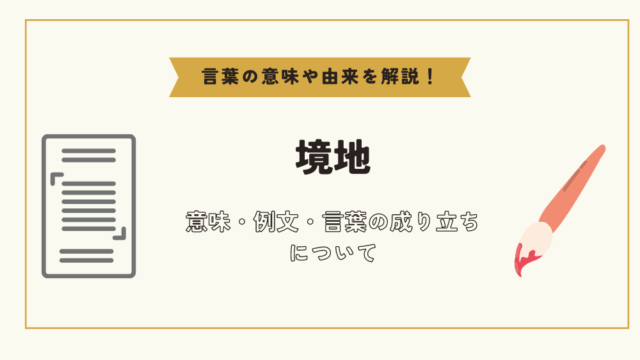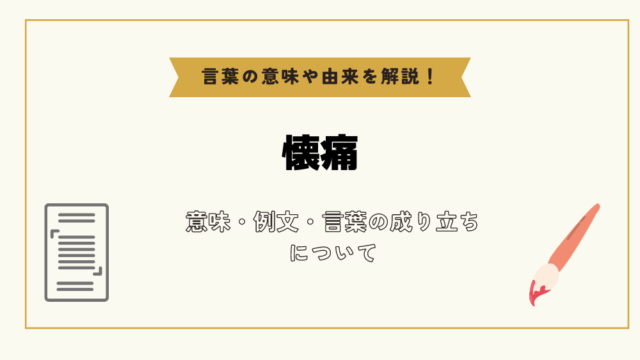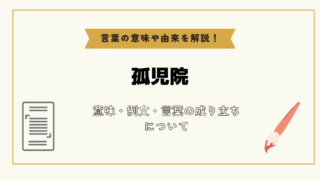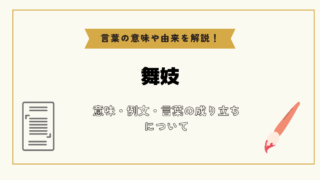Contents
「旭日旗」という言葉の意味を解説!
「旭日旗」という言葉は、日本の国旗である「日章旗(にっしょうき)」の別称として使われています。
日本の国旗は、赤い太陽の円が白い地に描かれたデザインで、その形状がまるで旭日のようだということから「旭日旗」と呼ばれるようになりました。
「旭日旗」の読み方はなんと読む?
「旭日旗」は、「きょくじつき」と読みます。
日本語の起源である漢字を用いた読み方ですが、普段はあまり使われる機会はありません。
そのため、ほとんどの人は「にっしょうき」という呼び方をすることが一般的です。
「旭日旗」という言葉の使い方や例文を解説!
「旭日旗」は、主に日本の国旗を指す言葉として使われます。
例えば、「彼は旭日旗を掲げてパレードに参加した」というように、国を表す象徴としての意味合いで使われることが多いです。
「旭日旗」という言葉の成り立ちや由来について解説
「旭日旗」という言葉は、昔から日本の国旗を指す言葉として使われてきました。
日本の国旗は、1945年まで日本帝国の国旗として使用されていたものであり、太陽の輪を象徴したデザインとなっています。
「旭日旗」という言葉の歴史
「旭日旗」という言葉の歴史は古く、日本の国旗としての起源は明確ではありませんが、平安時代の頃から太陽のシンボルを使った旗が存在していたことが記録に残っています。
その後、江戸時代になり現在の形状に近いデザインが定着し、明治時代以降、日本の国旗として広く認知されるようになりました。
「旭日旗」という言葉についてまとめ
「旭日旗」という言葉は、日本の国旗である「日章旗」の別称として使われます。
その起源は古く、日本の歴史と深く関わっています。
旭日旗は、日本の国の象徴として、多くの人々に親しまれています。