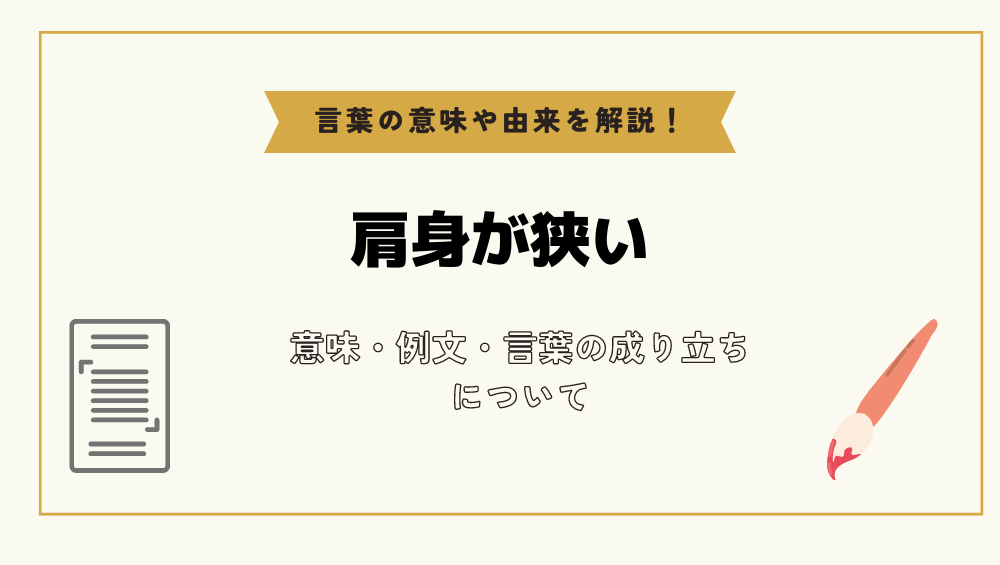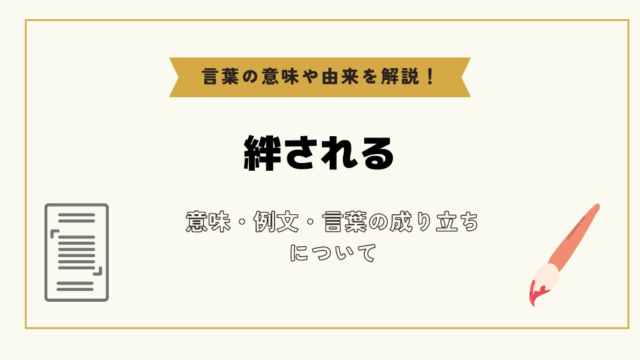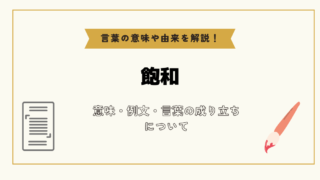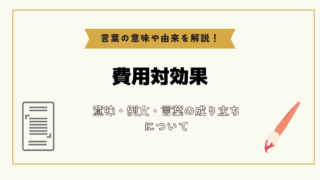Contents
「肩身が狭い」という言葉の意味を解説!
「肩身が狭い」という表現は、自分自身の立場や地位が低く、他の人たちから見下されたり、嫌われたりすることを指します。
日本語の表現であり、肩身が狭い状況に置かれると、不快感や居心地の悪さを感じることがよくあります。
肩身が狭い状態は、自己評価が低いと感じることが多く、他人の目を意識しやすくなります。
このような状況では、自己主張ができずにしゃべる言葉や態度が制限されてしまい、自信を喪失してしまうこともあります。
「肩身が狭い」の読み方はなんと読む?
「肩身が狭い」は、かたみがせまいと読みます。
かたみがせまいという表現は、落ち込んだり、気後れしたりすることを表しています。
また、人との関係性から生まれる不安や心の中の葛藤を意味しています。
「肩身が狭い」という言葉の使い方や例文を解説!
「肩身が狭い」という表現は日常会話でよく使われます。
例えば、自分の失敗やミスを他の人に知られてしまったとき、「肩身が狭い」と感じるのかもしれません。
また、上司や目上の人からの過度な指摘や批判を受けたときにも、「肩身が狭い」と感じることがあります。
例文としては、「先輩たちとの会議で自分の考えを発言しようとしたら、全員に否定されてしまって肩身が狭かったです」と表現することができます。
「肩身が狭い」という言葉の成り立ちや由来について解説
「肩身が狭い」という言葉は、江戸時代から使われていたとされています。
人間の体の中で最も広い肩が狭く感じられる状況になることから、「肩身が(他の部分に比べて)狭い」と表現されるようになりました。
「肩身が狭い」という言葉の歴史
「肩身が狭い」という表現は、江戸時代の書籍や文学作品にも見ることができます。
その頃から人々は「肩身が狭くなる」という不快感や恐怖を経験し、表現方法として定着しました。
現代でも、この表現は広く使われています。
「肩身が狭い」という言葉についてまとめ
「肩身が狭い」という言葉は、自分自身の立場や地位が低くなり、他の人たちから嫌われたり見下されたりする状況を表現する言葉です。
日本語の表現であり、肩身が狭いと感じると自己評価が低下し、不快感や自信喪失を招くことがあります。
その成り立ちや由来は江戸時代にまでさかのぼり、現代でも広く使用されています。