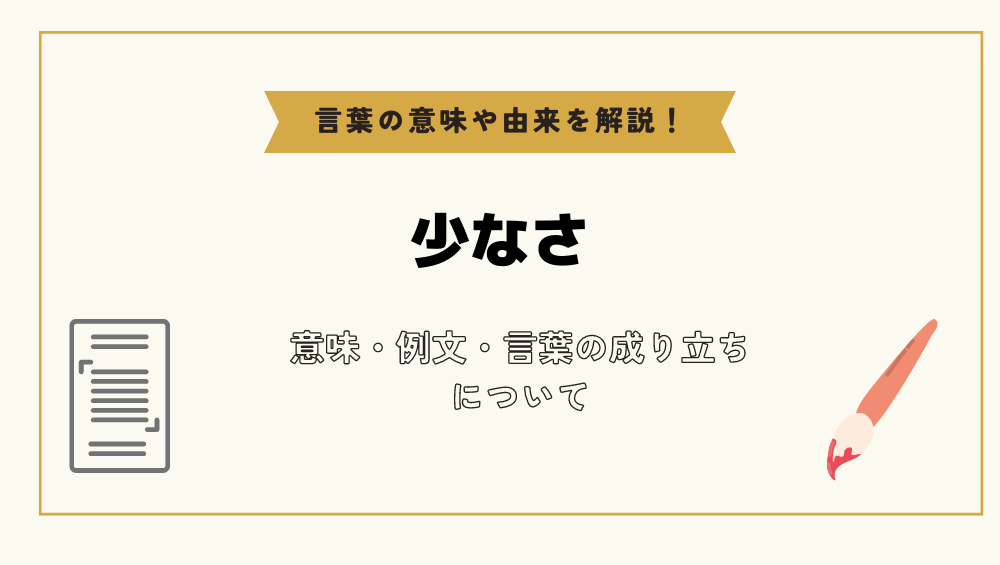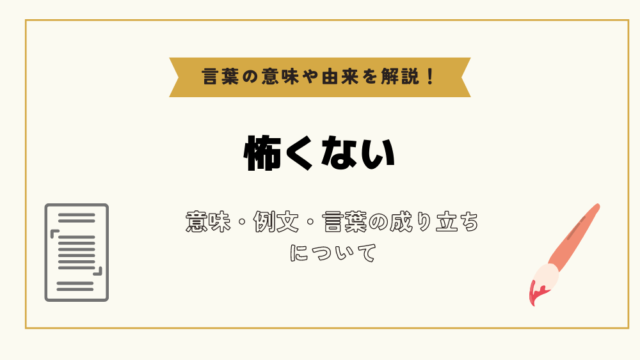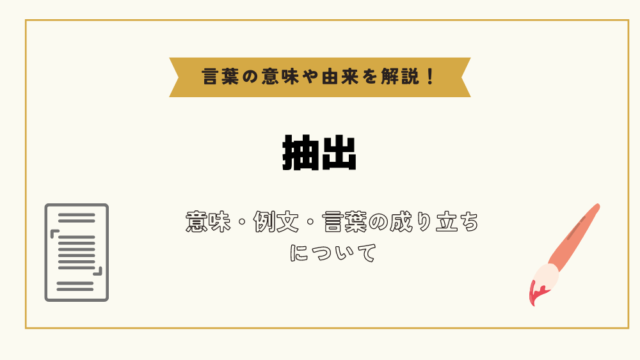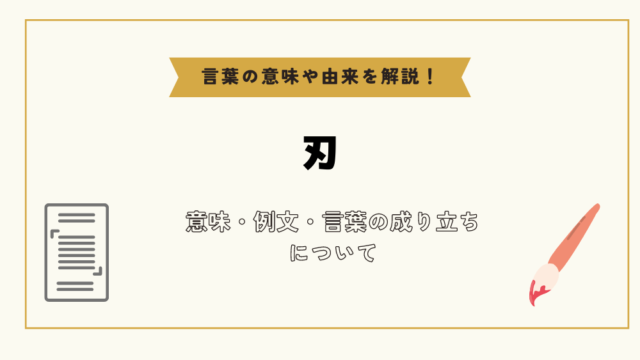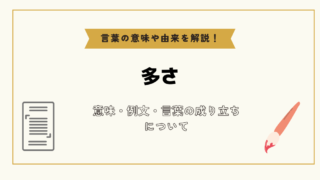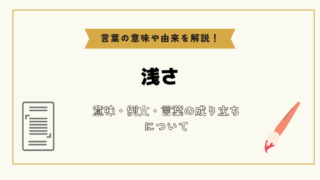Contents
「少なさ」という言葉の意味を解説!
「少なさ」という言葉は、物事の数量や程度が少ないことを表現する形容詞です。
何かが不足している状態や、期待や要求に対して満たされない状態を指すことがあります。
例えば、食べ物が少ない、お金が少ないといった具体的な状況や、時間が少ない、選択肢が少ないといった抽象的な状態も、「少なさ」という言葉で表現することができます。
「少なさ」という言葉の読み方はなんと読む?
「少なさ」という言葉の正しい読み方は、「すくなさ」となります。
日本語の発音ルールに従って、濁音化した「す」の音が「し」の音に変わり、後ろの「く」は「か」の音に変わります。
より自然な発音を心がけると良いでしょう。
「少なさ」という言葉の使い方や例文を解説!
「少なさ」は、主に数量や程度が不足している状態を表現するために使用されます。
例えば、「彼の給料は少なさすぎる」という文では、彼の給料が十分ではなく、不満足であることを表しています。
他にも、「商品のバリエーションが少ない」といった文では、商品の種類が少なく、選択肢が限られていることを示しています。
また、「時間の制約のため、話をする時間が少なさそうです」といった文では、制約された時間の中で話し合うことが必要であることや、十分な時間がないことを意味しています。
「少なさ」という言葉の成り立ちや由来について解説
「少なさ」という言葉は、古代の日本語に由来します。
元々は「少」を「さ」という語末音に変えて表現する方法であり、現代の日本語では主に形容詞として使用されます。
日本語の文法や表現方法の変遷の中で、現在の形に近づいてきました。
日本語の単語や表現の由来を知ることで、より深い理解ができるでしょう。
「少なさ」という言葉の歴史
「少なさ」という言葉は、古くから日本語に存在しています。
古代の文献や歌などにも使われており、日本語の魅力や特徴の一つとも言えます。
時代が変わっても、人々の生活や思考の中で「少なさ」という感覚は共通して存在しているようです。
言葉の歴史を振り返ることで、現代の言葉の使い方や意味にも新たな発見が得られるかもしれません。
「少なさ」という言葉についてまとめ
「少なさ」という言葉は、物事の数量や程度が不足している状態を表現する形容詞です。
日本語の発音ルールに従って、「すくなさ」と読みます。
この言葉は、さまざまな場面で使用され、人々の感受性や要求に関わっています。
古代の日本語に由来し、現代の言葉としても使われ続けています。
日本語の魅力や歴史とも深いつながりがあります。