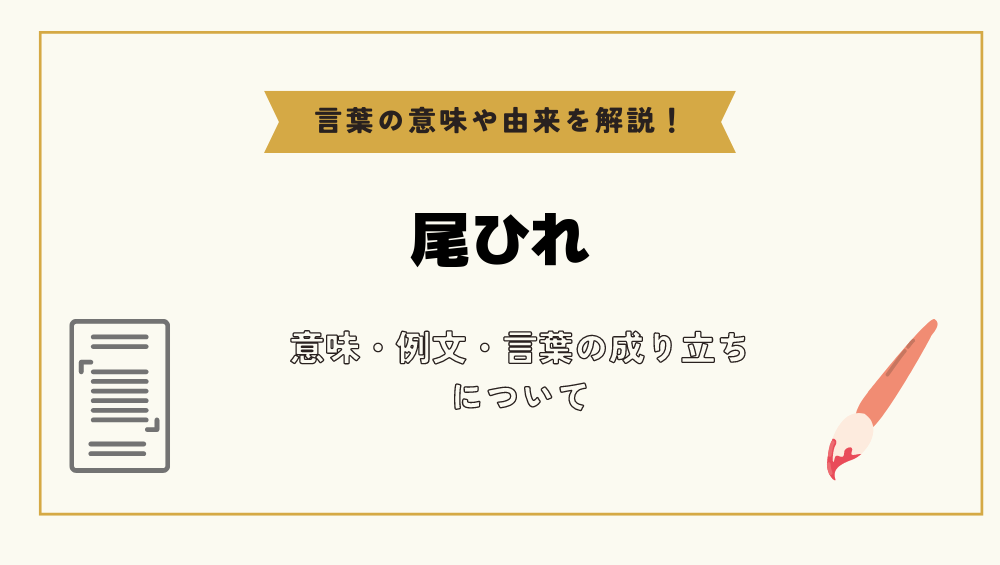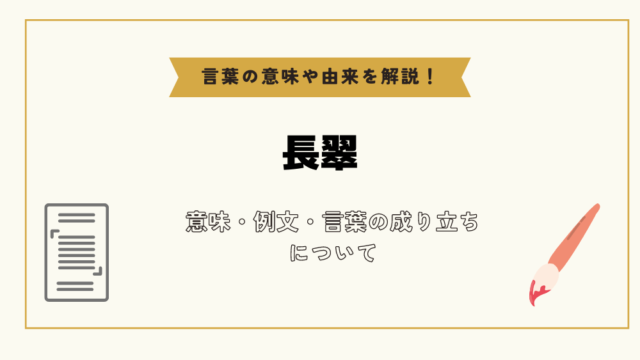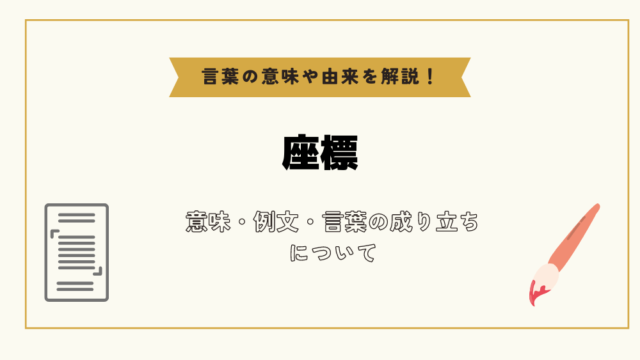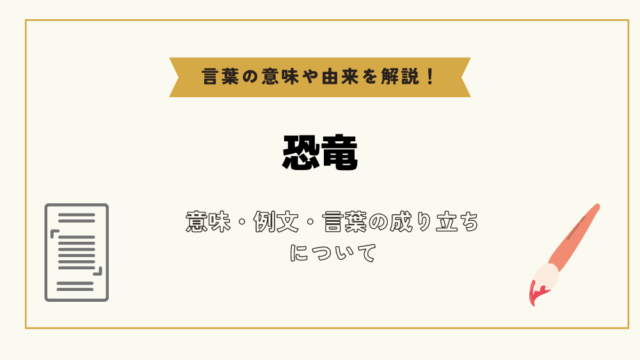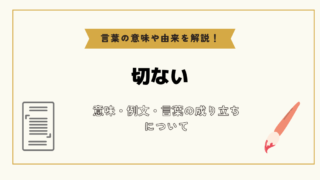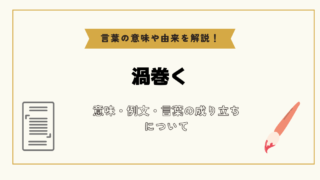Contents
「尾ひれ」という言葉の意味を解説!
「尾ひれ」という言葉は、ある事柄や物事の終わりの部分や余談のことを指しています。
何かの結末や余白に付随する要素を指すことが多く、尾状の形状を持つ部分を表現しています。
「尾ひれ」という言葉の読み方はなんと読む?
「尾ひれ」という言葉は、おびれと読みます。
最初の「尾」は「お」と読みますし、2つ目の「ひれ」は「びれ」と読みます。
日本語の読み方によくある特徴の一つであり、親しみやすさを感じられる読み方です。
「尾ひれ」という言葉の使い方や例文を解説!
「尾ひれ」という言葉は、文章や話し言葉の中でよく使用されます。
例えば、小説や物語の終わりにおいて、メインストーリーに関係のないエピソードや余談を「尾ひれ」と呼ぶことがあります。
また、日常会話でも長話の最後につけ加える要素や、話の結論に関係のない追加情報を「尾ひれ」として使うことがあります。
「尾ひれ」という言葉の成り立ちや由来について解説
「尾ひれ」という言葉は、「尾」と「ひれ」という2つの漢字文字によって成り立っています。
漢字の「尾」は、動物の胴体の末端や、物事の終わりを表す意味があります。
一方、「ひれ」は、魚や一部の生物が持つ形状のことを指します。
この二つの言葉を組み合わせたものが、「尾ひれ」となった結果です。
「尾ひれ」という言葉の歴史
「尾ひれ」という言葉の歴史は、古くから使われてきたと言われています。
もともとは、動物の尾と魚のひれという具体的な形状を指す言葉でしたが、やがて比喩的な意味合いが加わり、「終わりの部分」という意味でも使われるようになりました。
現代では、文章や会話の中で幅広く使われている言葉となっています。
「尾ひれ」という言葉についてまとめ
「尾ひれ」という言葉は、ある事柄や物事の終わりの部分や余談を指しています。
読み方は「おびれ」となります。
文章や話し言葉の中でよく使われ、小説や物語の終わりに付け加えられる部分のことを指すことが多いです。
成り立ちや由来については、動物の尾や魚のひれという具体的な形状から発展した言葉です。
歴史は古く、比喩的な意味で使われるようになった経緯を持っています。