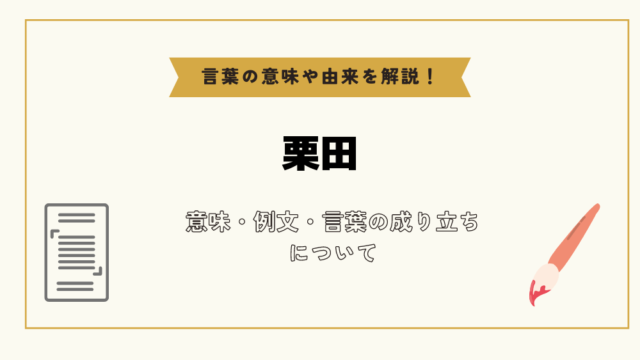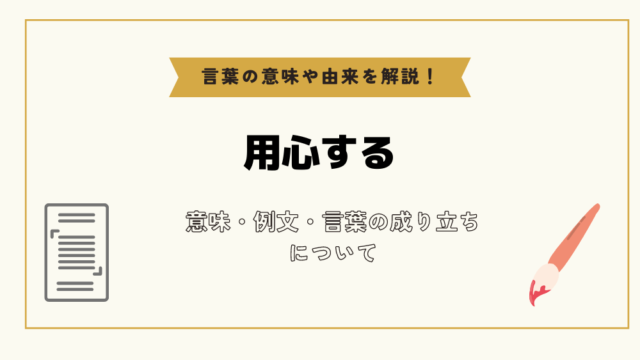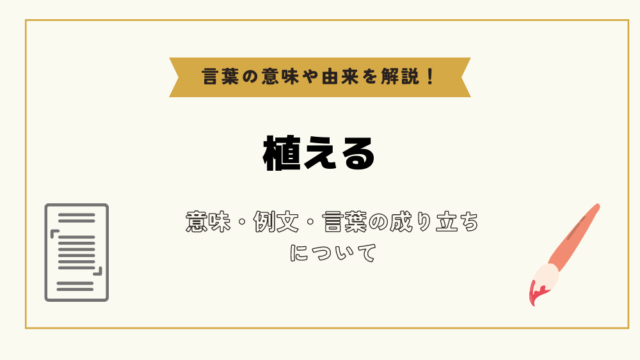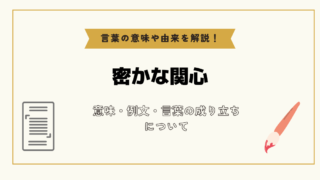Contents
「門首払い」という言葉の意味を解説!
「門首払い」とは、相手を完全に拒絶し、話さずに帰らせることを意味する言葉です。
「門首」とは家の玄関や門のことであり、「払い」とは帰らせることを指します。
つまり、「門首払い」とは、相手を冷たくあしらって帰らせることを表現しています。
この言葉は、注意や請求などを一蹴する場面で使用されることが一般的です。
例えば、訪ねてきたセールスマンが断固として商品を買わないと言った場合、店主は冷たく門前でそのセールスマンを帰らせることがあります。これが「門首払い」の具体的なイメージです。
「門首払い」の読み方はなんと読む?
「門首払い」は、「もんしゅふっさい」と読みます。
読み方は比較的シンプルな音訳であり、日本語に馴染みやすいものと言えます。
今後もこの読み方が一般的に使用されると思われます。
「門首払い」という言葉の使い方や例文を解説!
「門首払い」という言葉は、相手を冷たくあしらって帰らせる場面で使用されます。
例えば、営業マンが来訪した際、受付の社員が冷たく扱い、断固として商品を購入しないと伝える場合に使います。
「門首払い」は、相手の要求や申し出を一蹴し、拒絶することを表現する強いフレーズです。
例文:
– 「彼は門首払いされて、ショックを受けたようだ。
」。
– 「彼の要求は即座に門首払いされ、話し合いの余地はなかった。
」。
「門首払い」という言葉の成り立ちや由来について解説
「門首払い」という言葉の成り立ちは、日本の古い言葉に由来しています。
古来、家の門の前で相手を拒絶する光景が見られたため、「門首払い」という言葉が生まれたと考えられています。
現代の用法としては、商談や交渉の場面での拒否の意味合いが強くなっています。
「門首払い」という言葉の歴史
「門首払い」という言葉の歴史は、江戸時代にさかのぼります。
当時、門前での商売が多かったため、店主が来た客を拒絶する場面がしばしば見られました。
その様子から「門首払い」という表現が生まれ、広まっていきました。
現代でも「門首払い」という言葉は使用され続けており、拒否や冷たい対応を表す一つの言葉として広く認知されています。
「門首払い」という言葉についてまとめ
「門首払い」という言葉は、相手を冷たくあしらって帰らせることを表現する言葉です。
扱いの悪さや無視、完全な拒絶を意味します。
「門首払い」の語源は古く、江戸時代から使われていました。
現代でも一定の使われ方を保っており、相手の要求や申し出を断固として退けるときに適切に使用することができます。