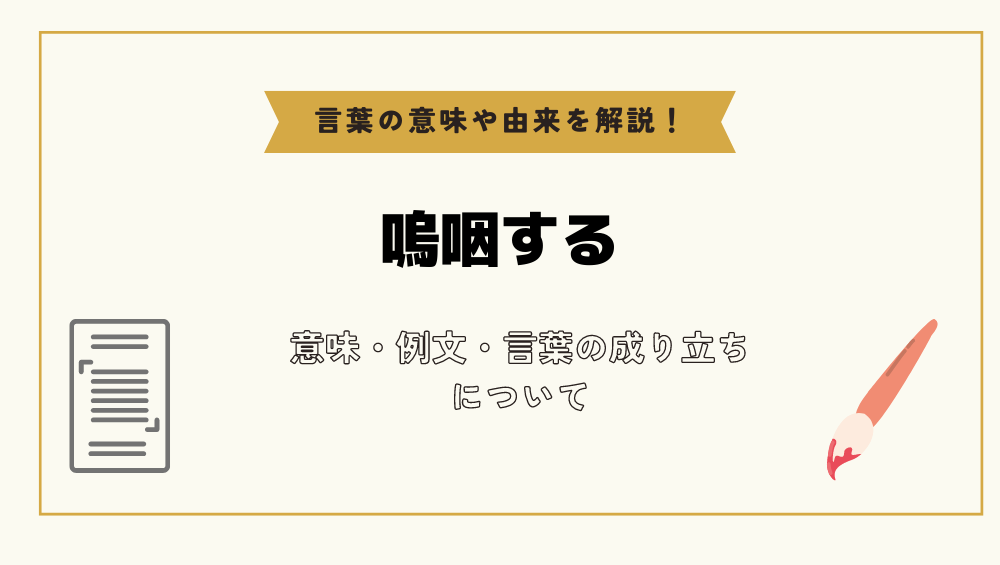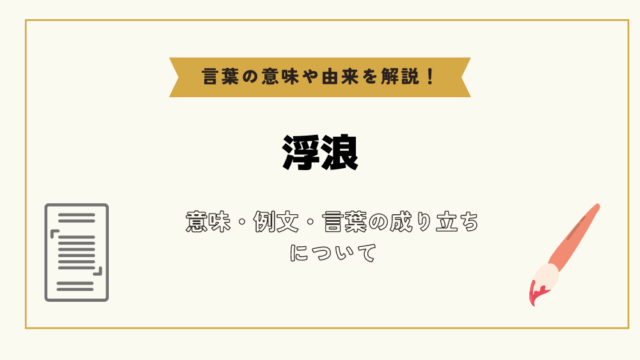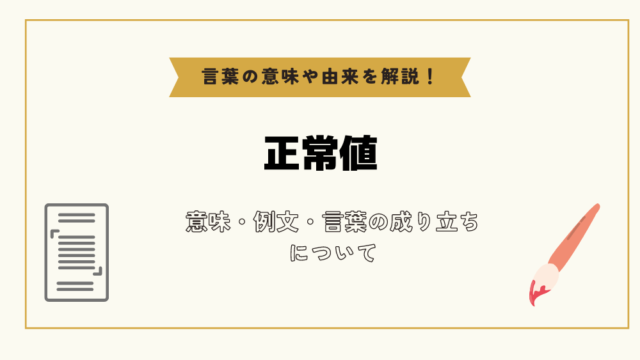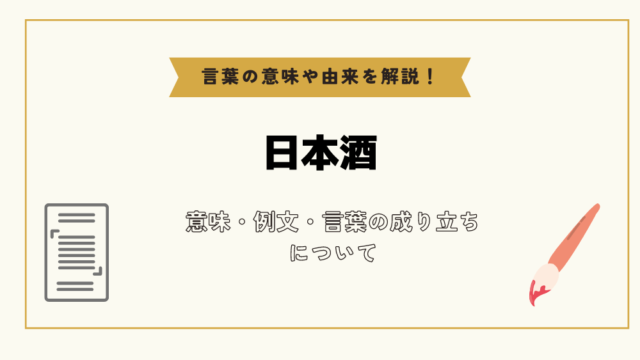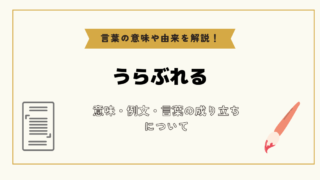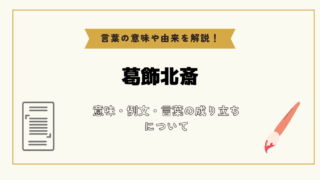Contents
「嗚咽する」という言葉の意味を解説!
「嗚咽する」とは、悲しみや苦しみ、驚きなどで声を絞って泣くことを指します。
目に涙が溢れ、声を上げて泣きながら胸の中の感情を表現する様子を表します。
この言葉には、感情の激しさや痛みが伴っていることが含まれています。
現代では、嗚咽する場面は映画やドラマでよく見られます。主人公が深い悲しみに包まれたり、喜びや感動で涙を流す場面などで使われます。嗚咽することは、感情が非常に強くなっている証拠であり、人間らしさや人間の心の豊かさを表現する手段としても使われます。
「嗚咽する」の読み方はなんと読む?
「嗚咽する」は、「おうえんする」と読みます。
日本語の音読みでは「オウエン」になります。
この言葉は中国語由来の言葉であり、漢字の読み方によって「おうえんする」という意味が表現されています。
「嗚咽する」という言葉の使い方や例文を解説!
「嗚咽する」は、感情が非常に激しい場面で使用される言葉です。
以下に使い方や例文を解説します。
例文1:彼女は悲しみに包まれ、声を絞って嗚咽しました。
例文2:その映画の感動的なシーンで、多くの人々が嗚咽していました。
例文3:彼は喜びと感謝の気持ちで嗚咽し、涙が頬を伝いました。
このように、「嗚咽する」は感情が極限まで高まった状態で使用される言葉です。人の心の奥底にある感情が爆発的に表れる瞬間を表します。
「嗚咽する」という言葉の成り立ちや由来について解説
「嗚咽する」という言葉は、中国語の「哀吟」から派生してきました。
その後、日本に伝わり、「嗚咽する」という表現になりました。
漢字の「嗚」と「咽」は、それぞれ「悲しい声を上げる」と「声を詰まらせる」という意味を持っています。
この言葉が日本語において広まった背景には、文学や演劇の影響が大きいとされています。特に、歌舞伎や能などの伝統的な演劇では、感情の高まりを豪快に表現することが重要視され、その表現手段として「嗚咽する」という言葉が使われてきました。
「嗚咽する」という言葉の歴史
「嗚咽する」という言葉は、日本の歴史と文化の中で長い年月を経て発展してきました。
古代日本では、悲しみや苦しみを表現するために歌や詩が使われていましたが、中世以降、演劇や文学作品の中で「嗚咽する」という表現が用いられるようになりました。
江戸時代になると、歌舞伎や人形浄瑠璃などの芸能が大いに発展し、「嗚咽する」表現がより一層増えました。おおらかな感性や感受性が求められる江戸時代の人々は、嗚咽することによって感情の高まりを表現することを好みました。
「嗚咽する」という言葉についてまとめ
「嗚咽する」という言葉は、感情が非常に激しい場面で使用される言葉です。
古代から現代まで、日本の文化や芸能において重要な役割を果たしてきました。
この言葉は、人の内なる感情を表現する上で大変有効な言葉であり、感情の高まりを的確に伝えることができます。また、悲しみや苦しみ、喜びや感動といった激しい感情を表現するためにも頻繁に使われています。