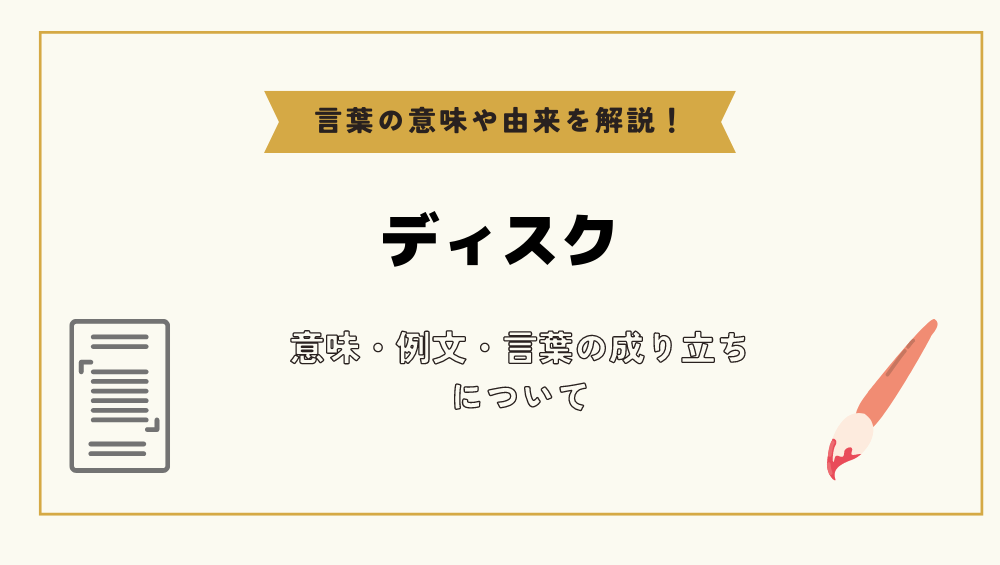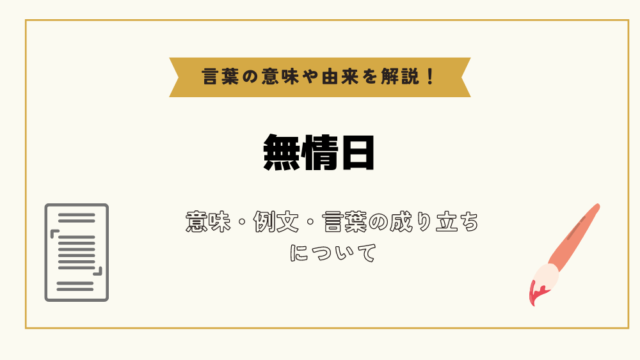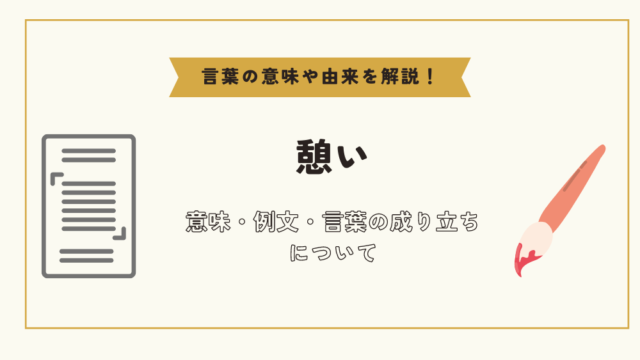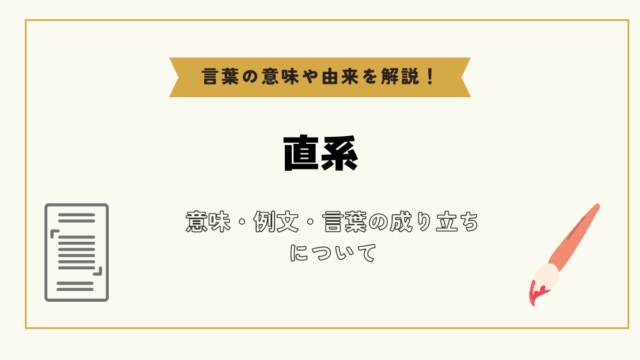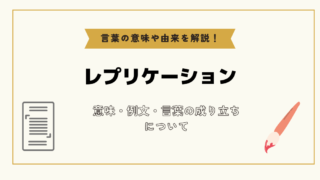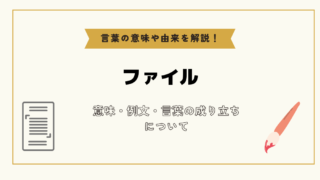Contents
「ディスク」という言葉の意味を解説!
ディスクという言葉は、情報を記録するための円盤状の媒体を指します。
主にコンピュータのデータ保存や音楽再生などに使用されます。
ディスクは表面に複数の溝があり、そこにデータが記録されています。
このデータは読み書きすることで情報をやり取りすることができます。
ディスクは非常に便利で、大量のデータを保存することができます。
また、ディスクは再利用が可能であるため、繰り返し使用することができます。
「ディスク」という言葉の読み方はなんと読む?
「ディスク」という言葉は、カタカナで表記されていますが、「でぃすく」と読みます。
英語の “disk” に由来する言葉ですが、日本語ではこのように読まれることが一般的です。
音の響きから非常に親しみやすく、なじみのある読み方となっています。
「ディスク」という言葉の使い方や例文を解説!
「ディスク」という言葉は、主にコンピュータや音楽の分野で使用されます。
たとえば、コンピュータのハードディスクやCD・DVDなどがそれにあたります。
また、データの保存やバックアップのためにディスクを使う、といった使い方もあります。
例えば、「昨日、大切なデータを外部ディスクにバックアップしました」というように使われます。
「ディスク」という言葉の成り立ちや由来について解説
「ディスク」という言葉は、英語の “disk” に由来しています。
英語の “disk” はラテン語の “discus” に由来し、円盤を意味します。
円盤状の媒体であるディスクが情報を記録するために使用されることから、この名前が付けられました。
「ディスク」という言葉の歴史
ディスクの始まりは、長い歴史を持っています。
最初のディスクは、1950年代に開発された磁気ディスク(ハードディスク)でした。
これはコンピュータのデータ保存に使用され、当時のコンピュータ技術の進歩に大いに貢献しました。
その後、1960年代には円盤状の光ディスクが登場し、音楽やビデオの再生に使用されるようになりました。
さらに、1970年代にはCD(コンパクトディスク)が開発され、音楽や映像ソフトの普及に大きな役割を果たしました。
「ディスク」という言葉についてまとめ
ディスクという言葉は、情報を記録するための円盤状の媒体を指します。
コンピュータのデータ保存や音楽再生など、さまざまな分野で活躍しています。
また、「ディスク」という言葉は親しみやすく、なじみがあります。
ディスクは便利な媒体であり、データの保存やバックアップに役立ちます。
ディスクの由来や歴史を知ることで、その重要性や普及の背景も理解できます。