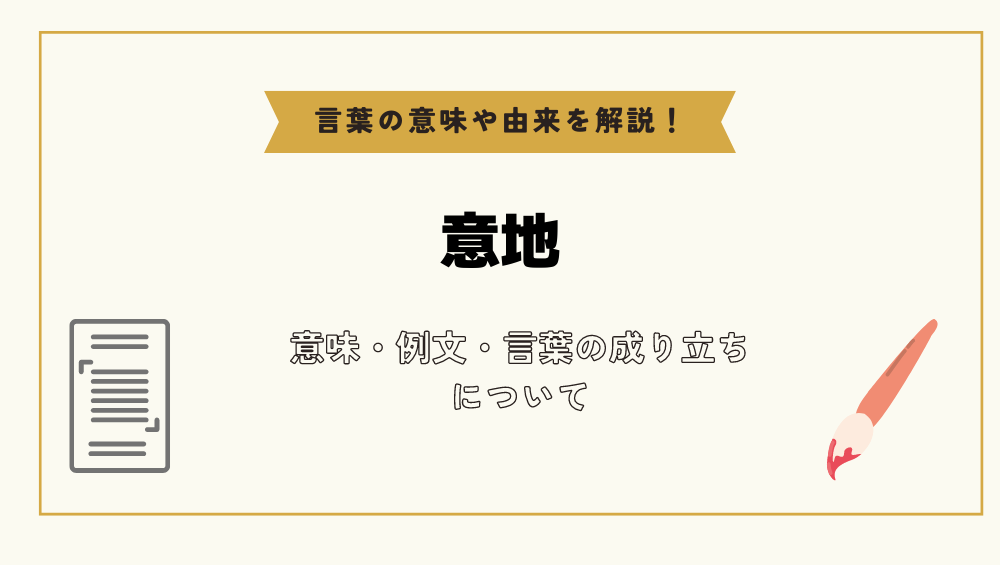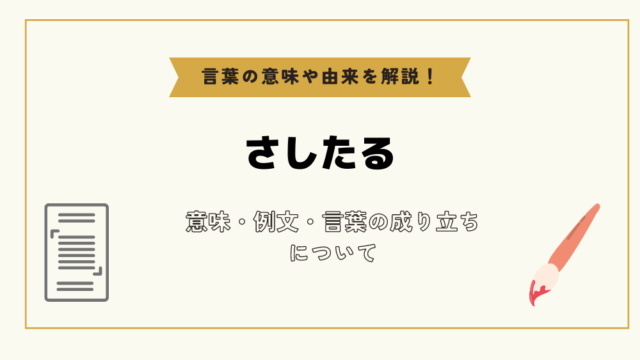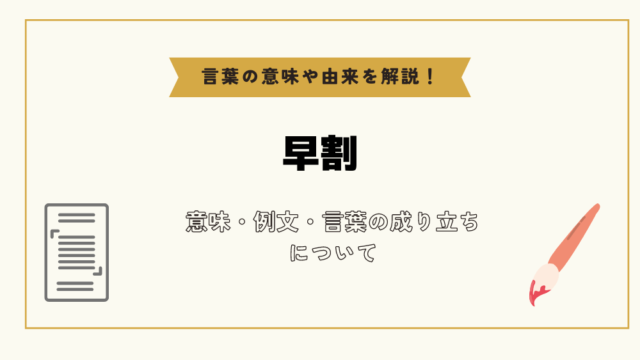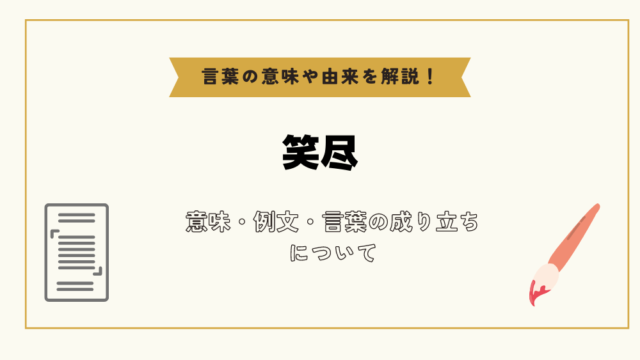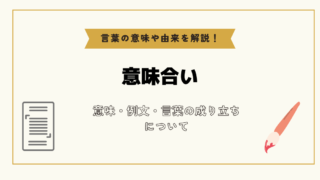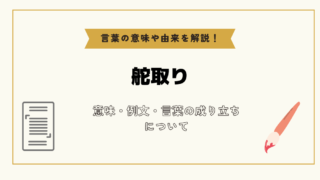Contents
「意地」という言葉の意味を解説!
「意地」という言葉は、強い意志や固い決意を持つことを表現する日本語です。
困難に立ち向かうために心に燃える熱い思いや、自分を貫くための強い信念を指す言葉として使われます。
意地を持つことは、少し頑固な一面もあるかもしれませんが、挫折や困難に負けずに最後まで諦めずに頑張る姿勢を表します。
そのため、「意地っ張り」という言葉が使われることもあります。
「意地」という言葉の読み方はなんと読む?
「意地」という言葉は、読み方は「いじ」となります。
これは、日本語の発音ルールに基づいています。
漢字で書かれた言葉の読み方は、常に個別に覚える必要がありますが、この場合は「いじ」と読むことで意味が通じます。
「意地」という言葉の使い方や例文を解説!
「意地」という言葉は、ある目的や目標を達成するために自分を奮い立たせる意志の強さを表現するのに使われます。
例えば、「彼は意地の張った性格で、どんな困難な状況でも最後まで頑張り抜く」というように使われることがあります。
また、「自分の間違いを認めずに意地を張る」という意味でも使われます。
「彼はいつも自分が正しいと思い込んでいて、誰の意見にも意地を張る」というような使い方です。
「意地」という言葉の成り立ちや由来について解説
「意地」という言葉の成り立ちは、平安時代から存在していたと言われています。
元々は「気の成るところ」という意味で使われていたとされており、気持ちや精神の力強さを表現する言葉として使われていました。
その後、江戸時代に入ると「負けず嫌いな性格」という意味合いが強くなり、現在の「意地」という言葉の使い方に繋がっていきました。
現代の日本語においても、強い意志やプライドを持つ人を表現する言葉として広く使われています。
「意地」という言葉の歴史
「意地」という言葉は、古くから使われている言葉です。
平安時代から存在しており、当時は「気の成るところ」という意味で使われていました。
江戸時代に入ると、「負けず嫌いな性格」という意味合いが強くなり、現在の使い方に繋がっていったのです。
また、歴史上の人物の中にも「意地の強さ」が評価された人物がいます。
例えば、戦国時代の豊臣秀吉や明治時代の西郷隆盛などは、厳しい状況や困難に立ち向かう際に意地を見せ、成功を収めたことで知られています。
「意地」という言葉についてまとめ
「意地」という言葉は、強い意志や固い決意を持つことを表現する日本語です。
頑固な一面もあるかもしれませんが、挫折や困難に負けずに最後まで諦めずに頑張る姿勢を意味します。
読み方は「いじ」となり、古くから使われている言葉です。
歴史上の人物や現代の人々においても、「意地の強さ」は評価されることがあります。