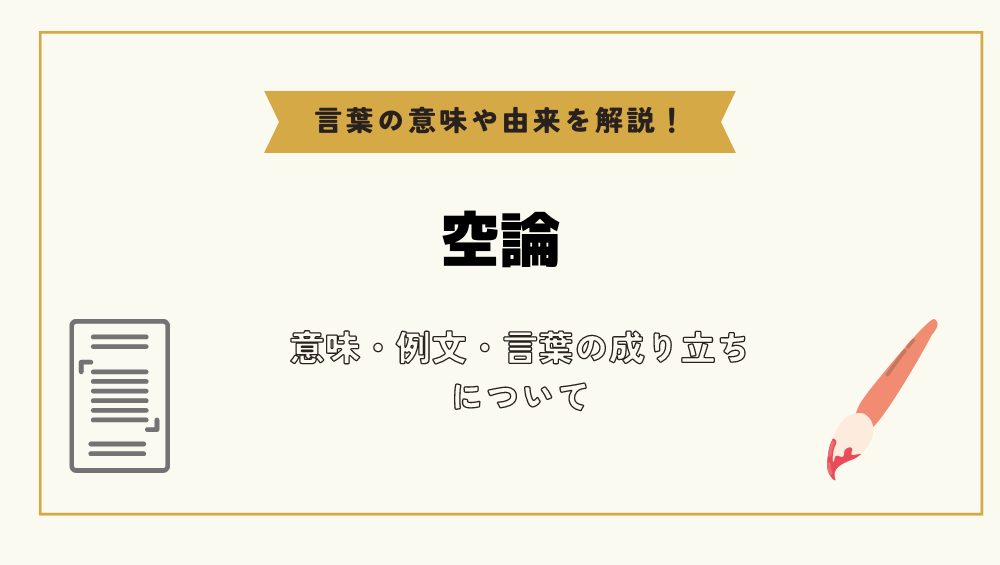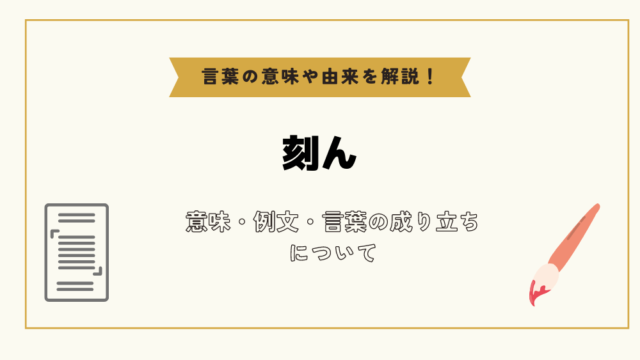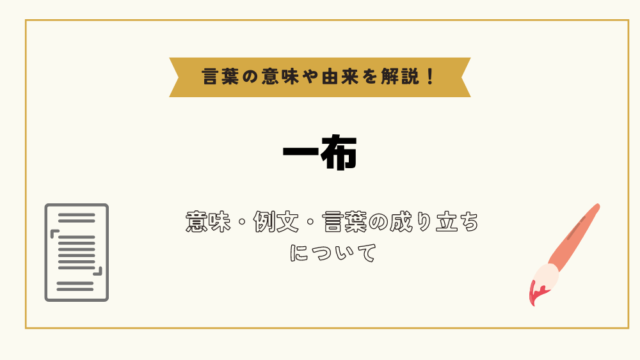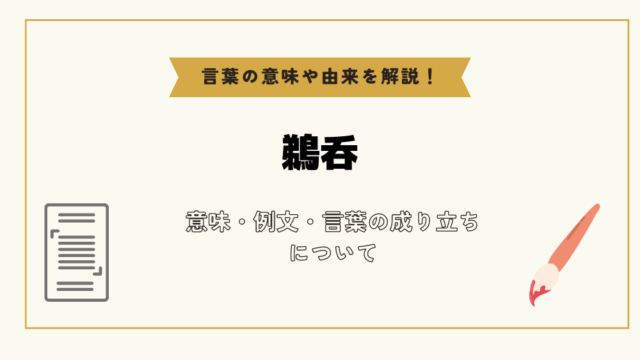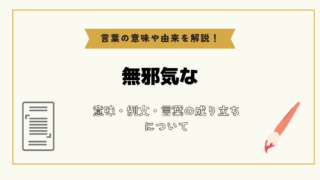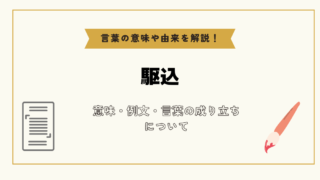Contents
「空論」という言葉の意味を解説!
「空論」という言葉は、口先だけで中身が無い議論や説明を指す言葉です。
具体的な内容や根拠がなく、理論的な枠組みよりも形式的な議論に偏っていることが特徴です。
空論は実際の問題解決や行動には役立ちませんが、場合によっては思考を広げたり、アイデアを発展させるために役立つこともあります。
「空論」という言葉の読み方はなんと読む?
「空論」は、「くうろん」と読みます。
日本語の言葉なので、日本語の音読みで読むことができます。
難しい読み方ではないため、たくさんの人が使っています。
「空論」という言葉の使い方や例文を解説!
「空論」は、話や議論の中で、具体的な裏付けや根拠がないために使われることが多いです。
たとえば、「具体的なプランや戦略がなければ、そのアイデアはただの空論に過ぎない」といった風に使うことができます。
また、「彼の発言は空論だけで、現実的な解決策を提案していない」というようにも使われます。
「空論」という言葉の成り立ちや由来について解説
「空論」という言葉は、元々は中国の儒教の思想に由来しています。
儒家の教えでは、理論的な議論や構想を立てることは重要ですが、それだけでは問題の解決や実践には繋がらないとされていました。
そのため、理論だけで中身がないことを指す言葉として、「空論」という表現が生まれました。
「空論」という言葉の歴史
「空論」という言葉の歴史は古く、中国の儒教の思想から始まります。
その後、日本においても官僚制度や政治組織などで、形式的な議論が重視されることがあり、それに対して批判的な意味で「空論」という言葉が使われるようになりました。
現代においても、中身のない議論や考え方を指す言葉として広く使用されています。
「空論」という言葉についてまとめ
「空論」という言葉は、形式的な議論や説明を指す言葉であり、具体的な内容や根拠がないことが特徴です。
日本語の言葉で、読み方は「くうろん」となります。
使い方や例文では、具体的なプランや戦略がない場合などに使われます。
成り立ちや由来は中国の儒教の思想に由来しており、現代においても広く使用されています。