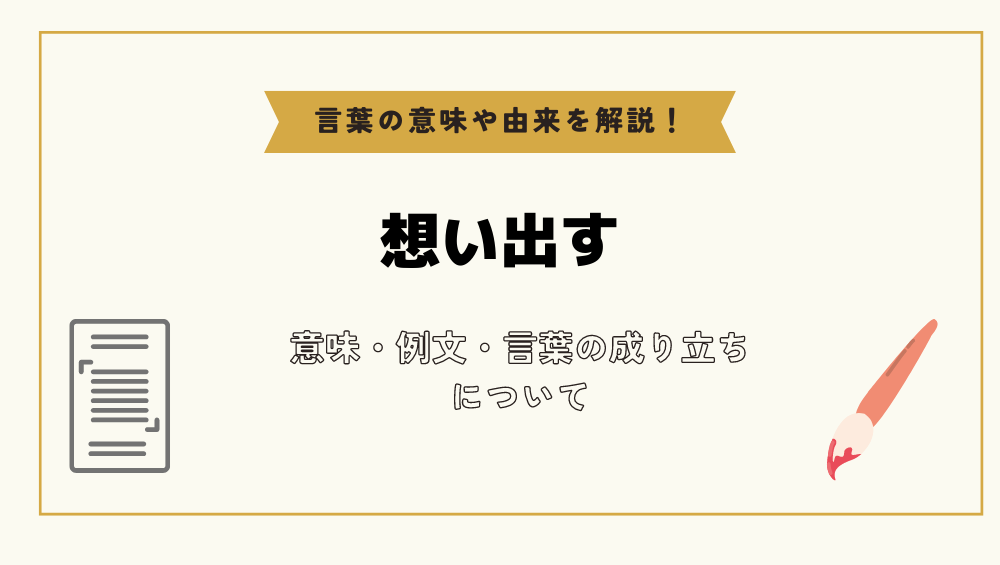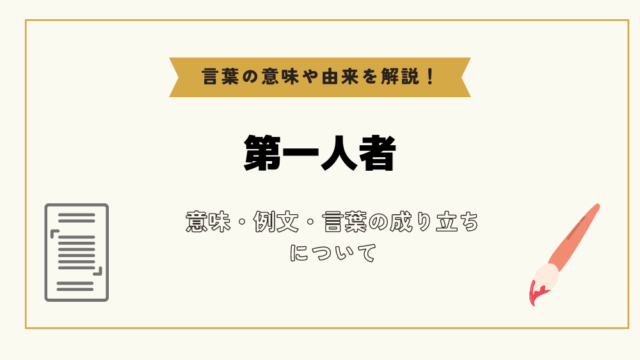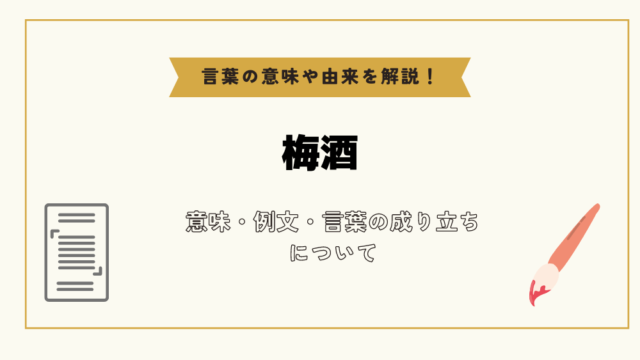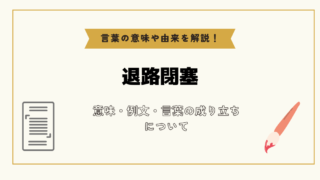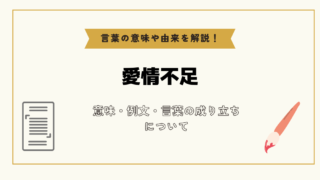Contents
「想い出す」という言葉の意味を解説!
「想い出す」という言葉は、過去の出来事や思いを思い起こすことを意味します。
ある出来事や人について記憶が薄れていたり、忘れかけている時に、その事柄を思い出すことを指します。
この言葉は、過去の思い出や経験を記憶することができるという人間の特性を表しています。
「想い出す」という言葉の読み方はなんと読む?
「想い出す」という言葉は、「おもいだす」と読みます。
最初の「おも」は「思い」の読み方で、二つ目の「だす」は「出す」の読み方です。
このように読むことで、過去の思い出を思い起こす意味が表現されます。
「想い出す」という言葉の使い方や例文を解説!
「想い出す」という言葉は、手紙や会話、物語などの表現に使われます。
例えば、「彼との出来事を想い出した」と言うと、過去に彼との経験や思い出が記憶から蘇ったことを意味します。
また、「この写真を見て思い出した」と言うと、その写真に写る人や風景に関連する過去の思い出が蘇ったことを表現しています。
「想い出す」という言葉の成り立ちや由来について解説
「想い出す」という言葉は、動詞「思い」に助動詞「だす」が付いた形で成り立っています。
「思い」とは心の中で生じる感情や思考を指す言葉であり、「だす」は出す、表すといった意味を持ちます。
このように、過去の思い出を心の中から引き出すという意味が込められています。
「想い出す」という言葉の歴史
「想い出す」という言葉の歴史は古く、日本語の成立以前の万葉集にも使われた形跡があります。
その後、時代が経つにつれて、様々な文学作品や歌によって広まりました。
現代でも、日常会話や文学作品などで頻繁に使用される一般的な言葉となっています。
「想い出す」という言葉についてまとめ
「想い出す」という言葉は、過去の出来事や思いを思い起こすことを表します。
この言葉は、私たち人間が持つ記憶の働きを象徴しています。
日常的な会話や文学作品でよく使用される言葉であり、人々が大切な思い出を共有するための架け橋となっています。