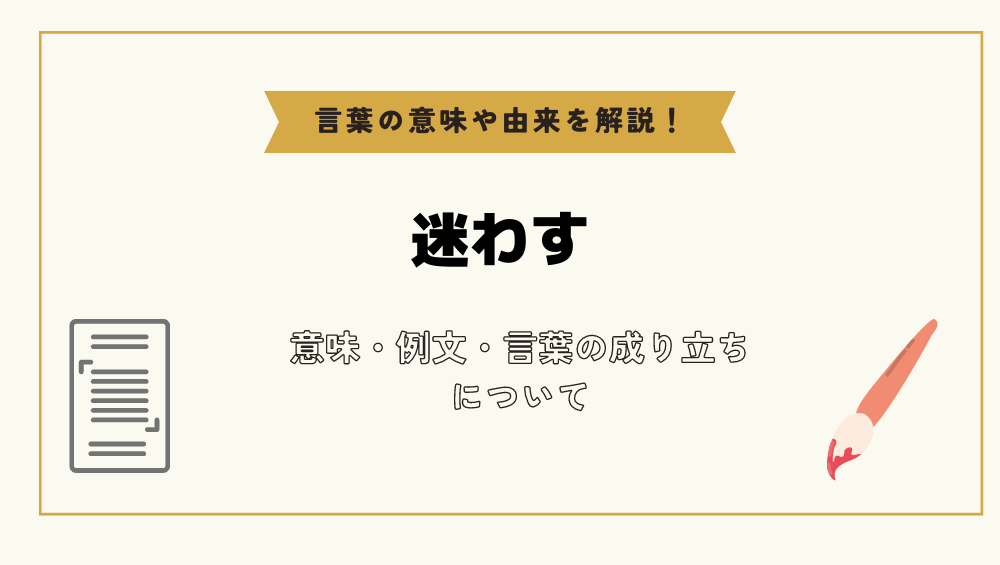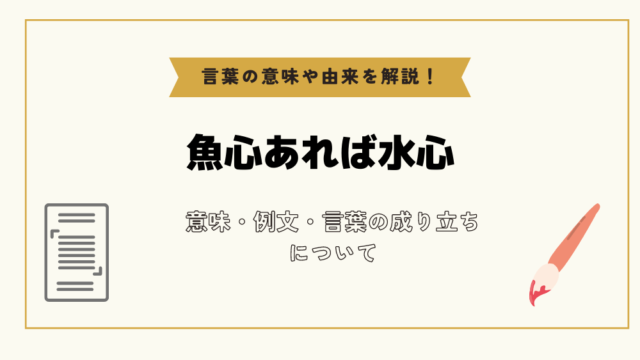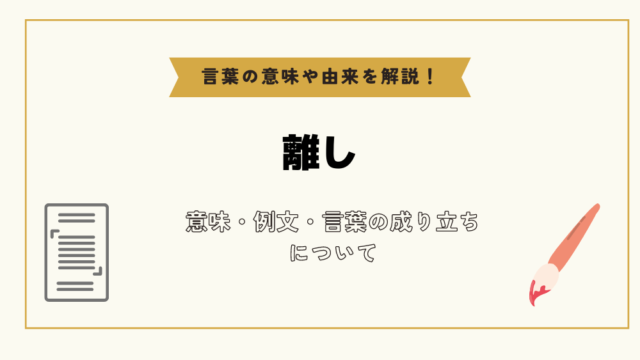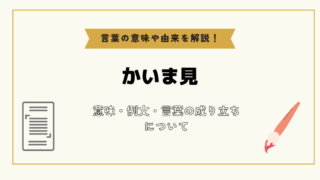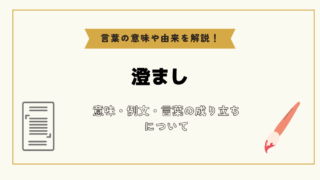Contents
「迷わす」という言葉の意味を解説!
「迷わす」という言葉は、人を迷わせたり、方向感覚や判断力を混乱させたりすることを意味します。
ある課題や問題に対して、適切な選択や行動が迷いやすくなる状態を表現する言葉です。
要するに、人を迷わせる行為や状態を表す言葉なのです。
「迷わす」という言葉の読み方はなんと読む?
「迷わす」は読み方が「まよわす」となります。
日本語の発音ルールに基づくと、二文字目の「や」は「i」という音に近いため、実際には「まよわす」と読むのが正しい読み方です。
「迷わす」という言葉の使い方や例文を解説!
「迷わす」という言葉は比喩的な表現として使われることが多いです。
「彼の言葉には迷いを迷わすものがあった」というように、ある人の発言や行動によって他人がどう行動すべきか迷いやすくなるという意味合いで使われます。
「教師の問いかけが生徒たちを迷わすことなく正しい方向へ導く」といった具体的な例文も考えられます。
「迷わす」という言葉の成り立ちや由来について解説
「迷わす」という言葉は、「迷う」という動詞に使役形をつけた形です。
「迷う」は、人が道に迷ったり、答えがわからなかったりする状態を表す言葉であり、「迷わす」はその状態を他者に与える行為や状態を示す言葉として派生したものです。
「迷わす」という言葉の歴史
「迷わす」という言葉の歴史は古く、日本語の古文書にも使用例が見られます。
元々は仏教用語として使われ、人々を迷い込ませることや錯覚させることを表していました。
その後、一般的な日常会話でも使われるようになり、現代の日本語においても広く使われる言葉となりました。
「迷わす」という言葉についてまとめ
「迷わす」という言葉は、他者を迷わせたり混乱させたりすることを意味します。
正確な行動や選択が難しくなる状態を表現する言葉です。
読み方は「まよわす」となります。
比喩的な表現として使われることが多く、例文では教師の問いかけや他人の言葉によって迷いが生じる状況を示すことができます。
由来や歴史は古く、元々は仏教用語として使われていましたが、現代の日本語で広く使用されるようになりました。