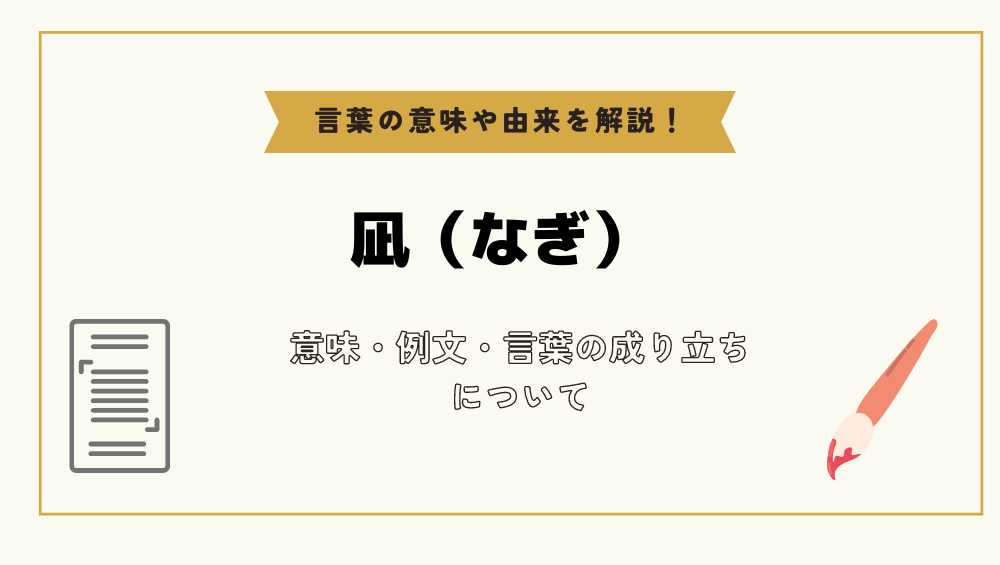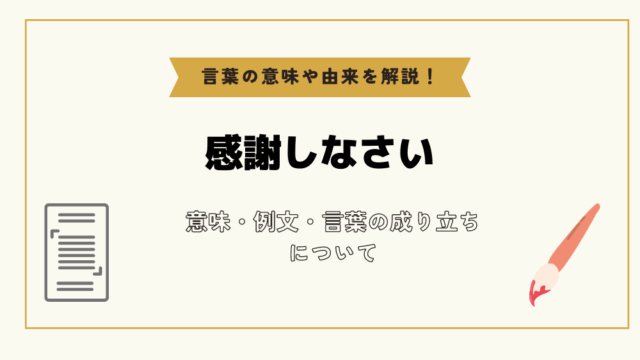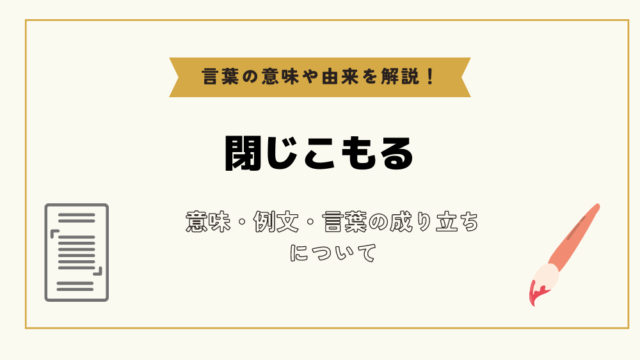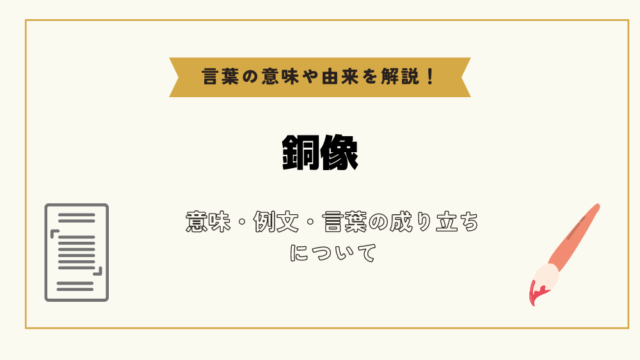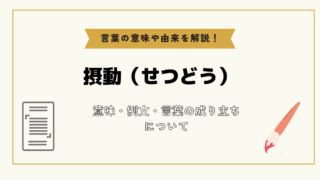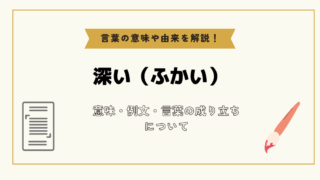Contents
「凪(なぎ)」という言葉の意味を解説!
凪(なぎ)という言葉は、船乗りや海の近くに住む人にとって馴染みのある言葉です。
これは、海の波や風が収まり、水面が穏やかになっている状態を表しています。
つまり、風がなく波もない状態を指すのです。
凪は、船の出入りや漁業にとって非常に重要な状態であり、穏やかな海での過ごし方を楽しむ人々にとっても特別な時間と言えるでしょう。
「凪(なぎ)」の読み方はなんと読む?
「凪(なぎ)」は、漢字の「凪」は「なぎ」と読みます。
これは正式な読み方であり、一般的に使われています。
ただし、地域によっては「なぎわ」とも読まれることがあります。
地域によって発音が異なることは珍しくなく、文化や言語の多様性があるからこそ、言葉の魅力も広がるのです。
「凪(なぎ)」という言葉の使い方や例文を解説!
「凪(なぎ)」という言葉は、主に海や風に関連する文脈で使用されます。
例えば、「今日は海が凪いでいて、釣りがしやすいですね」とか、「風が凪いでいるので、外での作業がしやすくなりました」といった具体的な使い方があります。
このように、「凪」は穏やかさや落ち着きを表す言葉として使われ、自然や海の景色を描写する際によく利用されることがあります。
「凪(なぎ)」という言葉の成り立ちや由来について解説
「凪(なぎ)」の成り立ちや由来については、特定の説が確立しているわけではありません。
ただし、この言葉が日本古来の海の文化と関わりが深いことは間違いありません。
海に囲まれた日本では、古くから船乗りや漁業が盛んであり、海の状態や風の様子を表現する言葉が生まれたのかもしれません。
また、「凪(なぎ)」の美しい風景は、日本人にとって特別なものとして受け継がれてきたのかもしれません。
「凪(なぎ)」という言葉の歴史
「凪(なぎ)」という言葉の歴史は古く、日本の古典文学や歌にもしばしば登場します。
例えば、万葉集や古今和歌集などには、海の凪や風情を詠んだ歌が数多く残されています。
このように、古代から「凪」の美しい風景が詠まれ、人々の心を惹きつけてきたのです。
長い歴史の中で、「凪」は日本の風土や文化の一部として深く根付いている言葉と言えるでしょう。
「凪(なぎ)」という言葉についてまとめ
「凪」は、波も風もない静かで穏やかな状態を指す言葉です。
海や風景を表現する際によく利用され、船乗りや自然愛好家にとって特別な時間と言えるでしょう。
読み方は「なぎ」であり、地域によっては「なぎわ」とも発音されることがあります。
また、「凪(なぎ)」の由来や成り立ちについては特定の説はないものの、海の文化や日本古来の風習と関係していることが考えられます。
日本の古典文学や歌にも多く登場し、人々の心を惹きつけてきた言葉であるとも言えるのです。