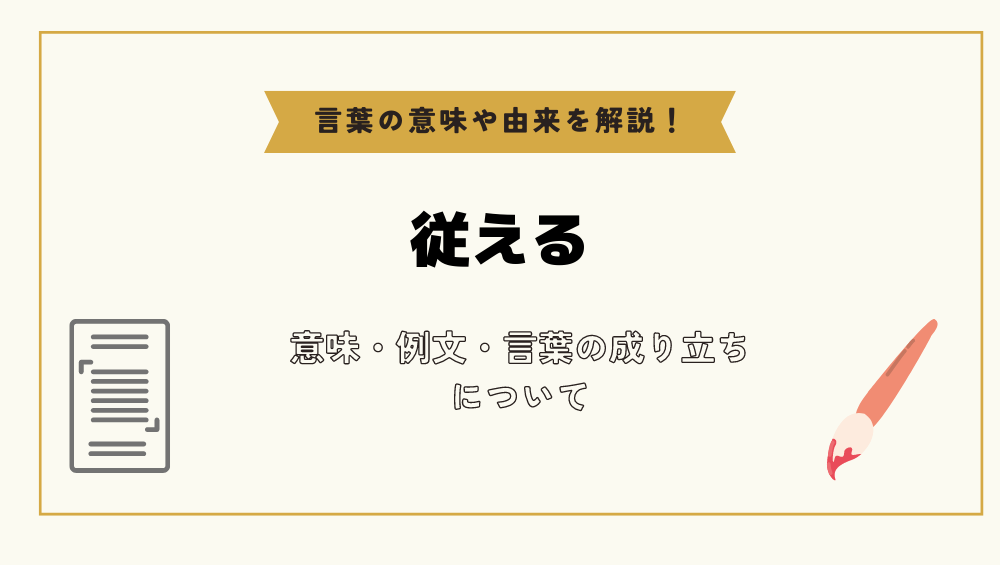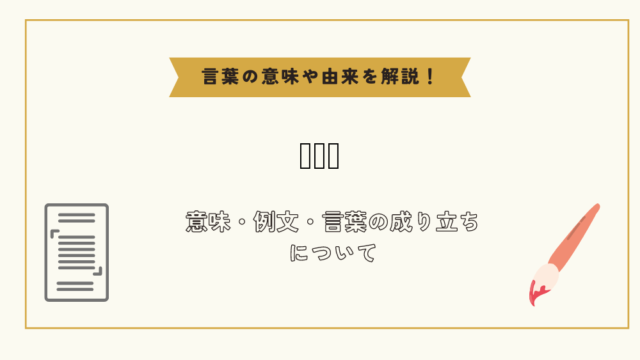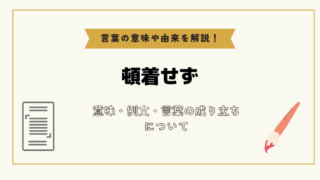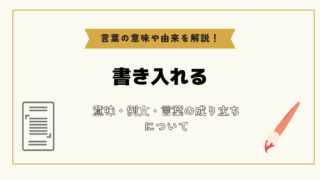Contents
「従える」という言葉の意味を解説!
「従える」という言葉は、他の人や物事を自分に服従させたり、ある行動を取らせたりすることを指します。
主に命令や指示に従うことを意味する言葉です。
相手や物事が自分の指示通りに動くという意味合いがあり、指揮や支配を行う際に使われることが多いです。
例えば、上司が部下に仕事を指示する際には、「従えるように」と言うことがあります。
ここでの「従える」は、上司の指示に従って行動することを求められていることを意味しています。
また、「従える」という言葉は、人間関係や組織の中での指導力や権限を表現する際にも使われます。
リーダーシップを持ち、他の人々を自分の意図通りに動かす力があることを示す言葉と言えます。
「従える」という言葉の読み方はなんと読む?
「従える」という言葉は、「したがえる」と読みます。
漢字の「従」は「したが」、動詞の接尾語「える」は「える」と読みます。
「従える」という言葉の使い方や例文を解説!
「従える」という言葉の使い方は、主に命令や指示をする場面で使用されます。
例えば、「彼は部下たちをうまく従えることができる」という文では、彼が上手に部下たちに指示を出し、彼らがその指示に従って行動することができる様子を表現しています。
また、個人的な関係でも、「従える」という言葉が使われることがあります。
「彼女は弟を上手に従えている」という文は、彼女が弟に対して指示や支配をせずに、上手に関係を築いていることを意味しています。
「従える」という言葉の成り立ちや由来について解説
「従える」という言葉の成り立ちは、「従」という漢字と「える」という動詞の接尾語から構成されています。
「従」は、「したが」と読み、「従う」という意味を持ちます。
この漢字は、人が他の人の指示や命令に従って行動する様子を表しています。
「える」は、「することができる」という意味の接尾語です。
この接尾語の結びつきにより、「従うことができる」という意味を持つ「従える」という言葉ができたのです。
「従える」という言葉の歴史
「従える」という言葉は、古い時代から存在していると言われています。
日本の古典文学や武士の道徳書などにも登場し、指導者や支配者の力や威厳を表現するために使用されてきました。
また、近代に入ってからも、「従える」という言葉は使われ続けています。
組織や企業の中での指導力や権限を持つ人物の存在が重要視されるようになり、そのような人々が部下やメンバーを「従える」という表現が一般的になりました。
「従える」という言葉についてまとめ
「従える」という言葉は、他の人や物事を自分の意図通りに動かすことを意味する言葉です。
命令や指示に従うことを表現し、指導力や権限を持つ人物の存在を示す場合に使われることが多いです。
正しい読み方は「したがえる」であり、古くから日本語に存在する言葉です。