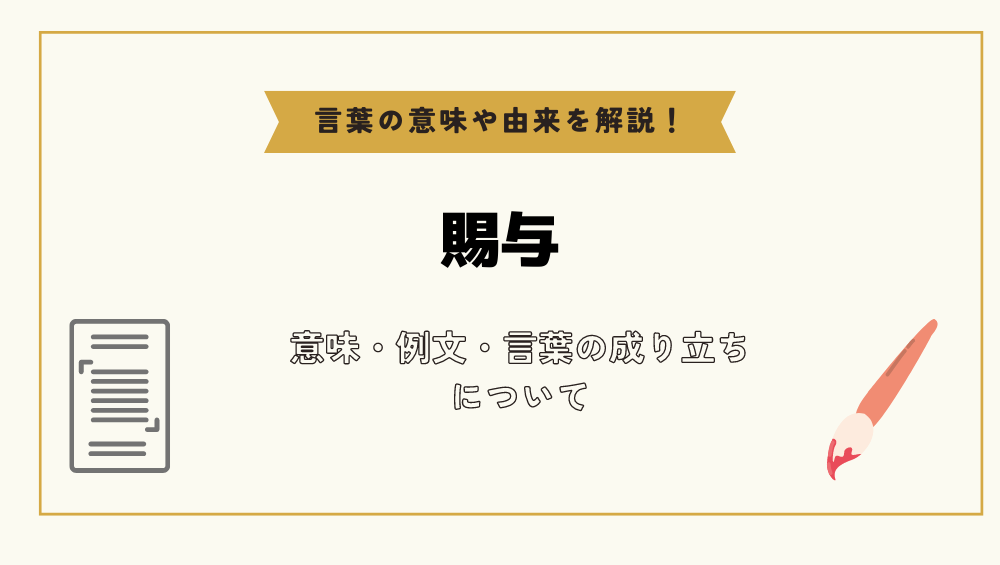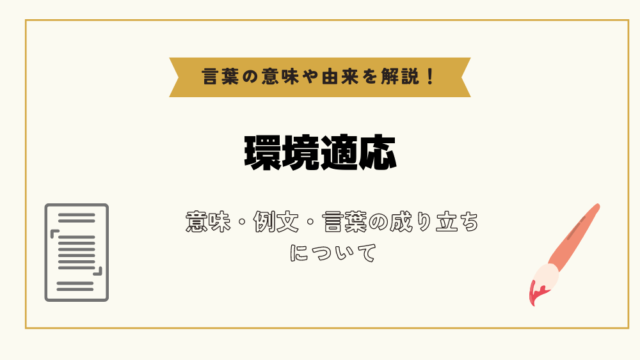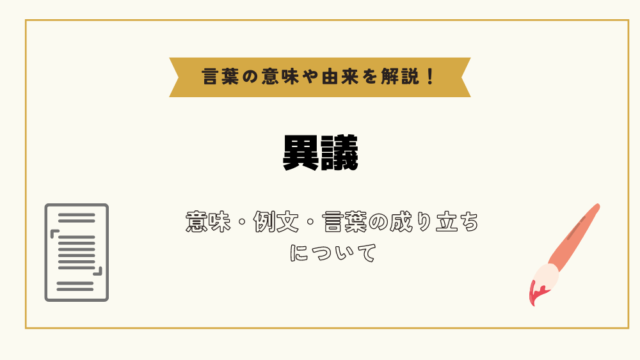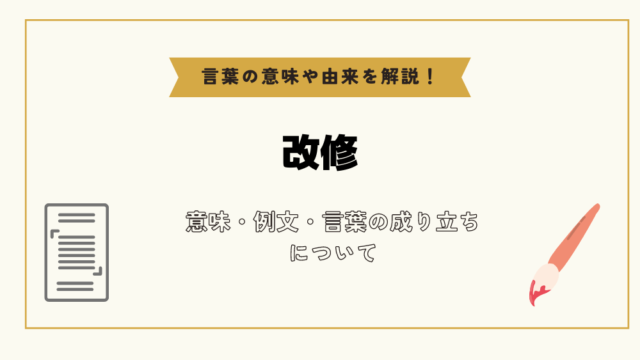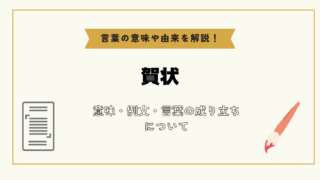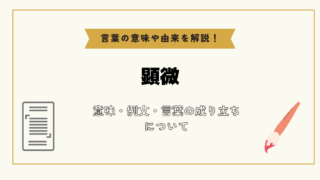「賜与」という言葉の意味を解説!
「賜与(しよ)」とは、目上の人物や公的機関が目下の人物に物品・地位・権利などを恩恵として授けることを指す格式高い言葉です。
この語は「賜る(たまわる)」と「与える(あたえる)」が結び付いた二字熟語で、両方の意味が重複しているため「とりわけ丁寧な授与」というニュアンスが濃く残ります。
現代日本語で日常的に耳にする場面は少ないものの、皇室関連のニュースや法律文書、宗教儀礼、文化財の寄進などで今も用いられています。
公的・儀礼的シーンでの使用が多い理由は、単に「与える」よりも敬意を示す効果が高く、利害関係の有無によっては「恩恵性」を明確に区別できるためです。
口語ではほぼ使われず、書面中心の語彙として定着している点が大きな特徴といえるでしょう。
「賜与」の読み方はなんと読む?
一般的な読み方は「しよ」で、音読みをそのまま当てはめた形が公的な辞書でも採用されています。
まれに「しゆ」と読む古書もありますが、現行の公的機関や新聞各社の表記基準では「しよ」が正式です。
訓読み(たまわりあたえ)と混同しやすいものの、熟語としては訓読みを当てる慣習はなく、あくまで音読み一本で理解すると良いでしょう。
漢字の構成上「賜」は「し」「たまわる」、「与」は「よ」「あたえる」と読むため、送り仮名なしの音読みを採ると「しよ」になります。
複合語「賜与金(しよきん)」「賜与者(しよしゃ)」なども音読みで続けるのが一般的です。
「賜与」という言葉の使い方や例文を解説!
書面語であることを踏まえ、目上から目下への「格別の恩恵」を示す文脈で用いることが基本です。
日常の会話では不自然になりがちなので、公文書・式辞・学術論文など「かしこまった文体」を必要とする場で限定的に使われます。
使用時は「賜与する」「賜与された」といった動詞形、あるいは名詞形「賜与」を目的語とする構文が中心です。
【例文1】本奨学金は、創設者の遺志により学生へ賜与される。
【例文2】叙勲に際し、天皇陛下から記念品が賜与された。
このように主語が「天皇」「財団」「国家」など、対象より高位に位置づけられる組織や人物である点がポイントです。
口語で言い換えるなら「授与」「寄贈」が近いニュアンスになりますが、「賜与」は「威光を帯びた贈与」であることを暗示します。
「賜与」という言葉の成り立ちや由来について解説
「賜」と「与」はどちらも古代中国語圏で「授ける」を意味し、日本へは漢籍を通じ飛鳥~奈良時代に輸入されたと考えられています。
律令制下の官文書では「賜」単独で恩賜を示し、「与」は一般的な付与として区別されていました。
やがて平安中期以降、両字を重ねて敬意を強調する複合語「賜与」が登場し、主に朝廷や貴族社会で限定的に用いられる尊敬語として定着します。
この重語化は「重言」と呼ばれる語形成の一種で、「見守る」「聞き入れる」といった現代語にも通じる日本語独自の強調表現と同根です。
つまり「賜与」は単なる漢語の輸入ではなく、日本語の敬語体系に取り込まれる過程で生まれた和製強調語といえるでしょう。
「賜与」という言葉の歴史
奈良時代の木簡や正倉院文書には「賜」と「与」を連結しない記録が大半でしたが、平安時代の『日本三代実録』あたりから「賜与」の初出が確認されます。
中世に入り武家政権が誕生すると、将軍や大名が家臣へ恩賞を与える際も「賜与」が用いられ、語義は「主君から家来へ」へと拡張しました。
近世では幕府の朱印状・領地安堵状など公式文書の定番語となり、明治期の近代法体系整備後も条文に残りました。
昭和以降は法律用語としての頻度が減り、『皇室典範』関連、文化財の寄附行為、大学の名誉学位授与式辞など専門領域へ限定されています。
「賜与」の類語・同義語・言い換え表現
同じく目上から目下へ授けるニュアンスを持つ語には「下賜」「恩賜」「授与」「下附」などがあります。
特に「授与」は中立的でビジネス文書でも使いやすく、「下賜」「恩賜」は皇室・神社関連で威光を伴うという使い分けが可能です。
【例文1】社長賞を授与する。
【例文2】神前に御神酒を下賜いただく。
「寄贈」「寄進」「贈与」は恩恵よりも好意を重視する点が異なり、「拝受」は受ける側の敬語表現なので混同しないよう注意しましょう。
「賜与」の対義語・反対語
対義的な関係に立つ語は「返納」「返上」「没収」など、授けられた物を返す・取り上げる行為を示す言葉です。
「返納」は受け手が自発的に戻す場面、「没収」は授け手もしくは権力者が強制的に取り上げる場面で用いられます。
また「給付」を広義の意味で対比させる場合もありますが、「給付」は立場差が薄く行政サービス的なニュアンスが強いため完全な反意ではありません。
反対概念を理解しておくと、契約書や規程の中で「賜与した財産を返納させる場合」などの条項の意味が明確になります。
「賜与」を日常生活で活用する方法
正直なところ、日常会話で「賜与」を用いると堅苦しさが際立ちます。
しかし表彰状や式次第、学術論文、社史の編纂などフォーマル文書を作成する機会がある人には重宝する語彙です。
使う際は「誰が誰に対して恩恵として授けたか」を明確にし、文章全体の敬語レベルを統一することがポイントです。
具体的には、全文を「謹んで」「ここに」「謹呈」といった格調高い語で統一し、「賜与」を浮かせない工夫が必要となります。
【例文1】創立者の遺産を基金として賜与し、奨学事業を開始する。
【例文2】名誉教授称号を賜与する旨、本学評議会において承認された。
「賜与」についてよくある誤解と正しい理解
最も多い誤解は「賜与=寄付」と同一視することですが、寄付は自発的行為、賜与は「上位者の恩恵」という立場性が必須です。
また「賜与=法律用語だから一般文書ではNG」と考える人もいますが、公的性質がある式辞や表彰状なら問題なく使えます。
漢字が難しいため「賜与」を「赦与」「賜予」と書き誤るケースも散見されます。
表記ゆれを避けるには、公的な文献や辞書で確認し、文書作成ソフトの校正機能を併用することが推奨されます。
「賜与」という言葉についてまとめ
- 「賜与」は目上から目下へ恩恵として授ける行為を表す格式高い言葉。
- 読み方は「しよ」で、音読みが正式とされる。
- 平安期に日本独自の強調表現として定着し、朝廷・武家文書で用いられた歴史を持つ。
- 現代では式辞や法律文書で限定的に使用され、敬語レベルの統一が重要。
「賜与」は日常語からは一歩離れた存在ですが、公的・儀礼的なシーンでは今も健在な日本語の財産です。
上意下達の立場差を明確にしながら感謝と敬意を示すこの語を適切に使うことで、文章全体の格調を高めることができます。
ただし乱用すると仰々しくなるため、用途や相手の理解度を考慮しながら「授与」「寄贈」など他の語と使い分けると良いでしょう。