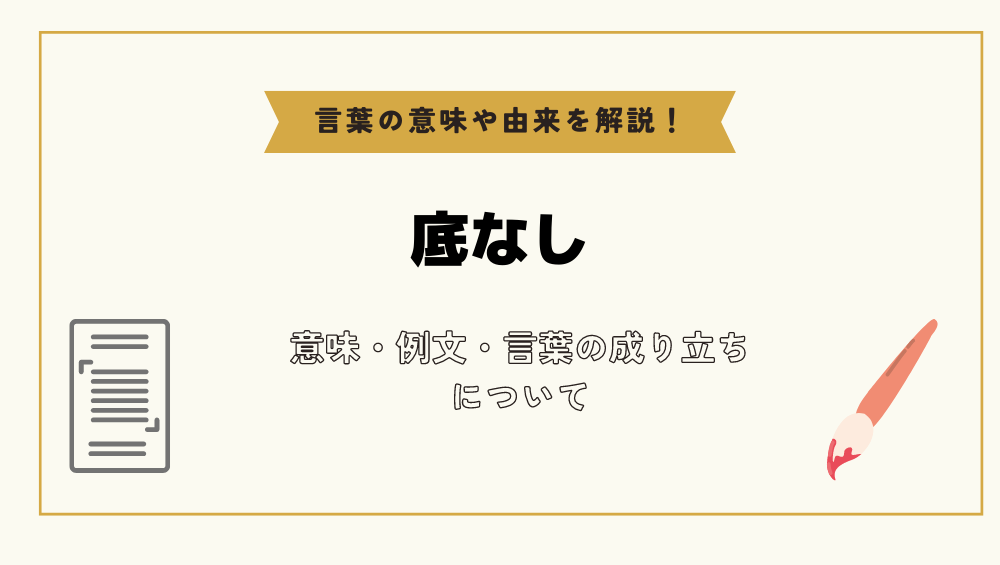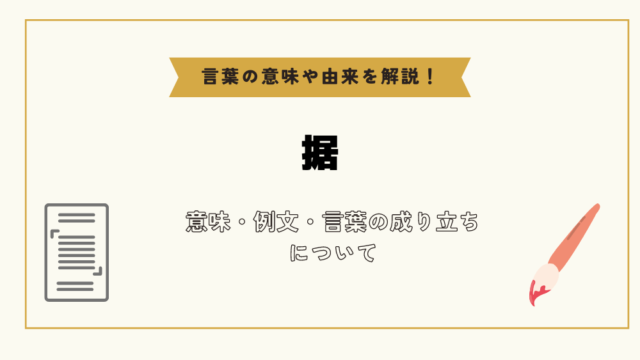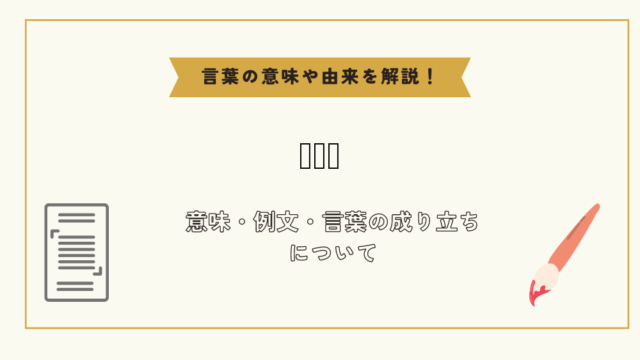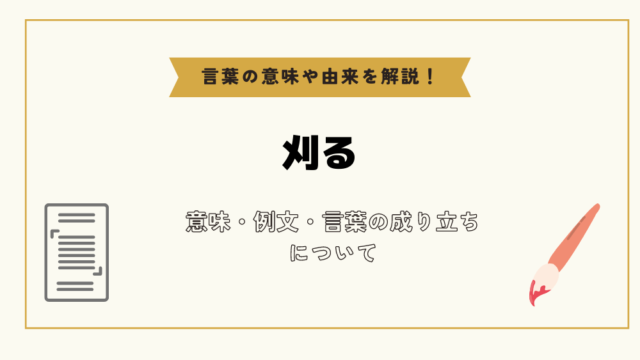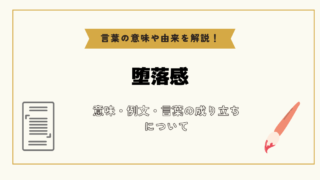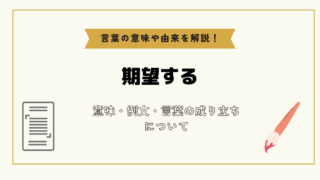Contents
「底なし」という言葉の意味を解説!
「底なし」は、物事や状況が果てしなく深くて終わりがない様子を表す言葉です。
何をしても底が見えず、限りがないという意味を含んでいます。
「底」は物の最も下部や終わりを指し、「なし」は存在しないことを意味します。
例えば、「底なし沼」という言葉は、沼地のように深く底が見えない状態を表現しています。
「底なし」の読み方はなんと読む?
「底なし」のふりがなは「そこなし」と読みます。
日本語の読み方においては、「そこ」の部分を「そこ」と読んで、「なし」の部分を「なし」と読みます。
このように読むことで、「底なし」という言葉がもつ深みや重みがより強調されます。
「底なし」という言葉の使い方や例文を解説!
「底なし」という言葉は、日常会話や文学作品などさまざまな場面で使われます。
例えば、仕事が山積みで疲れ知らずであることを表現する際には、「彼の仕事量は底なしです」と言えます。
また、物事がどんどん深刻になる様子を表現する時にも「底なし」という言葉を使うことがあります。
「この問題は底なしに複雑化しています」といった風に使われます。
「底なし」という言葉の成り立ちや由来について解説
「底なし」という言葉は、古くから日本語に存在している表現です。
由来ははっきりとは分かっていませんが、物事の深みや果てしなさを表現するために、「底」という言葉を使ったのが始まりと考えられます。
無限に続いているかのような様子を、言葉で表現するために、「底なし」という形容詞が生まれたと言われています。
「底なし」という言葉の歴史
「底なし」という言葉の歴史は古く、日本の文学作品や古典などでも頻繁に使用されてきました。
江戸時代や明治時代の文献にも見られる表現であり、人々の生活や思考の中で「底なし」という言葉は広く受け入れられてきたと言えます。
現代の言葉遣いでもそのまま使われることが多く、時代を超えて愛されています。
「底なし」という言葉についてまとめ
「底なし」という言葉は、果てしなく深い状態や終わりが見えない様子を表現する言葉です。
仕事や問題、物事の深みなどさまざまなものに使われます。
古くから日本語に存在し、言葉の歴史も長いです。
使う際には「そこなし」と読みます。
この言葉を使うことで、人間味が感じられる文章がより魅力的になります。