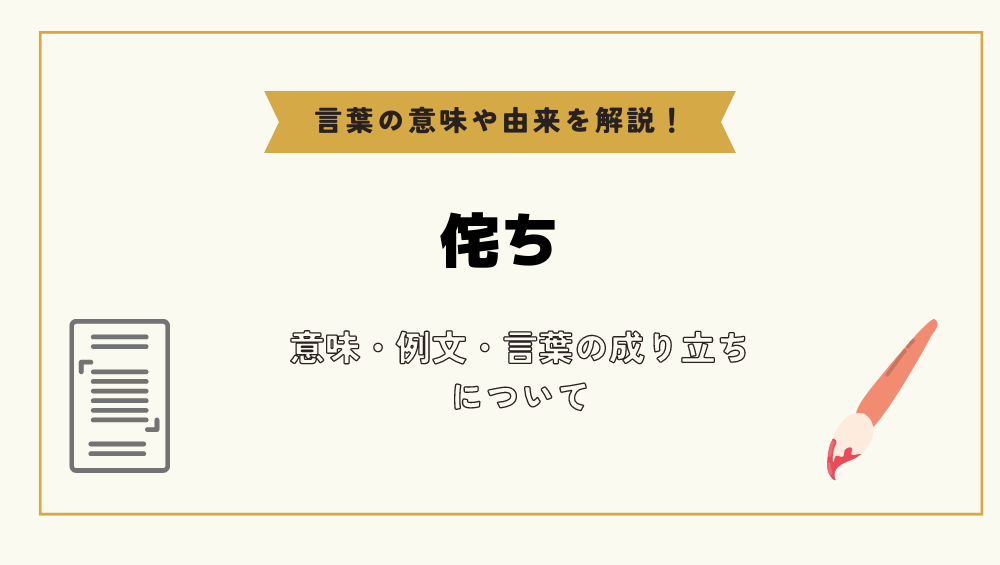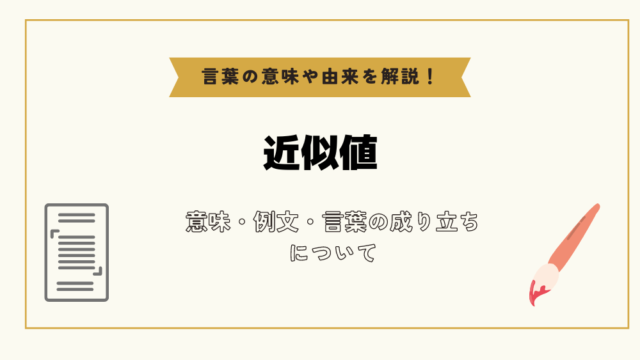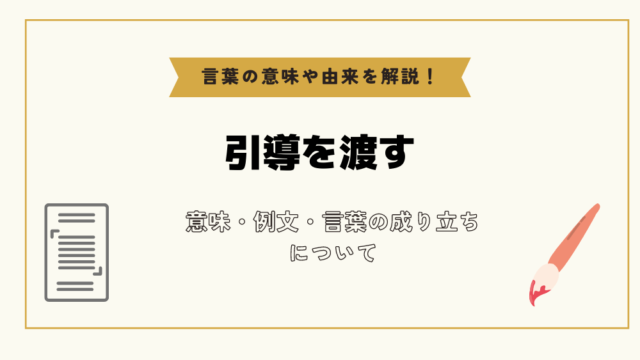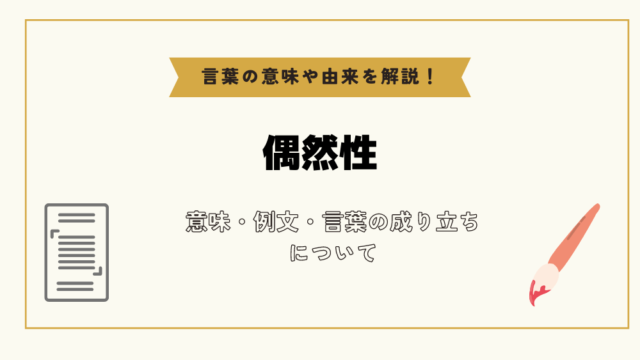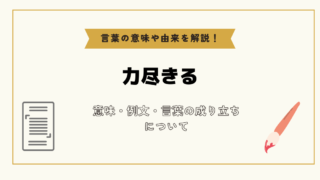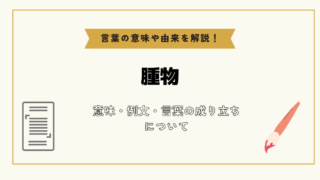Contents
「侘ち」という言葉の意味を解説!
「侘ち」という言葉は、日本語において特に美学的な文脈で使われる言葉です。
この言葉は、物事のあくまで自然なありのままの美しさや、控えめな美しさを指すことが多いです。
「侘ち」の魅力は、物事が単純で地に足の着いた形であることにあります。
人々に心の安らぎを与えるような、繊細な美しさを感じることができます。
「侘ち」という言葉の読み方はなんと読む?
「侘ち」という言葉は、わび・ち(Wabi-chi)と読みます。
この単語は、日本語の発音の特徴である「わ行」と「ち行」の音を含んでいます。
直訳すると、「わび」は「わびらしい」という意味で、「ち」は簡素であることを表します。
「侘ち」という言葉の使い方や例文を解説!
「侘ち」は、しばしば日本の伝統的な美の表現として使用されます。
日本庭園や茶室、または和食などの文化体験において、「侘ち」の要素を感じることができます。
例えば、自然の素材を使ったシンプルで質素な家具や、手作りの陶磁器などが「侘ち」の要素を含んでいます。
日本の古典的な美意識を体現したものとして、世界中でも高い評価を受けています。
「侘ち」という言葉の成り立ちや由来について解説
「侘ち」という言葉の成り立ちや由来は、日本の伝統文化に深く根付いています。
この言葉は、15世紀に起源を持ち、茶道や詩歌の世界で使われ始めました。
当時の日本では、戦国時代の変化とともに、単純で自然な美を追求する風潮が生まれました。
これが「侘ち」の概念の基盤となりました。
「侘ち」という言葉の歴史
「侘ち」の歴史は、約600年以上にわたります。
この言葉は、茶道や建築、庭園など、日本の芸術や文化の中で重要な位置を占めています。
特に茶道では、「茶の湯」の精神を体現するために、「侘ち」の要素が多く用いられています。
また、近年では、日本の伝統文化が海外でも注目を浴び、その美しさが広まっています。
「侘ち」という言葉についてまとめ
「侘ち」という言葉は、自然な美しさやシンプルさを表現するために使われることが多い日本語の言葉です。
この言葉は、控えめでありながらも心を豊かにするような美を追求する文化の中で生まれました。
日本の伝統芸術や文化の中で深く根付いており、世界中で高く評価されています。
「侘ち」の要素を含んだものは、我々の日常生活においても、より心地よさを感じさせてくれます。