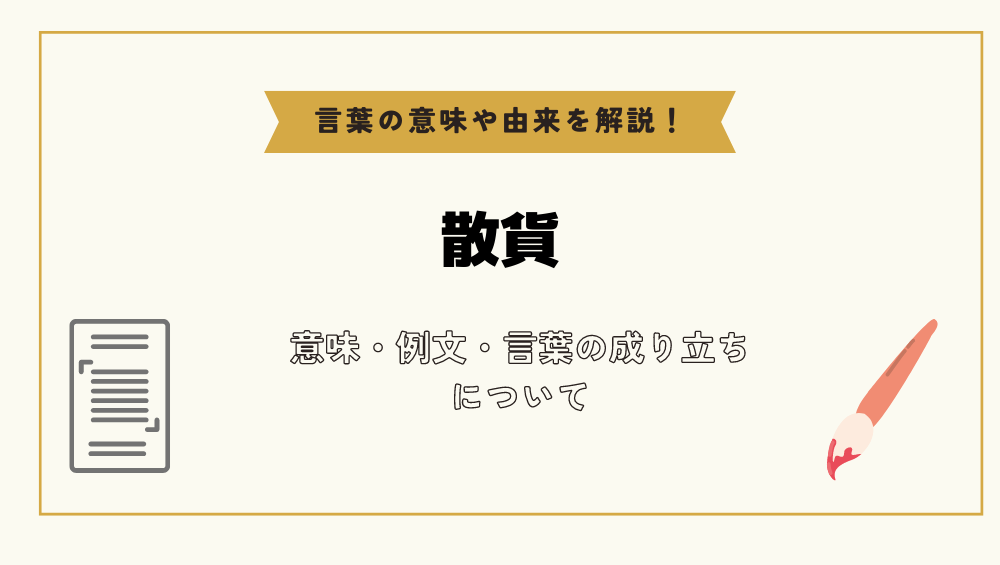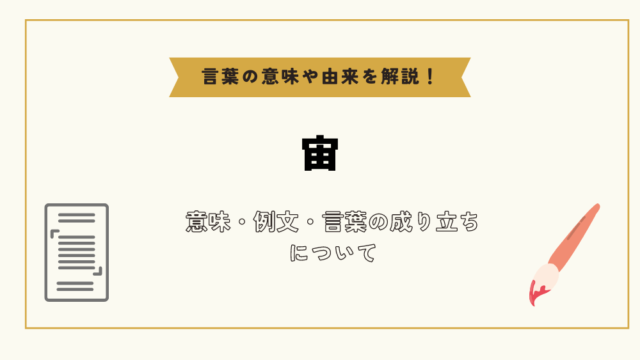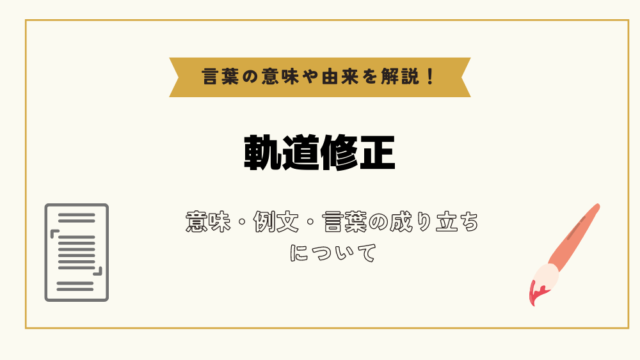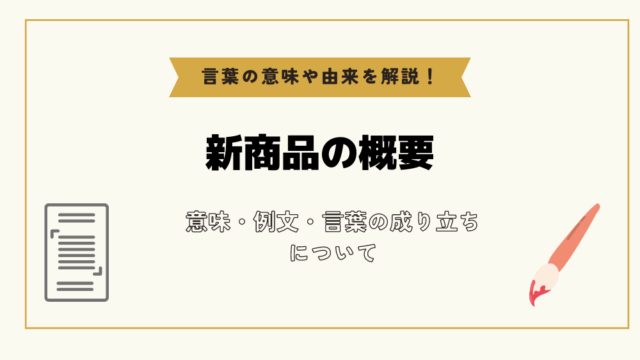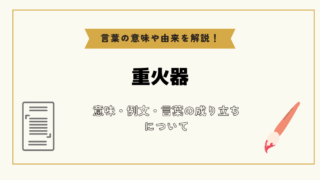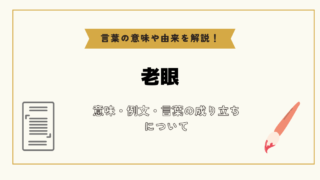Contents
「散貨」という言葉の意味を解説!
「散貨」とは、小銭や細かいお金のことを指す言葉です。
通常、100円以上の硬貨や紙幣とは異なり、1円や5円、10円などの小額硬貨を指します。
散貨は、日常生活のさまざまな場面で使われるため、私たちの生活には欠かせない存在と言えるでしょう。
「散貨」という言葉の読み方はなんと読む?
「散貨」という言葉は、読み方は「さんか」となります。
普段皆さんがよく使う単語ではないかもしれませんが、これから覚えておくと役に立つことがありますので、ぜひ頭に入れておいてください。
「散貨」という言葉の使い方や例文を解説!
「散貨」という言葉は、お金に関する話題でよく使われます。
たとえば、コンビニで商品を買う際に、レジで小銭を渡すことなどがあります。
「今日は1000円札しかありません。
散貨でおつりをもらえますか?」と言う具体的な例文が考えられます。
散貨は、小額のお金のことを指し、金銭のやり取りにおいて重要な役割を果たしています。
「散貨」という言葉の成り立ちや由来について解説
「散貨」という言葉は、漢字の「散」と「貨」から成り立っています。
漢字の「散」は、「破れる」という意味を持ち、また「貨」は「物品」という意味を持ちます。
小銭を指す「散貨」の言葉の由来は明確ではありませんが、おそらく小額の硬貨がばらけている様子を表した言葉と考えられます。
「散貨」という言葉の歴史
「散貨」という言葉は、古くから使われている言葉です。
江戸時代から存在し、当時の日本では小銭や小額のお金に頻繁に触れる機会がありました。
そこで、人々がより便利に使うために「散貨」という言葉が生まれました。
現代でもこの言葉は使われ続け、私たちの生活に根付いています。
「散貨」という言葉についてまとめ
「散貨」という言葉は、小額のお金を指す言葉です。
日常生活の中でよく使われ、金銭のやり取りに重要な役割を果たしています。
この言葉の由来は明確ではありませんが、古くから存在し、私たちの生活に根付いています。
個人の日常から経済活動まで、さまざまな場面で「散貨」という言葉が活躍しています。