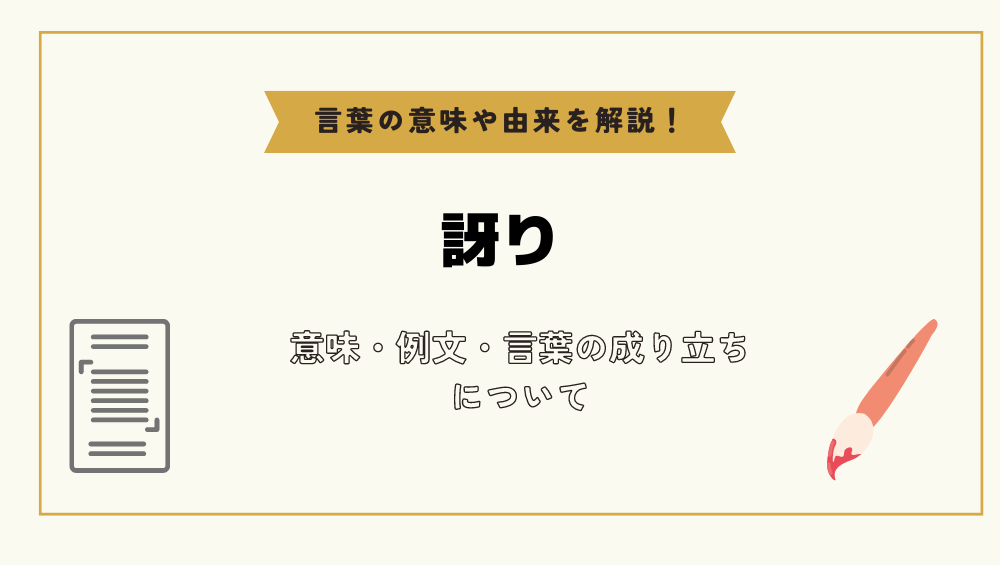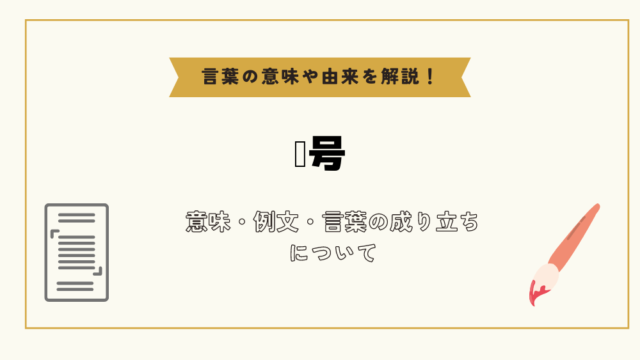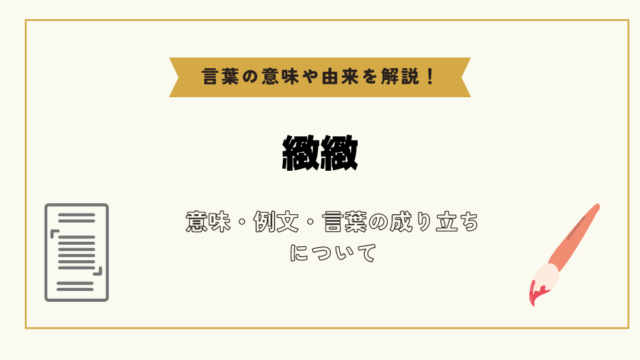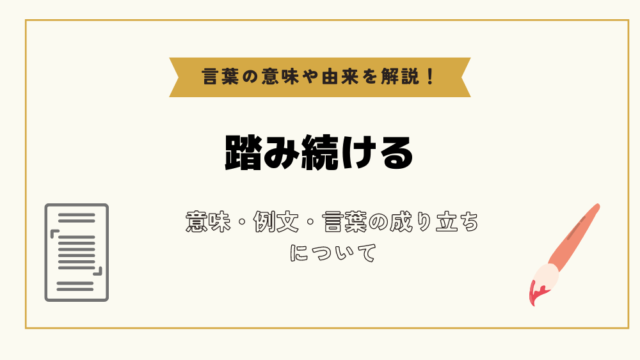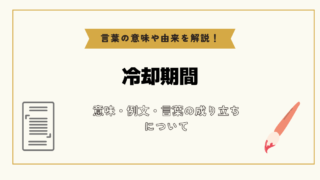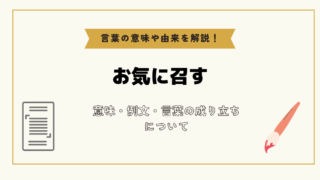Contents
「訝り」という言葉の意味を解説!
「訝り」という言葉は、疑問や不思議に思う気持ちを表現するために使われます。「疑問や不思議に思う気持ち」と言い換えると、他の言葉では「不審」「疑念」「疑問」「不信感」などとも言えます。
この言葉は、何かについて疑問や不審を感じる際に使います。「訝り」を感じるということは、通常の範囲を超えて状況が奇妙だと感じたり、事実と異なるように思えるという場合に用いられます。
「訝り」という言葉の読み方はなんと読む?
「訝り」の読み方は、「いぶかり」と読みます。このように読まれることで、「訝り」という言葉には少し風変わりで独特な響きがありますね。
「いぶかり」という読み方は、疑問や不安が感じられる響きを持っています。この読み方によって、言葉の意味をさらに強調しています。
「訝り」という言葉の使い方や例文を解説!
「訝り」という言葉は、疑問や不審に思う気持ちを表現する際に使用されることが一般的です。例えば、以下のような使い方があります。
1. 彼の言動には何かしらの訝りを感じる。
2. 彼の急な辞職には訝りを感じる。
3. 彼の態度には少し訝りを感じる。
これらの例文は、各人が自分の感情や状況に関して「訝り」を感じていることを示しています。何かが理解し難い、普通ではないと感じるときに使われる言葉なのです。
「訝り」という言葉の成り立ちや由来について解説
「訝り」という言葉の成り立ちは、「いぶかり」という形容動詞「いぶかる」から派生しています。この「いぶかる」は、「疑う」「不審に思う」といった意味があります。
日本語における「いぶかる」の語源は、古代中国の用法に由来しています。日本の遣唐使が古代中国との文化交流を行った際に、「いぶかる」の意味が言葉として持ち込まれたと考えられています。
「訝り」という言葉の歴史
「訝り」という言葉は古くから使われてきました。日本語の辞書や文献を見る限り、平安時代以降には既に使われていたとされています。
また、日本では「訝り」という言葉が使われていた時期には、独特な風習や価値観が存在していたことも考えられます。当時の人々は、疑問や不思議なことへの関心を持っていたのかもしれません。
「訝り」という言葉についてまとめ
「訝り」という言葉は、疑問や不審に思う気持ちを表現するために使われます。「いぶかり」と読まれるこの言葉は、独特な響きを持っています。
この言葉は、日本の古い言葉であり、平安時代以降に使われ始めたとされています。使われている時期や風習と関連して、当時の日本の文化を表現しているのかもしれません。
「訝り」は、状況や人間関係において、私たちが感じる疑問や不安を表現するのに適した言葉です。自分自身や他の人に対して「訝り」を感じた時は、この言葉を使って表現してみてください。