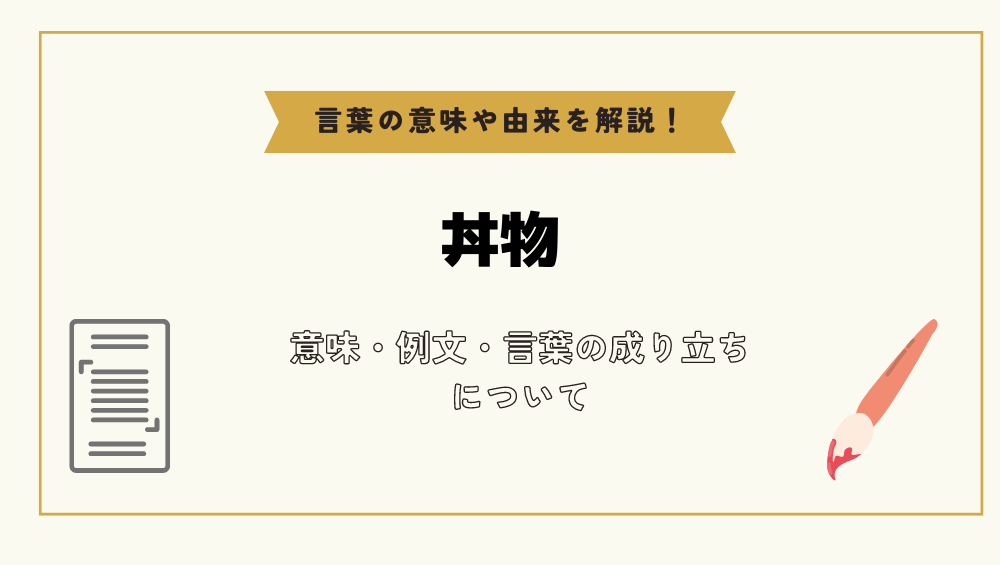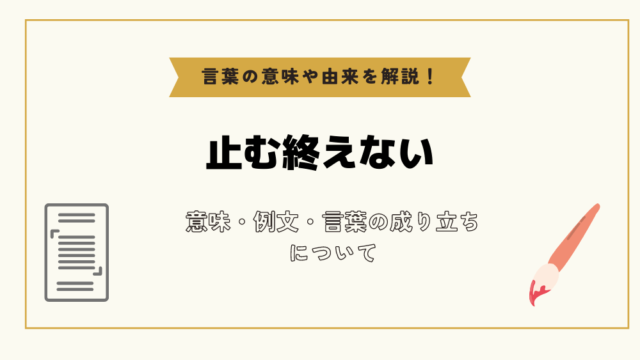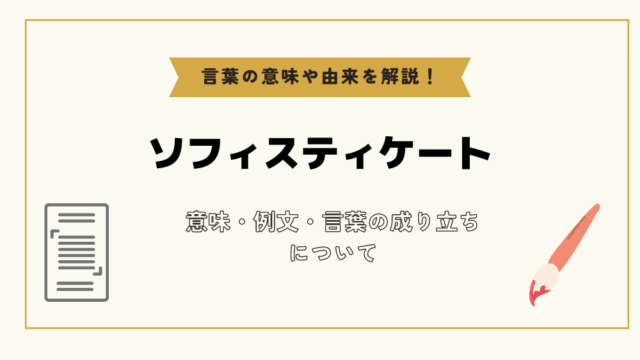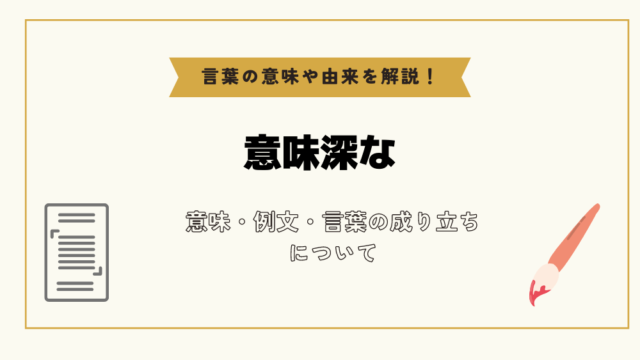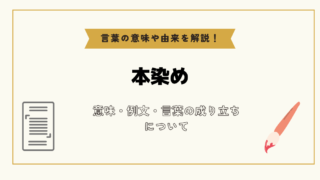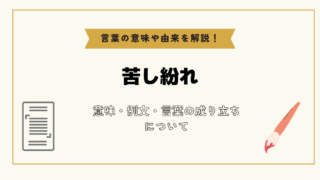Contents
「丼物」という言葉の意味を解説!
丼物(どんぶつ)とは、ご飯の上に具材を盛り付けた料理のことを指します。
具材はさまざまで、魚や肉、野菜などが主に使われます。
丼物は、ご飯と具材が一緒になって一つの食事となり、一杯で満足感を得ることができます。
「丼物」という言葉の読み方はなんと読む?
「丼物」という言葉は、「どんぶつ」と読みます。
日本語では、漢字の読み方は場合によって異なることがありますが、「丼物」の場合は「どんぶつ」と読むのが一般的です。
「丼物」という言葉の使い方や例文を解説!
「丼物」という言葉は、具体的な料理名として使われることが多いです。
例えば、「親子丼」や「牛丼」といった具体的な料理が、「丼物」として紹介されます。
また、「昼ごはんは丼物が食べたいな」というように、食事のジャンルを表現する際にも使われます。
「丼物」という言葉の成り立ちや由来について解説
「丼物」という言葉は、江戸時代に成立したと考えられています。
当時、具だくさんの大皿料理を「丼」と呼んでいました。
その後、「ご飯の上に具材を盛り付ける料理」を指すようになり、現在の意味が広まりました。
具体的な由来については諸説ありますが、江戸時代の「丼」という言葉が基盤になったと考えられています。
「丼物」という言葉の歴史
「丼物」という言葉は、江戸時代に誕生しました。
当初は大皿料理を指す言葉でしたが、やがてご飯に具材を盛り付ける料理に使われるようになりました。
明治時代以降の近代化に伴い、丼物は庶民の間で広く親しまれるようになりました。
現在では、丼物は日本の代表的な食文化の一つとして認知されています。
「丼物」という言葉についてまとめ
「丼物」という言葉は、ご飯に具材を盛り付けた料理を指す言葉です。
具材はさまざまな種類があり、魚や肉、野菜などが一緒になって美味しい一杯を作ります。
江戸時代に成立した言葉であり、日本の食文化を代表する一つとなっています。