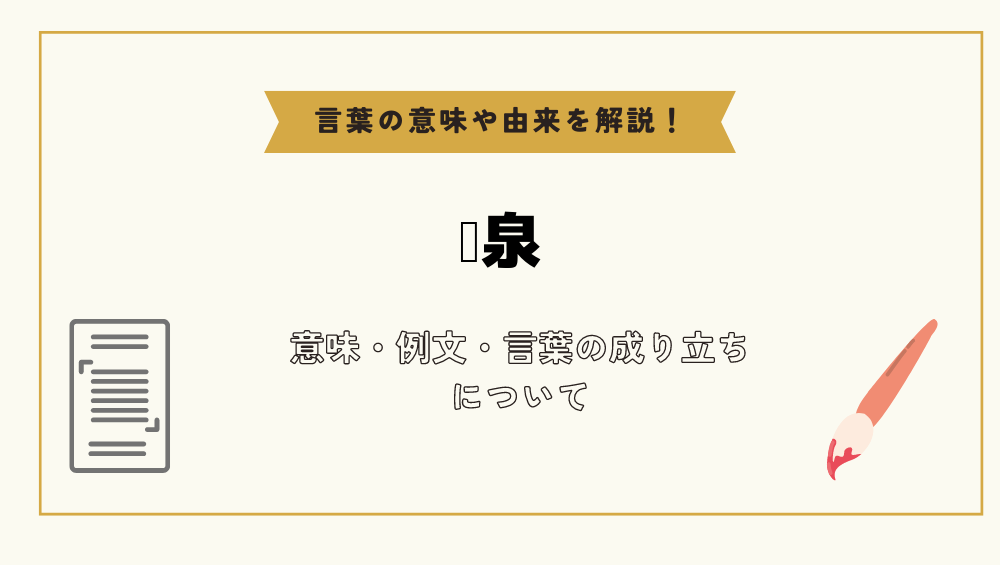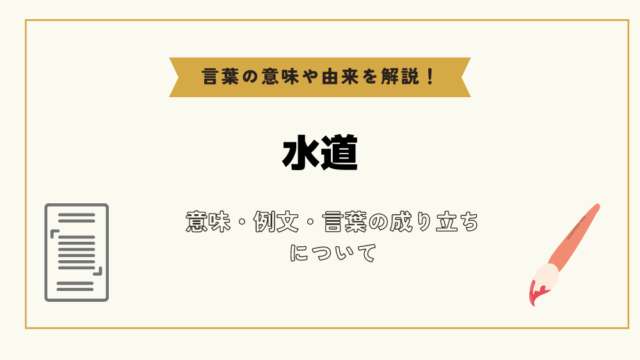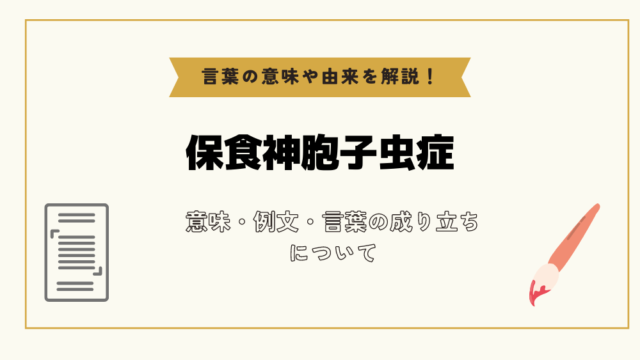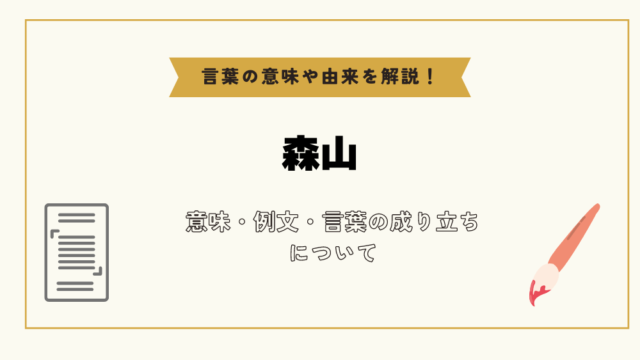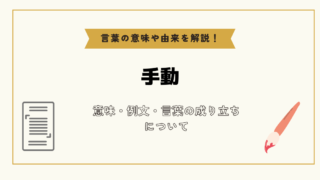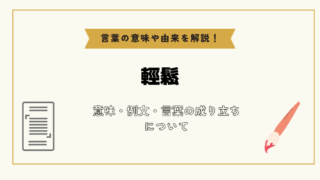Contents
「溫泉」という言葉の意味を解説!
「溫泉」とは、自然から湧き出る温かい地下水のことを指します。
その地下水にはさまざまなミネラルが含まれており、健康や美容に良い効果があるとされています。
また、湯量が豊富で温度も高いため、入浴や入湯することによってリラックスや癒しを感じることができます。
「溫泉」という言葉の読み方はなんと読む?
「溫泉」という言葉の読み方は、「おんせん」となります。
日本語では「おん」と「せん」という2つの音で構成されています。
「おん」は「温」の音、「せん」は「泉」の音です。
この読み方によって、温かい地下水の湧き出る場所を指す意味が伝わります。
「溫泉」という言葉の使い方や例文を解説!
「溫泉」という言葉は、主に温泉施設や旅行の際に使用されます。
友人や家族と一緒に温泉旅行に行く場合、「温泉に入る」と表現することがあります。
「今度の休日は溫泉に行こう!」と誘い合ったり、「温泉でゆっくりとリフレッシュしたい」と話したりすることもあります。
また、温泉地の名前を挙げて、「有名な温泉地に行ってみたい」と言ったりもします。
「溫泉」という言葉の成り立ちや由来について解説
「溫泉」という言葉は、古くから中国の文献に記されていました。
中国では温泉が発達しており、その文化が日本にも伝わりました。
日本でも温泉の存在が古くから認識されていましたが、明治時代に入り、温泉地の整備が進んだことで、一般的に広まりました。
その結果、「溫泉」という言葉が一般的な呼称となりました。
「溫泉」という言葉の歴史
「溫泉」という言葉の歴史は古く、日本での記録は奈良時代の文献に見られます。
既に当時の人々は温泉の効能や利用方法を知っており、温泉を利用する文化が根付いていたことが分かります。
江戸時代に入ると、温泉地の開発が進み、多くの人々が温泉を利用するようになりました。
現在では、温泉地は日本各地に広がり、観光地としても人気を集めています。
「溫泉」という言葉についてまとめ
「溫泉」とは、自然から湧き出る温かい地下水のことを指す言葉です。
湯量が豊富で温度も高く、健康や美容に良い効果があるとされています。
読み方は「おんせん」となります。
温泉施設や旅行の際に使われることが多く、温泉地の整備が進んで明治時代に一般的な呼称となりました。
歴史は古く、温泉利用の文化が根付いています。
現在では、温泉地は日本各地に広がり、人々に癒しと楽しみを提供しています。