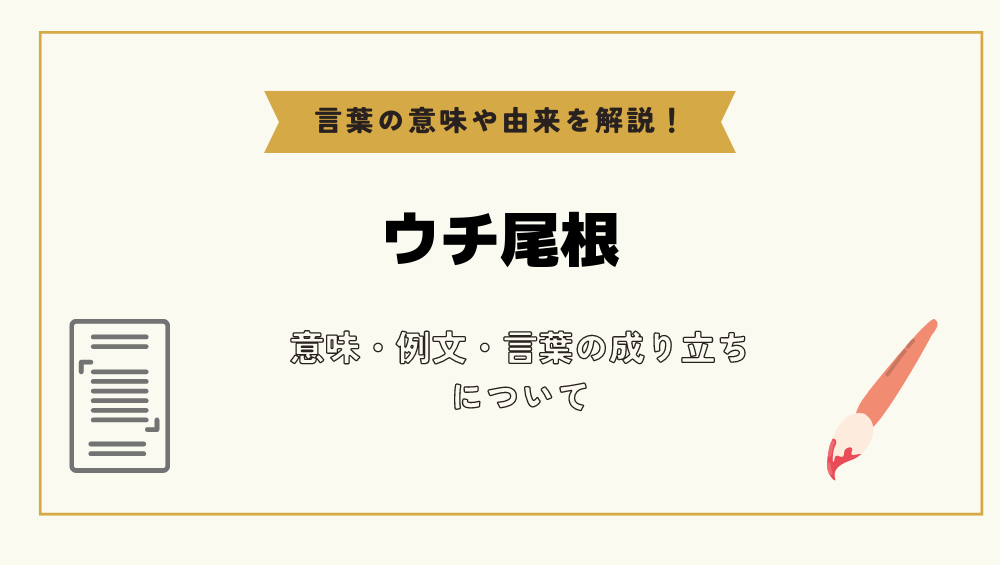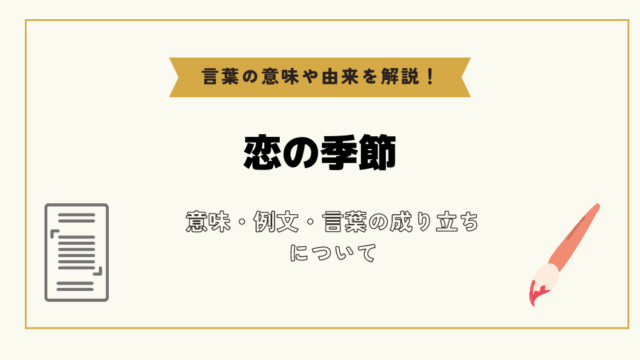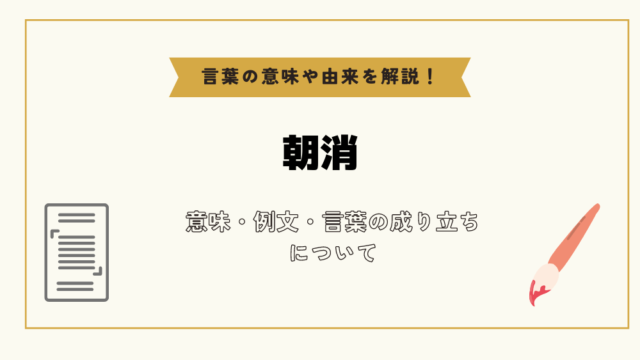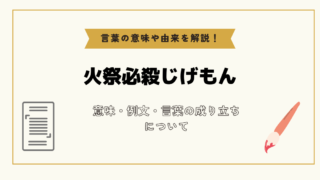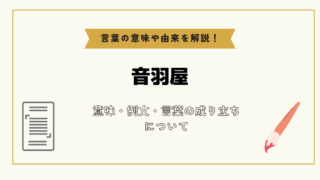Contents
「ウチ尾根」という言葉の意味を解説!
「ウチ尾根」とは、山や丘などの地形で、尾根の上部が広がった平地のことを指します。
ウチ尾根は、周囲の地形と比べて比較的平らで幅が広く、農地や集落などが存在することがあります。
また、ウチ尾根は水はけが良いため、農作物の栽培に適していることがあります。
「ウチ尾根」の読み方はなんと読む?
「ウチ尾根」は、読み方は「うちはね」となります。
長音記号の「ー」で繋がれた部分は、長くくっきりと発音するようにしましょう。
順番に読んでいくだけで、簡単に正しい読み方をすることができます。
「ウチ尾根」という言葉の使い方や例文を解説!
「ウチ尾根」は、主に地理や農業の分野で使用される言葉です。
地理学者や農業関係者などが、ウチ尾根の存在を調査したり、利用したりすることがあります。
例えば、「この地域はウチ尾根が多く、農業に適している」というように使われます。
「ウチ尾根」という言葉の成り立ちや由来について解説
「ウチ尾根」という言葉は、主に日本語の地理学用語として使われていますが、具体的な由来については明確な情報がありません。
ただし、地形に関する言葉であることから、昔の人々が山や丘の地形を表現するために生まれた言葉ではないかと考えられています。
「ウチ尾根」という言葉の歴史
「ウチ尾根」という言葉の歴史については、正確な情報が限られています。
この言葉が初めて使用された時期や文献なども不明です。
ただし、地理学や農業が発展していく中で、ウチ尾根の存在が注目されるようになり、その後広く使われるようになったと考えられます。
「ウチ尾根」という言葉についてまとめ
「ウチ尾根」という言葉は、山や丘などの地形で、尾根の上部が広がった平地を指します。
地理学や農業の分野で使用されることが多く、ウチ尾根は水はけが良いため農作物の栽培に適しています。
正しい読み方は「うちはね」であり、具体的な由来や歴史については明確ではありません。
しかし、ウチ尾根の特徴や利用については、多くの人々によって研究や使用がされています。